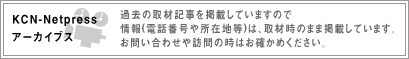燈りとの出会い
師匠から赤膚焼の名乗りを許され、師匠の世話で近くに窯も持つことができて武田さんの一人歩きが始まりました。その頃、奈良町の古い家を何かに使いたいと相談を受けたそうです。曲折を経て、結局は武田さんの仕事場に。

格子戸超えに見える武田さんの作品 |
|
「最初、家を見た時、生まれた家と雰囲気がそっくりで驚いたんです。大阪育ちなのに奈良とは不思議な縁があるんだと思います。平成4年から2カ所の仕事場を持つことになりました。最初は暇で、たっぷり時間がありましたから、透かしの技法に取り組んだんです。香炉や火屋など昔からあるんですが、手間な仕事でしょ、仕事の無い時代に根をつめて技を磨くにはうってつけ」
この時代に作った作品は、第一回奈良精鋭作家展で受賞、以後さまざまな受賞を受けました。主な仕事は茶道具ですが、透かし彫りをこれだけ駆使した作品はやはり人々の注目を受けます。陶器でできた灯りは、ガラスや紙とは光りを透さないということで、決定的に違います。彫りを施すことでのみ燈火器としての役を果たします。
「僕は手が不器用でしたから、人より努力しないと同じようにできないし、他の道で生きていこうと思えばできると思うんです。だからこそ、他のことをしないように暇でも陶芸以外のことはしなかった。もの作りとしての才能は無いんじゃないかな」
正攻法の修行を積んだ武田さんの作品は軽やかで使い勝手が良いのです。湯飲みやマグカップひとつにも何気ない造形の中に技と心が息づいています。薄く丁寧に引いた轆轤ならではの繊細な口当たりと手触りは、忘れられません。

奈良町の落ち着いた家並みの中の寧屋工房 |
|
「博物館や美術館へ行くと素晴らしい名品があって、とてもかなわないと思う。その中で私ができるのは、雰囲気を醸すものを作ること。奈良ならではの落ち着きや哀愁のあるものができたらと願っています」
シルクロードを通ってきて、まだ和の文化として熟成する以前の奈良を彷彿とする作品、そういうところで奈良を意識しているそうです。夏の短夜、陶燈の揺らぐ灯りに古代の幻想が浮かぶようです。
※8月7日から19日まで奈良市高畑の大乗院庭園で個展が開かれます。
題して「夏の夜に透かし模様の灯りが揺らぐー赤膚焼武田高明燈火器展」。
午後6時30分〜9時まで点灯(16日・19日は休み)。
同じ期間、寧屋工房でも個展開催中(10時30分〜午後6時30分)。
|