室内濃度指針値と室内濃度の温度変化
−ホルムアルデヒドの事例−
2002年1月14日
CSN #220
いわゆるシックハウス症候群など、室内空気中の化学物質汚染による健康影響が懸念され、表1及び表2に示すように、現在までにおいて、厚生労働省からいくつかの化学物質に対して室内濃度指針値または指針値案が示されています。
表1 厚生労働省が策定した室内濃度指針値(2002年1月14日時点、[1][2][3][4]をもとに作成)
|
化学物質* |
毒性指標 |
室内濃度指針値 |
|
|
μg/m3 |
ppm** |
||
|
ホルムアルデヒド1) |
ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 |
100 |
0.08 |
|
トルエン1),2) |
ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 |
260 |
0.07 |
|
キシレン1),2) |
妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 |
870 |
0.20 |
|
パラジクロロベンゼン1),2) |
ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響 |
240 |
0.04 |
|
エチルベンゼン1),2),3) |
マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響 |
3,800 |
0.88 |
|
スチレン1),2) |
ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 |
220 |
0.05 |
|
クロルピリホス4),5) |
母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響 |
1 |
0.00007 |
|
小児0.1 |
小児0.000007 |
||
|
フタル酸ジ-n-ブチル1),3),5) |
母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等への影響 |
220 |
0.02 |
|
テトラデカン2),6) |
C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響 |
330 |
0.04 |
|
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル3),5) |
ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 |
120 |
0.0076*** |
|
ダイアジノン4),5) |
ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 |
0.29 |
0.00002 |
|
アセトアルデヒド1) |
ラットに対する経気道曝露による鼻腔嗅覚上皮への影響 |
48 |
0.03 |
|
フェノルカルブ5) |
ラットに対する経口混餌反復投与毒性におけるコリンエステラーゼ(ChE)活性阻害等への影響 |
33 |
0.0038 |
|
総揮発性有機化合物量(TVOC)1),3) |
国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定 |
暫定目標値 |
− |
*1)-6)は表1の指針値策定方針のNo.を示す
**単位換算は25度
**フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)の蒸気圧については1.3×10−5Pa(25度)から8.6×10−4Pa(20度)など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.12から8.5ppb相当
表2 厚生労働省が審議中の室内濃度指針値(2002年1月14日時点、[1][2][3][4]をもとに作成)
|
化学物質 |
毒性指標 |
室内濃度指針値 |
|
|
μg/m3 |
ppm* |
||
|
ノナナール2),6) |
C8-C12混合物のラット経口暴露における毒性学的影響 |
41 |
0.007 |
*単位換算は25度
表1及び表2に示されるように、室内濃度指針値の単位は、基本的には質量/容積(例:μg/m3)で表されます。これは、化学物質の反応が、分子のモル数(質量/分子量または原子量)の比で考えるからです。しかしながら、これらの化学物質の室内濃度を測定するために用いられる高速液体クロマトグラム(HLPC)やガスクロマトグラム/質量分析計(GC/MS)などの分析機器を用いた分析方法や、一般的な簡易測定器では、分析作業が容易な体積濃度が用いられます。そのため、質量/容積で示される室内濃度指針値を体積濃度に換算する必要があり、表1及び表2において、体積濃度(例:ppm)が同時に示されています。
ただし、体積濃度は温度によって変化します。そのため、質量/容積の値から、必要な温度における体積濃度を計算しなければなりません。この計算には、簡易手法として理想気体の状態方程式を用いることができます。以下に、ホルムアルデヒドの例を示します。
ホルムアルデヒドの指針値:0.1mg/m3(100μg/m3)
(25℃換算で 0.08 ppm)
理想気体の状態方程式
PV=nRT
P:圧力(atm)
V:体積(リットル)
n:モル数(質量g/分子量または原子量)
R:定数0.0821
T:絶対温度(摂氏温度+273.15)
最初に0.1mg、25℃、1気圧での体積を求める
(ホルムアルデヒドの分子量: 30 )
V=nRT/P=(0.0001/30)×0.0821×(273.15+25)/1=0.0000815リットル
空気1m3=1000リットル
∴0.0000815/1000=0.082ppm (25℃)
同様に30度では、
V=nRT/P=(0.0001/30)×0.0821×(273.15+30)/1=0.0000829リットル
∴0.0000829/1000=0.083ppm (30℃)
同様に10度では、
V=nRT/P=(0.0001/30)×0.0821×(273.15+15)/1=0.0000788リットル
∴0.0000788/1000=0.079ppm (10℃)
以上のように、温度によって若干体積濃度が変化します。また、理想気体の状態方程式から明らかなように、質量から体積に換算するにあたり、温度以外にも、対象物質の分子量、圧力が変数となります。つまり、質量/容積の値から体積濃度に換算する時には、温度、対象物質の分子量、圧力が関係します。圧力は、室内濃度の場合、室内の気圧が関係します。気圧が大きく変化するようであれば、気圧を測定して換算しなければなりませんが、ここでは気圧は大きく変化しないという前提のもとに、温度のみを用いて換算しています。
一方で、実際の室内濃度は温度によってどのように変化しているのでしょう。図1に、内山らによって実際に測定されたホルムアルデヒドの室内濃度[5]と、井上らによって示されている温度換算式[6]を用いたホルムアルデヒドの室内濃度に対する温度変化の例を示します。
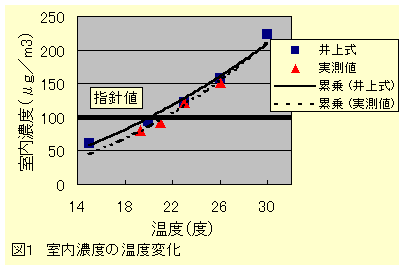
井上らによるホルムアルデヒドの室内濃度に対する温度換算式[6]
Ct=C×1.09(t-23)
Ct: t℃の気中濃度
C: 23℃の気中濃度
t: 測定温度
図1から明らかなように、実測値と温度換算式から得られた数値とは、傾向がよく一致しており、30度の時には約200μg/m3であったホルムアルデヒド濃度が、約20度になると厚生労働省の室内濃度指針値100μg/m3にまで低下します。これは、ホルムアルデヒドの放散源である建材からの放散速度が、温度によって大きく変化するからです。
ここで注意しなければならないのは、30度時のホルムアルデヒドの室内濃度と厚生労働省の室内濃度指針値を比較する場合、井上らの温度換算式を用いて25度時のホルムアルデヒドの室内濃度約150μg/m3を算出し、厚生労働省の室内濃度指針値100μg/m3(25℃換算で 0.08 ppm)と比較してはならないことです。正しくは、30度時の室内濃度約200μg/m3と室内濃度指針値100μg/m3を比較しなければなりません。
厚生労働省の室内濃度指針値が、25度換算で0.08ppmと示されていることに関係している可能性があるのですが、これまでこのような過ちを起こしている事例がいくつか存在しました。特に注意しなければならないのは、30度ではホルムアルデヒドの室内濃度指針値を超えているが、25度に換算すると室内濃度指針値よりも低いと示している事例です。このことは逆の例で示すと、15度でホルムアルデヒドの室内濃度が80μg/m3であった場合、25度では約190μg/m3に換算されることになり、室内濃度指針値を超えることになります。
実際の室内では、季節的あるいは日変動的な温度変化があります。井上らの温度換算式は、例えば昼と夜の変化や冷暖房時の変化を予測する場合には使えますが、30度や15度で実測された室内濃度を25度に換算して厚生労働省の室内濃度指針値と比較するために使用するものではありません。30度や15度で実測された室内濃度を、そのまま室内濃度指針値と比較しなければなりません。
以上の事例をまとめると、次のようになります。
- 「夏場30度で約200μg/m3(0.17ppm)であったが、25度に換算すると約150μg/m3(0.12ppm)となるため、厚生労働省の室内濃度指針値(25度で0.08ppm)の約1.5倍であった。」これは誤った解釈であり、約200μg/m3が実測されたのであれば、厚生労働省の室内濃度指針値の約2倍となる。
- 「夏場30度で約200μg/m3(0.17ppm)であったが、その日の気温が低下した夜間の25度では、約150μg/m3(0.12ppm)となる可能性がある。」このような使い方は、日変動を予測しているので使用可能。
このことを正しく理解しているところでは、例えば「年中を通じて、夏場の高温時では厚生労働省の室内濃度指針値を超えているため、引き続きさらなる対策が必要である。」と説明しています。つまり、秋・冬・春は室内濃度指針値を下回っているが、夏場の気温が高いときは、室内濃度指針値を超えていることを認めており、さらなる対策の必要性を認識しています。温度換算式の持つ意味と、室内濃度指針値の持つ意味をよく理解し、正しく実態を把握し、さらにそのことを公開する必要があります。
Author: Kenichi Azuma
<参考文献>
[1]厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室,「室内空気汚染問題に関する検討会中間報告書−第1回〜第3回のまとめ」, June 26, 2000
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1206/h0629-2_13.html
[2]厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室,「室内空気汚染問題に関する検討会中間報告書−第4回〜第5回のまとめ」, December 22, 2000
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1212/h1222-1_13.html
[3]厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室,「室内空気汚染問題に関する検討会中間報告書−第6回〜第7回のまとめ」, July 24, 2001
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0724-1.html
[4]厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室,「室内空気汚染に係るガイドライン(案)−室内濃度に関する指針値案−」, October 11, 2001
[5]内山茂久et al.,新築集合住宅における揮発性有機化合物の挙動と発生源の推定, 日本建築学会計画系論文集,第547号, pp75-80, 2001年9月
[6]井上明生,ホルムアルデヒド気中濃度のガイドライン対策,木材工業, Vol. 52, No. 1, pp9-14, 1997