1998年度環境庁ダイオキシン類蓄積状況調査結果
2000年3月6日
CSN #125
近年高度に発達した工業化社会の中で、工業製品として意図的に生成されるのではなく、廃棄物焼却や金属精錬など、反応過程における副反応物として生成されるダイオキシン類(以下、ダイオキシン)は、私たちの健康などに関わる重要な問題として、先進諸国をはじめとする世界各国でその対策が行われてきました。
最近日本でも政府による対策が進行し、2000年3月に「ダイオキシン対策推進基本方針を策定し、2000年7月には「ダイオキシン類対策特別措置法」が公布される予定となっています。
ダイオキシンは、その大半が大気中に放出され、土壌や水系へ拡散され蓄積していきます。大気、水系、土壌に拡散されたダイオキシンは、微生物から魚介類、鳥類、陸生生物などへと食物連鎖を通じて蓄積量が増大し、食物を通じて私たちの体内へと取り込まれていきます。そしてその摂取量、蓄積量に応じて、生殖系、発癌、免疫系など、様々な影響を生じるリスクが高くなります。
私たちの体内におけるダイオキシンの蓄積量に関して、日本の環境庁が1998年度実態調査報告書を1999年12月27日に発表しました[1]。その報告書では、ヒトや野生生物体内におけるダイオキシン蓄積量、精巣重量変化、陰膳方式による臭素系ダイオキシンの摂取量などについて報告されています。本稿では、その中からヒト組織中におけるダイオキシン蓄積量を取り上げて、図1に示します。また、欧州諸国との対比を図2に示します[1][2]。但し、図2の欧州諸国との対比図については、測定条件や換算条件などが異なるため、絶対値を単純に比較できません。
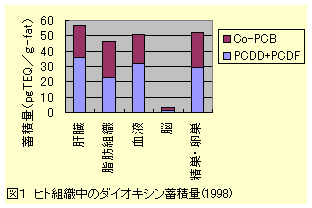 |
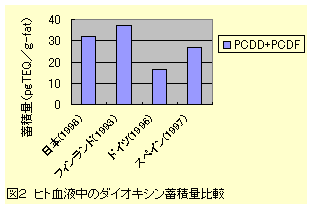 |
* PCDD:ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン、PCDF:ポリ塩化ジベンゾフラン、Co−PCB:コプラナーポリ塩化ビフェニール
* ( )内の数字は測定年度
ダイオキシンの摂取経路は主に食事からであり、消化器官から血液中に取り込まれます。その後、体内の各組織へと循環し、各々の組織で蓄積されます。1998年度環境庁実態調査において、血液中の濃度と組織中の濃度の相関関係を試算したところ、表1にように報告されています[1]。
表1 血液と各組織中のダイオキシン蓄積量の相関係数
|
|
肝臓 |
脂肪組織 |
脳 |
精巣・卵巣 |
|
相関係数(r) |
0.6089 |
0.5963 |
0.3934 |
0.1999 |
相関係数は、1に近いほど相関が高いと考えます。表1では、肝臓が最も相関係数が高く、血液中の蓄積濃度と肝臓中の蓄積濃度との相関性が高いと言えます。
図1の各組織中の蓄積濃度では、脳が最も低くなっています。脳内の血管には、血液−脳関門という関門があり、血管から脳への外来物質の移行を制限しています。しかしながら、少しばかり脳内へと移行しています。これは血管内皮細胞の細胞膜を、低分子の脂溶性化合物は、比較的容易に通過する[3]からです。このような脂溶性低分子化合物としては、ジエチルエーテル、トルエン、クロロホルムなどがありますが、ダイオキシンも、脂溶性低分子化合物の1つです。
ラットを用いた最近の研究では、胎仔期から新生期にかけて、ダイオキシンの中でも毒性が最も強い2,3,7,8-TCDDにさらされた雄ラットは、成熟してから雌の行動をするようになることがわかりました[4]。つまりダイオキシンは、脳の性分化に影響を与え、雄ラットの脳を雌のように変化させる可能性があると考えられます。
脳は、私たちの体の中枢であり、最も大切な組織です。脳から様々な信号が発せられ、それぞれの器官が機能しています。その脳へ、たとえ微量であってもダイオキシンが蓄積されている事実が判明しました。どのような影響が生じるかについて、できるだけ早急に解明する必要があると思われます。
表2 ヒトにおけるPCDD、PCDF、PCBの生物学的半減期([5]をもとに作成)
|
化合物 |
生物学的半減期(年) |
|||
|
子供 |
成人 |
|||
|
血液 |
血液 |
脂肪組織 |
全身 |
|
|
PCB混合物 |
2.8 |
7.1 |
|
|
|
2,3,7,8-TCDD |
|
|
|
5.8 |
|
2,3,7,8-TCDD |
|
|
9.7 |
|
|
2,3,7,8-TCDD |
|
7.1 |
|
|
|
2,3,7,8-TCDD |
|
11.3 |
|
|
|
2,3,4,7,8-PeCDF |
|
7.2 |
4.7 |
|
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
|
4.4 |
2.9 |
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
|
4.3 |
3.5 |
|
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
|
4.1 |
6.5 |
|
ダイオキシンの体内での半減期(濃度が半分に減少する時間)は、表2のように報告されています[5]。つまり表2に示すように、生体内での半減期が極めて長く、血液中で4.1-11.3年、脂肪組織中で2.9-9.7年にもなります。そのため、体内蓄積濃度は加齢とともに増加します。
図3に、1998年度環境庁実態調査において報告された、年齢と血液中における蓄積濃度の関係を示します[1]。
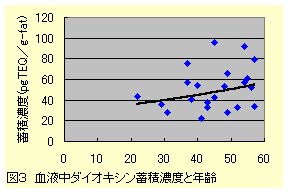
*試算に用いたダイオキシンは、PCDD、PCDF、Co-PCBの合計
図3から明らかなように、加齢とともに血液中のダイオキシン濃度が、増加傾向を示していることが示唆されています。
ダイオキシン1998年度環境庁実態調査におけるヒトの体内蓄積濃度によって、初めて全国レベルの現状把握ができました。しかし、世界保健機関(WHO)の専門家委員会の報告によると、先進工業国における、現在のダイオキシン類摂取量(2-6 TEQ pgTEQ/kg体重/日)や、体内蓄積量(4-12 ngTEQ /kg体重)によって、ある部分では、一般の人々の微妙に影響が生じている可能性があることを認めています[6]。
今後はさらに、健康影響との関連性を調査し、どのような影響が生じているについてできるだけ早く明らかにする必要があると思われます。
Author:東 賢一
<参考文献>
[1] ダイオキシン類の人体、血液、野生生物及び食事中の蓄積状況等について−平成10年度調査結果, 環境庁 環境保健部 環境安全課, December 12, 1999
http://www.eic.or.jp/kisha/199912/66354.html
[2] Report
produced for European Commission DG Environment
UK Department of the
Environment Transport and the Regions (DETR),
Compilation of EU Dioxin Exposure
and Health Data, October 1999
http://europa.eu.int/comm/environment/dioxin/
"Dioxin
exposure and health"
[3] 筏 義人, 環境ホルモン, 講談社, 1998
[4] 松本 明, 日本内分泌攪乱化学物質学会 第四回講演会テキスト, pp10-16, February 28 2000,
[5] 宮田秀明, 廃棄物学会誌, Vol. 8, No. 4, pp301-311, 1997
[6] Assessment of the health risk of
dioxins: re-evaluation of the Tolerable Daily Intake (TDI) WHO Consultation,
May 25-29 1998, Geneva, Switzerland
http://www.who.int/fsf/dioxin/whoinf.htm