室内空気汚染に関するアメリカ連邦政府の研究活動状況
2000年3月12日
CSN #126
私たちは1日の大半を、室内で過ごしています。そのため、室内空気環境が快適でなければならないことは、言うまでもありません。しかしながら近年、室内空気環境は、たばこの煙・揮発性有機化合物などの化学的因子、カビ・ダニ・細菌などの生物的因子、ラドン・電磁波・音振動などの物理的因子によって汚染されています。またWHO(世界保健機関)は、年間約300万人の死亡者のうち、280万人が室内空気汚染であると試算しています[1]。
アメリカ合衆国では、環境保護庁を初めとする連邦政府機関が、公衆衛生上に対する最も深刻な健康リスクの1つとして、10年以上も前から室内空気汚染を取り上げてきました。また汚染物質に対して高い感受性を有する乳幼児や老いた人たちは、1日のおよそ90%を室内で過ごしていますので、特に注意が必要です。
1999年8月に発表された、アメリカ会計検査院(General Accounting Office: GAO)による室内空気汚染の研究活動状況報告書によると、これまでアメリカ連邦政府機関は、1987年から1999年まで室内空気汚染の研究に、全体で約11億ドル支出してきました[2]。その結果、室内空気汚染の解明と対策において、著しい進歩を遂げました。ただ現在でも、表1に示す不確定要素があり、表2に示すアメリカ連邦政府の研究機関によって、研究が継続されています。また、それぞれの機関によって支出された室内空気汚染の研究に関わる費用は、図1、図2のようになっています[2]。
表1 アメリカの室内空気汚染研究における不確定要素([2]をもとに作成)
|
No. |
不確定要素 |
|
(1) |
汚染源の特定 |
|
(2) |
汚染物質への曝露のメカニズム |
|
(3) |
複合した化学的汚染要因、生物的汚染要因への低濃度曝露による長期及び断続的な健康影響 |
|
(4) |
汚染源、曝露、健康影響を削減する最も効果的な費用効果戦略 |
表2 室内空気汚染の研究を行っているアメリカ政府機関の研究活動組織([2]をもとに作成)
|
研究活動組織 |
|
|
国立標準技術研究所 |
NISH (National Institute of Standards and Technology) |
|
国立労働安全衛生研究所 |
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) |
|
消費者製品安全委員会 |
CPSC (Consumer Product Safety Commission) |
|
国立がん研究所 |
NCI (National Cancer Institute) |
|
住宅・都市開発省 |
DHU (Department of Housing and Urban) |
|
国立アレルギー感染病研究所 |
NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) |
|
エネルギー省 |
DOE (Department of Energy) |
|
環境保護庁 |
EPA (Environmental Protection Agency) |
|
国立心肺血液研究所 |
NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institute) |
|
国立環境衛生科学研究所 |
NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) |
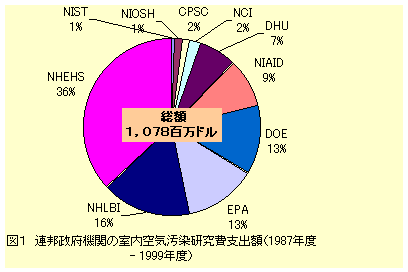 |
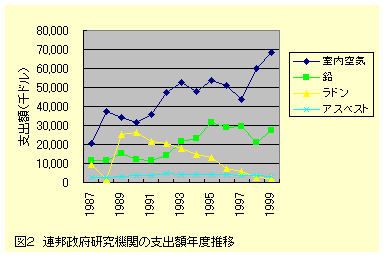 |
表2、図1から明らかなように、非常に多くの研究機関によって、室内空気汚染に関わる研究が行われてきており、多額の研究費が支出されてきています。また図2から明らかなように、室内空気汚染に関する研究費は、年々増加しています。表3には、現時点におけるアメリカ室内空気質委員会のメンバーを示します。
表3 現時点におけるアメリカ室内空気質委員会のメンバー([2]をもとに作成)
|
|
連邦政府機関 |
|
|
合同議長 |
環境保護庁 |
EPA (Environmental Protection Agency) |
|
消費者製品安全委員会 |
CPSC (Consumer Product Safety Commission) |
|
|
エネルギー省 |
DE (Department of Energy) |
|
|
国立労働安全衛生研究所、 |
NIOSF (National Institute for Occupational Safety and Health) |
|
|
職業安全衛生管理局 |
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) |
|
|
他の機関 |
ボンヌビル電力事業団 |
BPA (Bonneville Power Administration) |
|
農務省 |
DA (Department of Agriculture) |
|
|
国防総省 |
DOD (Department of Defense) |
|
|
住宅・都市開発省 |
DHUD (Department of Housing and Urban Development) |
|
|
内務省 |
DOI (Department of Interior) |
|
|
司法省 |
DOJ (Department of Justice) |
|
|
国務省 |
DOS (Department of State) |
|
|
運輸省 |
DOT (Department of Transportation) |
|
|
財務省 |
DOT (Department of Treasury) |
|
|
連邦政府調達局 |
GSA (General Services Administration) |
|
|
航空宇宙局 |
NASA (National Aeronautics and Space Administration) |
|
|
国立標準技術研究所 |
NISH (National Institute of Standards and Technology) |
|
|
連邦議会事務局 |
Office of the Architect of the Capitol |
|
|
中小企業庁 |
SBA (Small Business Administration) |
|
|
テネシー峡谷開発公社 |
TVA (Tennessee Valley Authority) |
|
|
アメリカ情報局 |
USIA (U.S. Information Agency) |
|
これらの内容から明らかなように、アメリカでは室内空気汚染の研究に対し、非常に多くの政府機関が連動し、多額の費用が支出されています。
日本では、1996年7月に建設省を中心とする4省庁の協力で「健康住宅研究会」が結成され、1998年3月まで研究が行われ、健康影響の少ない住宅を建設するための「設計施工法」および「住まい方」のガイドラインが設定されました。また1998年4月から日本建築学会が、「室内化学物質空気汚染調査研究委員会」を発足し、化学、医学、社会科学分野の研究者が共同で、居住環境の実態調査、人体に対する汚染調査と医学的影響の解明、化学物質抑制対策手法の開発、設計・施工者のための汚染防止対策総合評価システム開発に関わる研究を開始しました[3]。
厚生省は、1997年度厚生科学研究「アレルギー研究班」において、化学物質過敏症の問題を取り上げ、この疾患の概念、診断、治療に関する医師向けのパンフレットを作成しました。また1997年から居住環境中における揮発性有機化合物の全国実態調査を行っており、化学物質のクライシスマネジメントに関する研究として、化学物質過敏症の研究・調査を行いました。そして1998年からは室内空気中の化学物質に関する調査研究、1999年からは住宅における居住環境の実態調査を推進しています[4]。
このように日本では1996年頃から徐々に室内空気汚染に関する研究が拡大し、少しずつ実態が明らかにされつつあります。しかし、アメリカほどグローバルに展開されていないのが現状です。私たちの生活空間において最も重要な室内環境が快適で健康的となるように、日本もこれまで以上に力を入れて、さらに国際協力も含めてグローバルに研究が推進されることを願います。
Author:東 賢一
<参考文献>
[1] CNN Environmental News Network, Air pollution kills but deaths can be prevented, August 30, 1999
http://cnn.com/NATURE/9908/30/air.pollution.enn/
[2] Indoor
Pollution: Status of Federal Research
Activities, General Accounting Office (GAO), RCED-99-254, August 31. 1999
http://www.gao.gov/AIndexFY99/abstracts/rc99254.htm
[3] 坊垣和明, アレルギー・免疫, Vol. 6, No. 7, pp1018-1025, 1999
「化学物質過敏症(MCS):健康住宅」
[4] 阿部重一, アレルギー・免疫, Vol. 6, No. 7, pp1026-1030, 1999
「化学物質過敏症(MCS):行政の取組みについて」