 Poem BBSでは poemを募集しています
Poem BBSでは poemを募集していますご気楽に投稿下さいませ
 Poem BBSでは poemを募集しています
Poem BBSでは poemを募集しています
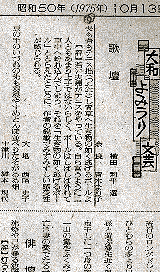 |
福岡から縁あってこの奈良の地にきました。 最初に夫の母から手ほどきを受け、作ったのがこの短歌です。 それ以来しばらく「短歌」の言葉遊びをしていました。(^^;) 各新聞に載せていただいた「短歌」のみです。(これしかない!?) 今は、まったく遠ざかっていますが、これらの歌であの時を思い出しています。 「むつき」は「おむつ」の事、「夫」は「ツマ」と読みます。 子供が小さい時は、手作りの「洋服」や機械編の「服」、手作り「ケーキ」や「パン」等に夢中になったのですが、やはりすっかりご無沙汰して、今はもう大きい子供達から文句が出ています。(^^;) 1997.8.23 |
|
こころとこころのふれあい -総合福祉センターを訪ねて- 十二月九日は「障害者の日」。 心身障害者福祉作業所では、義務教育を終えた子どもたちが障害の程度に応じて、部品組み立て、印刷、草引きなどと色んな作業種目をこなしています。 単純な組み立て作業を黙々と熱心にこなしている子もいれば、隣の子にちょっかいをかける子。また、「今日はうれしい給料日!」とはしゃいでいる子。言葉が不自由でも機械で言葉を打ち出し日記をつけている子。どの顔もみんな、生き生きと輝いて、明るい声が響きます。お世話くださる職員の方々の温かい「こころ」が伝わってきます。 印刷も手慣れたもので、プロの仕事と変わりありません。みなさんの注文をお待ちしていますとのこと。「名刺」「プログラム」「広告」「封筒印刷」なんでもござれです。 草引き作業に熱心な姿勢に頭が下がります。 帰り際に、お茶のサービスをしてくれた子がいました。自分も障害を持っているのに人のお世話をすることが大好きな子です。どうもありがとう、とてもおいしかったです。 この作業所は、収容能力が限度にきている関係で、親御さんたちが立ち上がり、社会福祉法人「ならやま会(仮称)」を組織し、子どもたちが自立の 一歩を築くために働く技能と喜びを得る環境を作ろうと活動されています。また、センター内でも点字など各種ボランティアグループの活動や、手話教室も開かれ、この時はバザーに向けての準備など多くの人たちが忙しく、和気あいあいと働いておられました。 「なにかお手伝いをしたいのだけれど」と思つているあなた、困っている人を見かけてもドキドキして行動に移せなかったあなた、少しの勇気を出してみませんか。「こころ」と「こころ」のふれあいを味わいたいと思いませんか。 あなたの思いやりを行動に! 障害を持つ人が一歩街へ出ると、多くの壁にぶつかります。そういった時に、まわりにいるわたしたちには何かできるでしょうか。 まず、声をかけましょう。「何かお困りですか?」障害を持つ一人ひとりが全て違います。そして自立しようと努力をしています。時には、見守つていてくれる方がありがたいこともあるのです。 そして、必要ならば快くお手伝いしましょう。障害をもつ人を特別現したり、無能力扱いをしないことが大切です。 また、まわりのちょっとした身勝手が、障害を持つ人の多大な迷惑になっていることがあります。例えば、駅前やデパート付近でよく見られる放置自転車。車イスの人にとって大きな障害物となり、視覚障害者の唯一の道標である誘導ブロックをふさぎ、通行の妨げとなります。このようなことは、ちょっと気を付ければ避けられることです。みんなのちょっとした「勇気」と「思いやり」そして「気配り」で、すべての人が明るく、幸せに暮らせる街にしましょう。 |
|
未来の芸術家に心から拍手を ー青年作品展を見てー 1991.3 なら しみん だより 奈良市の「第六回青年作品展」が、一月三十日から二月三日まで東寺林町のならまちセンターで開かれました。 昭和六十年の「国際青年年」を記念して始まったこの作品展は、高校生から社会人(30歳)までの作品の発表の場として好評で、今回は百八十点もの作品を鑑賞する機会を得ました。 日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の六部門に分かれ、それぞれが若者らしく新鮮でみずみずしく、どの作品もまじめに素直に自分を表現しているのが印象的でした。 その中で、「市長賞」を獲得された二人にお話をうかがいました。 彫刻部門の市長賞の作者は、まだ十六歳の県立高円高校二年生のお嬢さんです。学校の授業でクラスメートとお互いに励まし合いながら、ノミを手に石材と格闘して十カ月。 「夢と希望と悩みの青春時代の自分を表現しました」と答えてくださった宇都宮素子さんのかわいい笑顔に、彼女の分身のような「願う私」と命名された石材が一緒にうなずいているようでした。 工芸部門は、花器、陶版画、しぼり染めと種類が多く並ぶ中、ひときわ目をひく作品がありました。それが「花うさぎ」と命名されたグリーン色の着物です。うさぎ、波、花などが、肩に、すそに、まるで物語のように丁寧に描かれています。 「子どものころは、絵がきらいでした」と話される松本佳子さんは、現在絵画教室の先生で、帝塚山短期大学で染色の授業の助手もなさっています。 「毎日が忙しく、作品に取り組む時間が一日に少ししか取れなくて」「着物はこれで三作目です」「自分の作品を着られることが楽しみです」「この作品展に出品できる最後の機会に入賞できて、とてもうれしいです」と話してくださいました。 最終日午後三時からは、表彰式が行われました。青年作品展だけあり、さすがに学生服(高校生)が多く目立ちました。工芸・写真部門は男子が優位でした。表彰をうけるどの顔もはればれと輝いて、未来の芸術家に心から拍手を送りました。 賞に入っていなくても、印象に残る作品が多くありました。応募作品はすべて展示するという趣旨はすばらしく、この作品をより多くの人に見てもらえるようにと願います。 そして、それが青年芸術家の励みとなり、奈良市から未来のピカソ、セザンヌ、ロダンが生まれてくることを楽しみに会場を後にしました。 |
