 |
 |
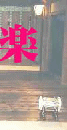 |
| 鉦鼓 | 太鼓 | 羯鼓 |
| 奈良には「南都楽所(なんとがくそ)」と呼ばれる雅楽を継承し広く活動している組織があります。実際に雅楽を演奏し、舞を舞う人たちで構成されています。演奏活動をするかたわら、技量の錬磨を中心に、調査・研究や記録の保存、後継者の育成、楽器・装束の複製なども行っています。 雅楽は、奈良時代にシルクロードの各地にあった音楽・舞が中国や朝鮮半島を経由して遥々我が国に伝わり、平安時代には日本古来の神楽などと共に音楽、舞が整えられ、現在の形が確立されたようです。 |
|
 |
 |
| 春日大社中元万燈籠の夕暮れ 直会殿で奉納された舞楽「賀殿(かてん)」 | |
| 奈良時代から現在まで雅楽の伝統を伝えている「南都楽所(なんとがくそ)」とはどんなものかを紹介しましょう。 雅楽は日本に伝わった当時から、神道や仏教への奉仕(奉納)の役割や宮廷の儀式音楽の役割をもち、奈良に於いては現在でも春日大社、氷室神社、東大寺、興福寺、薬師寺、唐招提寺、法隆寺などで奉納されています。年間には20もの行事になるとのことです。 明治維新により東京に遷都されたことに伴い、当時京都・奈良・大阪にあった楽所(三方楽所と呼ばれていた)の楽人を東京に呼び寄せ、宮内省雅楽局を作ったものが、現在の宮内庁式部職楽部と成ったものです。 奈良の地に残った南都楽所の楽人達が結集し、奈良時代からの伝統を継承し続けてきたものが、現在の「南都楽所」なのです。 現在南都楽所の会員は約100名であり、毎週土曜日の夜、奈良市餅飯殿(もちいどの)町大宿所で練習をしています。会員は、まず、管楽器のうち、笙・篳篥・笛を学び、弦楽器は琵琶か箏のどちらかを学ぶことになっています。打楽器については、太鼓、鉦鼓は進度に応じて指導を受けますが、鞨鼓は指揮者の役割をする楽器であり、楽頭が常に演奏することになっています。 舞は左方(中国・インド・東南アジア地方−大陸系のもの)、または右方(古代朝鮮半島[新羅・百済・高句麗]および渤海地方など半島系のもの)のどちらかを選択することになっています。このように打楽器以外は初めに選択したものを修生変えてはならないことになっています。 |
|
