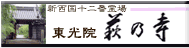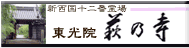- 仏日山吉祥林 東光院 萩の寺
-

当院は新西国三十三ヶ所第十二番の霊場にして、天平年間(735年)行基菩薩の草創にかかり本尊は同菩薩自作の薬師如来と十一面観世音ならびに、重文(旧国宝)降魔座釋尊を安置す。
孝徳天皇の御宇、豊崎村下三番(現大阪市北区中津)にて行基菩薩火葬の方法を伝授したるを起縁とし、薬師堂建立したるをその初めとす。
その際、死者の霊を慰めるため、当時淀川水系に群生する萩を供花として霊前に捧ぐ。
当院の萩、植栽の起縁なり。
延宝九年、相州功雲寺、霊全和尚来住し、初めて曹洞宗籍に入り、仏日山吉祥林東光院と称す。
別格地寺院なり。
文化年間、弥天一州禅師、当時大坂十人両替の殿村平右衛門(米平)中原庄兵衛(鴻庄)両開基家と協力、伽藍を再興して今日に至る。
境内には、相州小田原道了大権現を歓請し、また隠岐国あごなし地蔵尊を遷座し、阪急沿線西国七福神毘沙門天王を安置す。
前庭後園萩多きを以って通称萩の寺と呼び花時雅客の杖を曵くもの多し。
尚、昭和五十年には淀君ゆかりの「萩の筆」を復興し、また同六十三年当山授戒会を記念してスリランカ国より「アヌラーダプラ仏舎利」が贈られ、六百年ぶりに「こより観音写経大衣」が新調されるなど話題多し。
(東光院萩の寺 冊子より)
|