茶道具のページ
私たちの住む高山は竹製品の産地として有名です。特に茶せんは全国の80%を占めています。春には田んぼなどに竹干しが見られます。そして、高山竹林園という施設の中には、資料館、竹生庵、日本庭園があります。資料館には竹で作った編み針・花入れ・柄杓・茶杓などたくさんのものが展示してあります。
(左上)高山サイエンスプラザ付近には茶せんをモチーフにした街灯もあります
(右上)高山竹林園
(左下)竹林園資料館に展示されている花入れ
(右下)竹林園資料館に展示されている編み針その他
私たちは、茶杓を作っている三原さんの家に取材に行き、お話を伺いました。
その時の一問一答です。
Q.竹の種類は主に何を使いますか?
A.茶せんはハッチクを使うが、それ以外はマダケを使います。竹にもいろいろ性質があるので、用途によって使い分けます。
 柄杓を削る三原さん
柄杓を削る三原さん  柄杓の形いろいろ
柄杓の形いろいろ  マダケ
マダケ
Q.作るときには何に注意していますか?
A.品物によって違いますが、一般的に茶杓はピカソの絵と同じように何十、何百年と残るものなので、何かを訴えかけるように、使いやすいように作っていきます。
Q.何に苦労しますか?
A.手作業でやっているので、時間に追われます。お茶の道具としての約束ごとを守らなければならないし、その他いろいろ考えを入れながら作らなければならないということもあります。
また、後継者にも困ります。
Q.この仕事をしていて、いいと思うことは何ですか?
A.この辺りをまわるコースに茶杓削りなどが入っていて、そのお客さんが喜んでくれることや、お茶会の時に自分の名前が出てくるのがうれしいし、誇れるということです。
Q.何年ぐらいこの仕事をしていますか?
A.十八年ぐらいになります。父親の代からだと、六十年程になります。
Q.一人前になるにはどれぐらいかかりますか?
A.一生が修行だと思っています。
その他
「茶杓の節には何か意味があるのですか?」
茶杓は、真・行・草という種類に分けられるそうです。種類によって節のあるなしがあるそうです。また、伊勢神宮の木などいわれのある木で作られた茶杓もあります。節の位置は、家元の人の好みにより変わるそうです。

節が一つある草(左)と節のない真(右)。お茶会で客をもてなすため客の好みの字を入れます。
ご協力くださった三原さん、ありがとうございました。



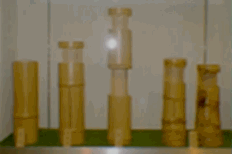
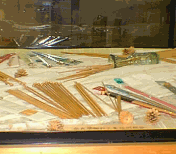


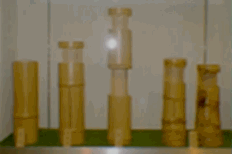
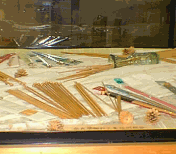
 柄杓を削る三原さん
柄杓を削る三原さん  柄杓の形いろいろ
柄杓の形いろいろ  マダケ
マダケ