拾遺集、伍 Aus meinem Papierkorb, Nr. 5
ゼルタース水 Selterswaſſer
目下ドイツでは DTA (Deutsches Textarchiv) と呼ばれる文献のデジタル化プロジェクトが進行中。これを行っているのは「ベルリン=ブランデンブルク・アカデミー」(*)で、2007年から2014年の間に、17世紀後半~19世紀のあらゆる学問分野のドイツ語による基本的文献1300点をデジタル化してネット上に公開し、自由な利用に供するというプロジェクトで、現在 (2012年3月) すでに700点くらいが完成している。ドイツ語テキストの電子化は「プロジェクト・グ-テンベルク」や「ウィキソース」、また最近では「グーグル・ブックス」等によって急速に進んでいるが、それらに対してこのプロジェクトは「テキストとその版の選択、再現の正確さ、信頼性で区別される」と宣言している。
このプロジェクトの、すでに電子テキスト化を終えた作品リストを見ていて、中にアントニウス・アントゥスの『美食講義』が含まれているのを発見した。アントニウス・アントゥス Antoninus Anthus は精神病理学者グスタフ・ブルームレーダー Gustav Blumröder の筆名であり、異色の人物であって、前川道介先生がかつて次のように紹介されている。
ブルームレーダーの美食の本はユーモラスな独断と偏見に満ちた痛快なものだが、フェルストやカール・フリードリヒ・フォン・ルモールの陰に隠れて知る人は少ない。しかし大分変わった経歴の人物で、最初ヴュルツブルク大学で医学を修め、精神病理学者となったが、文学、音楽、絵画にもすぐれるという多才ぶり、文学ではやはりマルチ人間だったホフマン熱愛者だった。医学論文においても神経組織に宿る善の原理をペルシャ神話に倣ってオルムッド、血液に宿る悪の原理をアーリマンと名付けるなど、いささか文学的神秘的なイデーを説いたため大学教授の椅子を逸し、田舎町の裁判医をしていたが、その地方の人望をあつめた。一八四八年の革命の年にはフランクフルトの国民議会の議員に選ばれたものの、実行力のある統率者を欠いた国民議会は議論だおれの末、結局解散に追い込まれた。彼も逮捕され、獄中で肺疾を患っていた体をさらに痛め、故郷ニュルンベルクで亡くなっている。このテキストをダウンロードして所々拾い読みをしているうちに、一箇所おやと思う記述が目に留まった。食事と飲み物の関連を論じている中である。
前川道介『愉しいビーダーマイヤー』(国書刊行会 1993)
食事中に水を飲む人々と付き合うくらい美食家にとって耐えがたいことは無い。--グラス一杯の新鮮な水--清浄な白紙!--を就寝直前か起床直後に、あるいはいつでも時と場合に応じて、夏であれ冬であれ、それだけならさっぱりした飲み物として理にかなっている。ワインと砂糖を添えたゼルタース水のビンは、暑くて埃っぽい夏の日の木陰にはうってつけである。--しかし食事中に水となると、ソースたっぷりで脂っこい熱々の料理の折には尚更だが--消化に関する二、三の § § だけでも読んだ者は誰しも知るように、健康に良くない、それどころか美食の徒には全く相応しくない。そして水に次ぐ卑俗な飲み物はビールで、食事中はワインに限る、というのが彼の主張である。それはともかく、ここで時と場合によっては悪くないとして挙げられている「ゼルタースの水」とは、ヴィースバーデンの北に広がるタウヌス山地ゼルタースで汲まれる炭酸水である(だから「ゼルター水」ではなく「ゼルタース水」となろう)。この水は健康に良いとして昔から有名で、陶製の容器に詰められてヨーロッパ中で販売され、ゼルタースという名称は発泡性ミネラルウォーターを意味する普通名詞となった。アメリカでは今も seltzer water として売られているがこれはもちろん、自然のミネラルウォーターではなく人工の炭酸水である。
Der Eßkünſtler wird Leute, die über Tiſch Waſſer trinken,
für Alles eher als für Collegen halten. — Ein friſches Glas
Waſſer — ein leeres Blatt Papier! — unmittelbar vor Schla-
fengehen oder nach dem Aufſtehen, oder für ſich in Zwiſchen-
zeiten je nach Bedarf und Verhältniß, Sommer oder Winter etc.
iſt etwas Erfriſchendes, Zweckmäßiges; ein Krug Selterswaſſer
mit Wein und Zucker in einer ſchattigen Laube an einem heißen
ſtaubigen Sommertag etwas Treffliches; — Waſſer aber
während eines Gaſtmahles überhaupt — zu warmen, ſaftigen,
fetten Speiſen beſonders — iſt nicht nur undiätetiſch, wie jeder
weiß, der nur ein paar § § über Verdauung geleſen, ſondern,
was mehr iſt, durchaus unkünſtleriſch.
-- Antonius Anthus: Vorleſungen über Esskunst. Leipzig, 1838.
さて、何に注意を引かれたかというと、「ワインと砂糖とゼルタース水」の取り合わせである。前に書いた《ワインと砂糖!》で、俳優ルートヴィヒ・デフリントが舞台を終え、行きつけの酒場ルター・ウント・ヴェーグナーで「ワインと砂糖!」と注文する場面について、ワインに砂糖を混ぜて飲むのか砂糖を舐めながらワインを飲むのか、この取り合わせが不思議だと記した。しかし美食の本でこう書かれるのだから、奇とするほどのことはないかも知れないのか・・・ かつて南ドイツに滞在中、夏にはカフェでショルレ Schorle と呼ばれる、白ワインを炭酸水で割った飲み物をよく飲んだ。周りで同じものを飲む客も多かったが、砂糖を溶かしたり舐めたりする光景は見た覚えがない。
表記について一言。従来のフラクトゥーア文字をつかった表記では、s の文字にはギリシャ語とおなじく二種類あった。ドイツ語では「長いs」Langes s «ſ» と「丸いs」Rundes s «s» である。ドイツ語をラテン文字で表記するとき «ſ» は使用しないのが普通だが、DTA のテキストではフラクトゥーアと同様に使い分けられている。
もう一つ。引用した箇所の下から2行目にある § § はテキスト中でここだけに出現する。電子化の産物かと思って原テキストを見ても同じく存在する。前後の文脈から「本、著作、論文」の類の語が入るべき個所だと思うが意味がよくわからない。あるいはドイツ語で法律の条文、教則本の項目などをパラグラフと呼び、§ で表すので、消化に関する医学テキストの項目(複数だから § § )ということか。
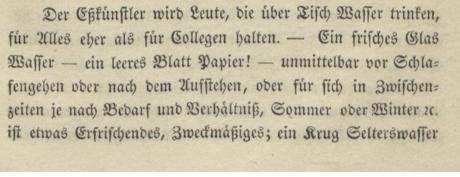
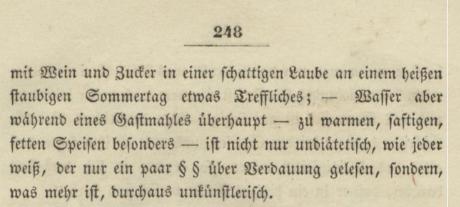
(DTA "Antoninus Anthus: Vorleſungen über Esskunst." より)
* 「ベルリン=ブランデンブルク・アカデミー」はドイツ再統一後の1992年にベルリンとブランデンブルク両州の約定により設立された。遡ればライプニッツが初代総裁となって創設された「王立プロイセン・アカデミー」の系譜を引く学会と言える。
朗らかな憂鬱 heitere Melancholie
前項でアントニウス・アントゥスが『美食講義』中、食事中の飲み物として最悪なのが《水》、それに次ぐ「俗悪極まりない飲み物」が《ビール》と断じていることを紹介した。彼のビール攻撃は激烈で、ドイツの人々は詩的な言い回しだとでも思ってかビールを「液体のパン」などと呼んで、町でも村でも至るところで飲んでいるが、「ともかくも舌というものを持ち合わせている人間が何故に食卓でビールを飲むことができるのか、今に至るも解けない問題だ」、スープにビールから始まって、牛肉の煮込みに、サラダに、テリーヌに、挙句にはデザートにまでビールという「身の毛のよだつ」光景を目にした。これは「不趣味と野蛮の極致」だと非難する。ただし、ビール追放を求めるのはあくまでも食事中のことで、ビールそのものを咎めているわけではない、ビールにも取り柄がある、とアントゥスは言うのだが、それも何か皮肉というか風刺というか、含むものがある言いかただ。
食事中のビールに異議を唱えるに熱心だからといって、誤解しないでいただきたい。食事でなければ私自身ビールを飲まないわけではない。ビールを飲めばまた晴れ晴れと憂鬱な気分になれるのである。しかし物事にはいろいろな側面があって、例えば、取り返せぬ喪失、癒されることのない喪失による痛苦を引きずっている人生、あるいは「理想」という辛辣な発酵する毒液に貫かれている人にとっては、これで精神を高揚させるロマンチックな原理が与えられるが、しかしそのような人はビールを飲みすぎないよう用心しなければならない。晴れ晴れと憂鬱な気分になる、とはまた言ってくれますね。どんな気分なのか、どんな有様なのか。このアントニムの組み合わせはどう解釈できるのか。酒を飲んで日ごろの憂さ晴らしをする連中、酔ってやたら「理想」に燃えて大言壮語する人間たちを揶揄しているようにも思える。ひょっとしたら、時代は下るが、マーセンの語る学生酒場の情景を見れば、解釈のヒントが見つかるのではないだろうか。
Ich bitte, nicht mißverſtanden zu werden, indem ich gegen das Biertrinken über Tiſch eifere. Ich trinke ſelbſt außer Tiſch nichts weniger als ungerne Bier. Man kann ſich auch damit in die heiterſt melancholiſche Stimmung verſetzen. Doch hat’s ſeine Seiten, z. B. durch weſſen Leben ſich der Schmerz eines unerſetzlichen und unverſchmerzlichen Verluſtes zieht, oder wen der ätzende und ſtachelnde ſauerteigige Gifttropfen „Ideal“ durchdrungen, dem iſt zwar ein hebendes romantiſches Prinzip eingegeben, doch hat ſich derſelbe ſehr zu hüten, nicht zu viel Bier zu trinken.
-- Antonius Anthus: Vorleſungen über Esskunst. Leipzig, 1838.
完璧を目指したため未完に終わったホフマン全集の編者カール・ゲオルク・フォン・マーセンは、日常の奇矯な行動で知られ、また様々な分野で多彩な才能を発揮したことでも有名である。美食探求の方面では『食事の知恵』を著したが、そのビールの章でアントス『美食講義』の「怒鳴り立てるビール攻撃」に触れ、確かに贅沢な食卓にはワインが相応しいと認めつつ、質素な食事には良質の新鮮なビールが合うとビールを擁護する。さらに単なる飲料を超えて持つ「気分上の要素」を見逃すことができないと強調する。
およそ大学生の身分となった者でなければ、ビールに潜む至高の浄福を味わい尽くすことはできない。入学して初めて学生規範に則る酒場に立ち入ることを許された日々が、わが人生のもっとも晴れやかな日々だったと私は今日でも思っている。この世のいかなる飲み物がたぎりたつ青春の高揚に、至福の気分に適するというのだろうか。--何人か不機嫌な顔が薄暗い居酒屋の部屋にうっそりと座りこんでいる。そこへ、扉が開いてはつらつとした若者の一群がわっと入場するや、先の連中も立ちあがる。こぼれる笑顔で椅子を手に取り三々五々、古い樫のテーブルに席を定める。黄金の液体に白い泡のキャップを被った重いジョッキが持ち上げられ渇いた喉へと向かう。早くも最初の歌が沸き起る。アントニウス・アントゥスことグスタフ・ブルームレーダーも大学に入学したとき、同様の体験をしたのではないか。学生酒場の「至高の浄福」こそが「晴れ晴れと憂鬱な気分」の原型となった。これが精神病理学者によるひょんな表現の解釈として正しい方向なのではあるまいか。自信は無いけれど。
「わが町一番のビール
マルガレートが注ぐ・・・」
Wer niemals Student war, kann die ganze Wonne nicht erfühlen, die im Bier schlummert. Noch heute gelten mir die Tage, da ich als Mulus die ersten Kneipen mit studentischen Komment besuchen durfte, als die lachendsten meines Lebens. Welchen Getränk der Welt würde auch so vortrefflich zur seligen Stimmung brausenden Jugendüberschwanges passen? -- Da sitzen ein paar verdrießliche Gesichter in der dämmerigen Wirtsstude herum. Sie fahren empor, wie die Tür auffliegt und herein mit ihr eine jugendlich lebhafte Schar. Mit lachenden Gesichtern greifen sie zu den Stühlen und gruppieren sich um den alten Eichentisch herum. Die schweren Gläser mit goldgelben Trank und der weißen Schaumhaube schweben empor zu durstigen Kehlen. Schon steigt der erste Kantus:
„Das beste Bier im ganzen Nest,
Das schenkt Margret am Tore ...“(*)
-- Carl Georg von Maassen: Weisheit des Essens. München 1928.
* 市門近く、菩提樹の前、酒場の娘マルガレートに惹かれ夜な夜な通うという歌。
Johann Georg Theodor Grässe: Bierstudien (Dresden 1872) に、この2行から始まる7行3連の詞が «Margreth am Thore» という題で採録されている。
ビール旅行 Bierreisen
宗教改革の嵐が吹き荒れる16世紀ドイツ、神学を学んで聖職者となり、教職につき、宗教劇を執筆し、ラテン語の詩を書いていたのが、さっさと教師を辞めて法学を修め法律家へと転身、職を求めてドイツ各地を転々とするかたわら各所のビールを飲み歩き、飲み比べ、ついにはビールに関する浩瀚な書物まで著した変わり者がいた。ハインリヒ・クナウスト Heinrich Knaust (1521/24-1577) である。一所不住、処世の上で何事にも頓着することなく、信心もフレキシブルであった。宗教改革運動の本丸ヴィッテンベルク大学でルター、メランヒトンに学んだのに、いつの間にかカトリックの修道院で働いているのだから、あっぱれな自由奔放・我流人間というべきか。彼の生涯については確かなデータがなく、伝記事典 ADB また NDB の記述も著書の序文や献辞などに記された本人の陳述によって構成されている。我々も両伝記事典に引用されている記述によって彼の生涯を簡単にスケッチしてみよう。ADB では「法学研究家、世俗歌謡作家、文筆家、多くの土地を転々、多彩な才能の持ち主」と筆を起こし、NDB では「法律家、文学者、翻訳家」と記述を始めている。ある著書の序文にハンブルク生まれと書いているが、生年については触れていない。金細工師であった父から古典語の手ほどきを受け、1536年からヴィッテンベルク大学で学ぶ。1540年にはベルリンのギムナジウムの監理職に就く。
早くも1544年にはそこを辞し、法律家となるべくマールブルク大学のオルデンドルプ教授に師事、そのあとベルリンで弁護士の仕事、さらに北ドイツ、東ドイツを巡歴してさまざまな職に就いた。1557年まではブレーメンに留まって様々な組織で法律顧問のような仕事に従事、1560年ころからリューベックで、そしてコペンハーゲンで、続いてダンチヒ、デミンで同じく法律の仕事に従事。そのあとようやくエアフルトを居所とし、管財人あるいは公証人として活動した。この都市に腰を落ち着けたのは「エアフルトのみならず近辺の村や地区でいいビールを醸造しているから」と述べている。NDB によると、
・・・その地[エアフルト]で聖堂参事会員の地位を得、1560年からは聖マリア修道院神学校の教師になった。この職は彼に個人教師や弁護士の副次的な活動をする多くの時間をもたらしたと思われる。というのも彼の本務である神学校はおそらく彼の任用前に閉校になっていたからだ。閉校になった学校に任用? そんな可笑しなことがあるのだろうか。でも確かに時間に恵まれたようで、旅行と学位取得に精を出し、1565年にマグデブルクの首席司祭から poeta laureatus なる称号を得て、次いでリューベックで博士号を獲得している。
[...] und dort [in Erfurt] eine Stelle als Canonicus, seit 1560 als Scholasticus am kath. Marienstift innehatte. Das Amt scheint ihm viel Zeit für Nebentätigkeiten als Privatlehrer und Advokat gelassen zu haben, denn die Stiftschule, sein eigentlicher Aufgabenbereich, wurde wahrscheinlich schon vor seiner Berufung geschlossen.
-- NDB (NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE) Bd.12, S.167
クナウストの著作は数多いが最も広く読まれたのは『ビール醸造術』 „Kunst Bier zu brawen“ だと言われる。彼の学業・職業上の旅は同時に「ビールの旅」Bierreisen であった。この興味津々の本には(まだ電子化されていないようだ)直接アクセスできなかったのだが、説話・文芸史の研究者で『ゲスタ・ロマノールム』『レゲンダ・アウレア』の独訳者として知られ、ザクセン国王フリードリヒ・アウグスト二世の個人司書も務めたテオドール・グレーセの『ビールの研究』 Bierstudien (1872) にその詳しい紹介がある。『真面目に、また面白く』(*)と副題のあるこの本で、クナウスト本の長い、長い全タイトルも知った。以下のごとし:
哲学的かつ貴く驚嘆すべきビール醸造術の、神々しく高貴なる賜物に関する五つの書。加えて全ドイツに亘る優れたるビールの名称ならびに性質、気質、資質、その種類と特性、健康に良きもの悪しきもの、小麦・大麦ビール、白・赤ビール、薬味の添加・無添加のもの。旧版を様々に増補改修した新訂版。両法学博士ハインリヒ・クナウスト氏著、エアフルトにてゲオルギウス・バウマン印刷。この書はドイツで初めて書かれたビール百科と呼べるようである。クナウストはまず白と赤(茶)に分ける。ビールには透き通った黄色のものから琥珀色、茶色、赤色を経てほとんど黒に近いものまであるので、色で分類するのには困難があるが、白ビールについて彼は Weißbier と Weitzenbier と二通りの書き方をして、どうやら小麦を主原料とするものという意味合いのようだ。従って赤(茶)ビールというのは大麦を主原料とするビールとなる。
Fünff Bücher von der göttlichen vnd edlen Gabe, der philosophischen, hochthewren vnd wunderbaren Kunst, Bier zu brawen. Auch von Namen der vornempsten Biere in gantz Teudschlanden vnd von derer Naturen, Temperamenten, Qualiteten Art vnd Eigenschafft, Gesundheit vnd vngesundheit, Sie sein Weitzen- oder Gersten-, Weisse oder Rotte Biere, Gewürtzet oder vngewürtzet. Auffs newe vbersehen vnd in viel wege vber vörige edition gemehrt vnd gebessert. Durch Herrn Heinrich Knausten, beider Rechten Doctor. Getr. zu Erffurdt durch Georgium Bawman 1575.
ともあれその二通りに分けて各地のビールを評価してゆく。まずヴァイツェンで最高のものとして彼はハンブルクのビールを挙げる。
それは最初甘かった、だが次第にワインのような後味をもつようになった、「ゆえにローマの枢機卿ライムンドゥスも教皇使節としてハンブルクに滞在し、ハンブルクのビールを飲んで冗談めかしてこう言った。o quam libenter esses vinum. この枢機卿の言葉、おお汝はいかにワインたりと欲するか」はハンブルク・ビールに対する永遠の栄誉であり讃辞である。このビールは血色を良くし、肌色を良くするが長持ちはしなかった。クナウストが言うには、このビールで体を洗うと肌色が良くなるだけでなく、すっきりと清潔で純粋な皮膚をもたらす。しかし飲みすぎると化膿し爛れ、顔は赤く腫れぼったくなる。続けてリューベック、ダンチヒ、コペンハーゲン、ブレーメンのビールを順次取り上げてゆき、ハンブルクから5マイルに位置するシュターデ Stade のヴァイツェン(白)ビールについては、
Es war anfangs süß, allein allmälig gewann es einen weinlichen Nachgeschmack, „weshalb auch der Cardinal Raimundus von Rom, wie er zu Hamburg als ein päpstliche Leget gewesen und Hamburger Bier getrunken scherzlich gesprochen: o quam libenter esses vinum. Dies Wort des Cardinals ist eine ewige Ehre und Lob derm Hamburger Bier: o wie gern wollest Du Wein sein!“ Dieses Bier machte gutes Blut und eine schöne Farbe, aber es hielt sich nicht lange. Knaust sagt, wenn man sich damit gewaschen, mache es nicht blos eine gute natürliche Farbe, sondern auch eine gelinde, saubere und reine Haut am Leibe. Wenn man aber zuviel davon trinke, mache es Schwäre und Beulen und das Gesicht werde roht und aufgedunsen.
・・・使っているのはまったく同じエルベの水、同じ小麦とホップなどなど。シュターデの市民は外部から、とくにハンブルクからはビールを入れさせないと威張っているが、クナウストが請けあって言うには、ハンブルクのビールの方がまず体に良い、そしてこれを飲んだ者が翌朝に頭痛になることはない。シュターデのビールはそこの人たち自らが「猫」Kater と呼んでいたように、飲みすぎると頭を掻きむしることになる、とのこと。ドイツ語で二日酔いのことを Katzenjammer とか Kater とか「ネコ」で表現する(**)。なぜ猫なのかと不思議に思っていたが頭痛で「頭を掻く」からだったのか!? このようにクナウストはビールの性状、味覚だけでなく、名称についても面白く解説して、読者サーヴィスを忘れないのである。
[...] genau aus demselben Elbwasser, demselben Weizen, Hopfen u.s.w. Zwar hielten es die Bürger von Stade so hoch, daß sie kein anderes Bier, namentlich kein Hamburger ihn ihre Stadt zuließen, allein Knaust versichert doch, letzteres sei erstlich gesünder, dann aber steige es dem, der es getrunken, nicht am andern Morgen nach dem Kopfe. Dies that nämlich das Stader Bier, welche man dort selbst Kater nannte, weil es den Menschen, der davon zu viel getrunken, im Kopfe kratze.
-- Johann Georg Theodor Grässe: Bierstudien -- Ernst und Scherz (Dresden 1872)
* 前川道介『愉しいビーダーマイヤー』(国書刊行会 1993) で「さすがにこの年代のドイツ文化の厚みを感じさせてくれる好著」と紹介されている。
** ドイツの辞書・事典類を検索すると Katzenjammer なる言い回しは18世紀後半から学生の間で広まったらしい。Grimm 辞典では1809年の出典をあげている。また Kater は「カタル Katarrh」と掛けた19世紀の学生言葉から生まれたとされている。
ヒルデガルトの自然学 Physica
テオドール・グレーセの『ビールの研究』にはヒルデガルト・フォン・ビンゲンが登場してくる。幻視者とも巫女とも呼ばれるこの神秘的な修道女とビールの取り合わせは一見奇妙に思われるかもしれないが、中世の修道院ではワインでなければビールが醸造されていたし、それに庭園ではさまざまな草木を栽培して薬草研究の拠点にもなっていたのだ。ヒルデガルトは薬草に留まらず、自然界の植物、動物、鉱物すべてに関する博物学的な知識の持ち主であって、全9巻に及ぶ『素朴療法の書あるいは自然学』 Liber simplicis medicinae oder Physica (1151–1158) を著している。この聖女ヒルデガルトこそがビールのスパイスとしてのホップについて書き残した最初の人だと、グレーセは記している。
ビールに不可欠な添加物としてこの植物 (humela) は、ルーペルツベルゲの女子修道院長として1079年[正しくは1179年(引用者)]に亡くなった聖ヒルデガルトの書で初めて現れた。彼女はホップについて、人を悲しくさせ内臓を乾燥させるが、しかしその苦味によってこれを添加した飲み物を長持ちさせる効果があると語っている。その時から一般にホップビールが醸造されることになったと思われる。なぜならホップを混ぜることでビールを長持ちさせられると考えたからだ。引用箇所の注でグレーセは『自然学』を典拠として示している。このラテン語著書の英訳を入手したので、まず索引を見てみると、ホップは2回出現する。「ホップ」自体を取り上げた項目と、「トネリコ」の項目とで言及されている。「ホップ」の項目を開くと、
Als nothwendige Zuthat zum Bier kommt diese Pflanze (humela) erst in einer Schrift der H. Hildegardis, welche 1079 [sic] als Aebtissin auf dem Rupertsberge starb, vor. Sie schreibt von ihm, er mache die Menschen traurig und trockne seine Eingeweide aus, allein durch seine Bitterkeit bewirke er, daß die Getränke, denen man ihn zusetze, sich lange hielten. Von da ab scheint man allgemein Hopfenbier gebaraut zu haben, weil man meinte, durch die Beimischung des Hopfens halte sich dasselbe länger.
-- Johann Georg Theodor Grässe: Bierstudien (Dresden 1872)
ホップは温と乾の薬草で、少し水分がある。人に使うのにはあまり適していない、なぜならメランコリーを増大させ悲しい気分にさせ、そして腸を重くさせるからである。とはいえその苦味はこれを加えた飲みものの損傷を抑制し、長持ちさせる。ホップの解説はこれだけ、見ての通り薬草としての効用と「飲みものを長持ちさせる」働きを説明しているだけである。はっきりビールという名称が出るのは「トネリコの木」の項目で、ここではホップを用いないビールについて触れていて、この記述によってホップを用いてビールを醸造するのが一般であったことがわかる。
Hops (hoppho) is a hot and dry herb, with a bit of moisture. It is not much use for a human being, since it causes his melancholy to increase, gives him a sad mind, and makes his intestines heavy. Nevertheless, its bitterness inhibits some spoilage in beverages to which it is added, making them last longer.
[前略]オーツ麦でビールを造るときは、ホップを用いないで挽き割りだけで造ってトネリコの葉をたくさん加えなさい。このビールを飲むと胃を清浄にし胸部を晴れやかに快適にするだろう。[後略]ちなみに、こういう症状の時にはこの薬草を入れたビールを飲むのがよい、あるいは飲んではいけないなどなど、ビールは9箇所で取り上げられている。
[...] If you want to prepare beer from oats, without hops, cook it only with groats, with many ash leaves added. This beer, when drunk, will purge the stomach and make the chest light and pleasant. [...]
-- Hildegard Von Bingen's Physica: The Complete English Translation of Her Classic Work on Health and Healing, Translated from the Latin by Priscilla Throop (1998)
「温と乾のハーブ」とか「メランコリー」という表現からヒポクラテス、ガレノスを祖とする古代医学の伝統の中に、ヒルデガルトもあることが分かる。ヒポクラテスの四体液説によると、人体は血液、粘液、黒胆汁、黄胆汁から成り、血液が多い人は楽天的、粘液が多いと鈍重、黒胆汁が多いと憂鬱、黄胆汁が多いと気むずかくなるとされる。またガレノスは温・冷・乾・湿のバランスが身体の機能を決定するという伝統的な教義と四体液の説を継承発展させ、中世医学思想の流れを定めたとされる。
ヒルデガルトはこのギリシャ・ラテンの医学思想とキリスト教の世界像を融合させている。旧約聖書『創世記』の天地創造こそ『自然学』の枠組みであり、神に与えられた鉱物、植物を治療に用い、動物の振舞いを健康法の手本にしようとした。ヒルデガルトの生涯と思想世界について我々はつとに種村季弘による優れた評論をもっているが、その中で種村は、彼女の医学思想におけるキリスト教の意味を次のように言う。
ヒルデガルトの医学は彼女独特の救済史観と緊密に対応している。すべての被造物は、神の創造したもうた天地創造の七日間の初源においては健康にして完全であった。人間の肉体も創造の時の素質 (constitutio) にあっては病や欠如を知らない。けれども最初の人間アダムが悪魔のささやきに誘われて堕落した瞬間に、アダムの肉体に病が生じた。病から健康=原初の素質に立ち戻るためにはしかし、神があらかじめ地上の被造物のなかにひそかに用意してあった「隠された諸性質」を発見し、これを治療手段としつつ楽園の原素質に帰還するのでなくてはならない。自然学はまさにこの楽園回帰=健康回復への手段として、肉体の治療とたましいの救済を同時に解決すべき知識なのである。『自然学』は植物・元素(空気、水(*)、土)・宝石・魚類・鳥類・獣類・爬虫類など500以上の項目を取り上げて薬効・毒性と利用法を説いている。彼女のもう一つの著作『病因と治療』 (Liber compositae medicinae oder Causae et curae) と併せて、中世医学、自然学の古典に数えられるが、ヒルデガルトの療法は現在のホメオパシー(類似療法)の元祖だとする見方もある。
-- 種村季弘『ビンゲンのヒルデガルトの世界』(青土社 1994)
幻視家ヒルデガルトには天上の光り輝くヴィジョンが視えただけでなく、宇宙の諧音も聞こえたようだ。降り注ぐメロディーを受け止めて彼女は70曲を超える典礼聖歌を作曲している。それは自然の四大元素を組み合わせる壮麗な響きであった。彼女の聴いた「天上の声」を、我々はいまCD(**)で遥かに追体験することができる?
* 元素「水」のなかにライン河、マイン河、ドナウ河などドイツの河川が取り上げられ、飲用あるいは調理用の水としての性質、そしてそこに棲む魚の特徴を論述している。「魚類」で取り上げられる数多くの魚もこうした河川に生息するものが多い。
** deutsche harmonia mundi レーベルの "canticles of ecstasy" や "voice of the blood" など数枚のCDが出ている。
薄口ビール Covent
先にマックス・バウアー『ドイツ大学生の風俗史』から「ブルゼ Burse 」と呼ばれる中世の学寮を取り上げて「中世の学寮の食事」を話題にした折、ライプチヒの「ハインリヒ学寮」で供せられる貧しい食事について、次の風刺文を引用した。我々の学寮では毎日二度、昼と夜、七品の結構な食事が供される。一品目は「常々」といいドイツ語では粥である。二品目は「恒常」といってスープ。三品目は「連日」といって野菜である。四品目は「頻繁」という少量肉、五品目は「異例」というロースト肉、六品目は「皆無」というチーズ、七品目は「後日」でリンゴとナシ。加えて結構な飲み物はコヴェントという名の薄口ビール。ご覧あれ、立派なものではないか。最後の、「コヴェントという名の結構な薄口ビール」と訳したところ、原文を直訳すると「コヴェントと称する良き飲み物」である。コヴェントとは何か? 中世から近世にかけては一度醸造で搾った麦芽を使って再度ビールを造るのが普通であった。要するに出がらしのビールだが、この名称は「コンヴェントビール」 Konventbier、すなわち修道院で院長らの飲む「一番搾りビール」ではない、平の修道士の飲む薄い搾りかすビールから生まれたらしい。わが国では「淡口」と表記されるゆかしい「うすくち醤油」なるものがあるが、コヴェントは有体に「薄口ビール」と呼ぶほかあるまい。
Wir haben auch gut zu essen in unserer Burs und zweimal täglich sieben Gerichte, Mittags und Abends. Das erste heißt Semper, auf deutsch Grütze. Das zweite Continue, eine Suppe. Das dritte Quotidie das heißt Gemüse, das vierte Frequenter, Magerfleisch; das fünfte Raro Gebratenes; das sechste Nunquam Käse, das siebente Aliquando Äpfel und Birnen. Und dazu haben wir einen guten Trunk, der Covent heißt. Seht da, ist das nicht genug?
身分の低い修道士に供せられ、また貧者や巡礼者に振舞われる飲料であったコヴェントは、まさに往時の学生寮で提供するに似合わしい「良き飲み物」であった。しかし必ずしも二番煎じの薄いビールだけが学寮の飲み物では無かったようだ。
またコヴェントがあまねく所でこれしかない飲み物という訳ではなかったようだ。いずれにせよ学寮ではいずこもビール止まり、ワインが出されることは無かった。もともとビールは「液体のパン」 flüssiges Brot と呼ばれていたように、嗜好品というより栄養を補う飲料であった。何せドイツでは昔から大人も子供も朝食に「ビール・スープ」 Biersuppe というものを食べていた。それは小麦粉あるいは古くなったパンをビールで煮たもの(裕福な家庭では卵を加え、バターや塩、砂糖で味を調えることもある)で、これには「薄口ビール」が用いられていた。かのフリードリヒ大王が「余も幼時ビール・スープで育てられたのじゃ」と言ったのは有名な逸話だが、19世紀まで粗末な家庭料理のひとつであった。現在では昔を懐かしむ(?)レセプトとして残っている。
Auch das Covent scheint nicht überall das ausschließliche Getränk gewesen zu sein. Immerhin wurde in allen Alumnaten nur Bier, niemals Wein gereicht.
-- Max Bauer: Sittengeschichte des deutschen Studententums. (1991)
ビールがアルコール飲料というより栄養補給の食品であった歴史は長い。また次の例を見れば「薄口ビール」が学生寮で標準的な飲み物であったのはドイツに限らないのかもしれない。
二十世紀前半の欧米社会では、ワーキング・クラスの男性が労働のために朝からアルコールを手にすることは見慣れた光景だった。イギリスの伝統あるパブリック・スクールのイートン校でさえ、生徒用の朝食にビールが出された。ここでは、チョコレートやココア以前の手軽なエネルギー源という脈絡でビールが話題に上がっているのだが、イートン校のビールが「薄口」だったのか、あるいは真っ当な伝統的エールだったのか、興味あるところだ。
-- 武田尚子『チョコレートの世界史』(中公新書 2010)
公子ホンブルク Prinz von Homburg
最近、ドイツ・ビールの沿革を軸にストーリーが展開する《歴史小説》が出た。ギュンター・テメスという作者の『ビール魔術師』シリーズで、3巻まで出版されている。物語は13世紀のビール醸造を巡る出来事から始まるようだ。魔術師とは、醸造人としての腕の良さを褒める渾名だろうが、あるいはキリスト教会側からの非難の言葉かも知れない。前の2冊を読んでいないので確かなことは言えない。取り寄せて読んだのはシリーズの第3巻『ビール魔術師の罵り』だ。第3巻では時代は「三十年戦争」など戦乱の続く17世紀に進んでいる。酸鼻を極めた「マグデブルク大殺戮」に遭遇、家を失い妻を失ったビール醸造人コルト・ハインリヒ・クノルの物語で、小説の後半では「大戦争」が終わったあとの、彼の息子ウルリッヒを中心にして物語が繰り広げられる。ウルリッヒは各地を遍歴修業したあとヴェーファーリンゲンで醸造人となっていて、やがて父親も合流するが、この地の新しい領主となったのが公子ホンブルクであった。
史実とフィクションを織り交ぜた作品ということになろう。ヘッセン公子フリードリヒ・フォン・ホンブルクの生まれからヘッセン公国のお家の事情、フリードリヒの「騎士旅行」、帰国後に結社「結実協会」に加入、彼の結社員名が「頑固者 Klebrichte 」であったこと、21歳でスウェーデンでの軍務につき、北方戦争におけるデンマーク攻撃戦で右脚を負傷、切断(*)したこと。30歳年長の富裕な未亡人との結婚、スウェーデン軍元帥の地位にあったケーニヒスマルクからの領地購入など、「史実」が大変詳しく書き込まれている。
公子が購入した領地の一つがヴェーファーリンゲンだった。この土地の獲得を決意したのは、物語では、同地に優れたビール醸造所があったからとされる。
そしてブランデンブルク選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルム1世は1662年1月11日、31350ターラーという額の抵当貸付金の受納と引き換えに、ケーニヒスマルクの担保が解除され、ヴェーファーリンゲン統治権のヘッセン公子フリードリヒ・フォン・ホンブルクへの移譲を認可した。小説では公子の後援を得つつ、「ビール魔術師」の意気込みと努力が実って、ウルリッヒの醸造所は隆盛に向かう。装置の改良、原料の吟味、品質向上・増産に取り組んで成果をあげてゆくのだが、そこにまた戦争が勃発する。この度はブランデンブルク・プロイセンとスウェーデンの間で。この局面で物語後半のクライマックスが訪れる。
[中略]隻脚の公子は29歳、かくてひとつの醸造所の、公子の名を歴史に残すこととなる醸造所の、オーナーとなった。
Und so genehmigte der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm I. am 11. Januar 1662, gegen Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von einunddreißigtausenddreihundertundfünfzig Talern, mit dem der Pfandbesitz Königsmarcks ausgelöst wurde, den Übergang des Amtes Weferlingen in den Privatbesitz des hessischen Prinzen Fridrich von Homburg.
[...] Der einbeinige Prinz war neunundzwanzig Jahre alt und nun Besitzer einer Brauerei. Einer Brauerei, mit der er in die Geschichte eingehen sollte.
ヘッセン公子ホンブルクといえば、ドイツ文学の愛好者・研究者にはすぐさま、ハインリヒ・フォン・クライスト最後の戯曲『ホンブルクの公子フリードリヒ』(成立 1809–1811、初演 1821)が想起されるだろう。この作品はブランデンブルク・プロイセンとスウェーデンの交戦、とくに「フェールベリンの戦い」を背景にしてドラマが展開する。
1675年6月28日(**)の「フェールベリンの戦い」は、いわゆる「北方戦争」(1674-1679) と呼ばれる戦役の一こまである。領内に侵入してきたスウェーデン軍に対して、選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムの軍隊はベルリン北西60キロのフェールベリンで布陣し、偵察の任を与えられたホンブルク公子が命令を待たずに攻撃をしかけ、敵軍を敗走させた。このあとスウェーデン軍をドイツ領内から駆逐して、プロイセンがヨーロッパ列強の一角を占める契機になったこれは歴史的勝利だと称揚され、フリードリヒ・ヴィルヘルムは「大選帝侯」と呼ばれ、ナショナリズムが高揚した19世紀から20世紀にかけてのドイツでは、この日が祝日に定められるに至った。
クライストのドラマでは公子ホンブルクが敵軍偵察の命令に違反して戦闘を始め、戦いには勝利したが軍令違反を咎められる。「法に照らして厳格に対処するなら死罪に値する」ところを選帝侯の雅量により許される、という筋書きになっている。
ところが、選帝侯と公子は戦場の作戦行為ではなく別の理由で激しく対立していた、というのがギュンター・テメスの「歴史小説」の設定である。対スウェーデン戦争の軍費を調達するため選帝侯が導入したのがオランダの先例に倣った「アクチーゼ Akzise 」と呼ばれる消費税である。課税対象となった品目はライ麦、小麦、ホップなどの穀物ならびに製粉したもの、砂糖、塩、油、肉、タバコ、コーヒー、紅茶、ビール、シャンパン、家畜などであった。何かと金を出し渋っていた諸侯もこの税を承認する。この消費税、特にビール税が『ビール魔術師の罵り』では両者の争いの原因になっている。
公子は、自分は帝国騎士でヴェーファーリンゲンはその領地だから納税の義務はない、と主張して課税に応じない。ブランデンブルク軍はテュレンヌ率いるフランス軍に翻弄され、フランス王ルイ14世と結んだスウェーデンが侵入してくるという情勢下、
宮廷に戻った選帝侯は家臣を前に大声でヘッセン公子を非難した。「フランス奴は余を侮辱する、スウェーデン奴は腹に据えかねる、それにこの痛風があってまだ足りないとでも言うのか、あのヘッセン公子はビール税のことにとやかく言いおる。」選帝侯と公子ホンブルクがビール税を巡って対立していたという説は、実は法律家で歴史家・作家のヘルベルト・ローゼンドルファーに拠っている。数多い著作の一つに『公子ホンブルクあるいは銀脚の方伯』(ミュンヘン、1978)があるのでそこで詳述されていると思われるが、『ドイツの歴史』(ミュンヘン、1998~2010)【この著作はオーディオブックになっている】第7巻の「フェールベリンの戦い」を扱った部分で、命令に違反した公子とそれを許す選帝侯、という伝説が歴史的事実と受け取られるようになり、プロイセンの「国粋的なトポス」となっていった経緯を語っている。
Zurück am Hof lästerte der Kurfürst lautstark und öffentlich über den Hessenprinzen: »Als ob mir der Franzose nicht schon genug auf die Füße tritt, der Schwede mir Ärger bereitet und mich dazu die Gicht plagt, kommt jetzt auch noch dieser Hessenprinz und beschwert sich über unsere Bierakzise.«
-- Günther Thömmes: Der Fluch des Bierzauberers - Historischer Roman (2010)
そのイメージの極北にあるのが画家クレッチマー Carl Kretschmar の『フェールベリンの戦場でホンブルク公子を許す大選帝侯』(1800年)だろう。43歳の義足の公子と55歳で担架に載って行軍していた痛風病みの選帝侯が、画面では健全な両脚を備えた若い貴公子と威厳を持って悠然と構える君主として描かれている。クレッチマーはベルリン芸術アカデミーに出展する常連であったが、この作でアカデミーの大賞を与えられた。
こうして美化された伝説がクライストのドラマの機軸となったのだが、実際は、フェールベリンは公子ホンブルクの領地に近く、彼は狩猟で何度もこの地を訪れ、地勢を知悉していた。
歴史上のホンブルクは、すでに触れたように、ついに勝敗を左右する高地を占拠したとき、それは決して命令に背いてではなく単に命令を受けずして行動に出たのである。加えて彼は自己の行為をしっかりと承認させた。その際、たまたまその場所を良く知っていて土地勘があったことが勝利に導いたことは明らかだ。彼に対する軍事裁判などは存在しなかった。選帝侯とのいさかいはおそらくビール税のためであった。ドイツ・ビールを巡る《歴史小説》を書くなら、誰しもこの「史実」は恰好のネタとして取り上げるだろう。ギュンター・テメスは『ビール魔術師の罵り』巻末の注記で、公子と選帝侯の不和の原因について従来の誤りを正したと、ローゼンドルファーへの賛辞を記している。
Der historische Homburg hat, wie schon erwähnt, keineswegs gegen einen Befehl, nur ohne Befehl gehandelt, als er die schließlich die Schlacht entscheidende Höhe besetzte. Außerdem ließ er sein Handeln ganz korrekt sanktionieren. Daß seine Entscheidung, verbunden mit seiner zufälligen, sehr guten Terrainkentnisse, den Sieg dabei geführt hatte, ist klar. Ein Kriegsgericht-Verfahren gegen ihn gab es nicht. Ein Zerwürfnis mit dem Kurfürsten wohl wegen der Bierakzise.(***)
-- Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Ein Versuch (Hörbücher Vol.7), München 2008
* ヴェーファーリンゲンのHP flecken-weferlingen では、失くしたのは左脚となっている。
** グレゴリオ暦による。ユリウス暦では6月18日、それゆえ第二次大戦まで祝日となっていた戦勝記念日は18日だった。
*** 引用は聞き取った音声の書き起こしなのでオリジナルの表記とは異なっているかもしれません。

