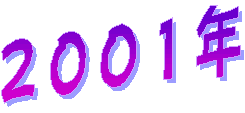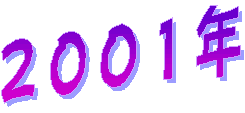|
当日のプログラムに、落語でおなじみの桂南光さんが書いている文章によると、「佐渡さんは今はやりの陰陽師、会場の1万人の皆様、今日も彼の術にかかって、存分にたのしんでください。」とある。
バリトンの独唱者が「フロイデ」と歌いだすのに応ずる形で、バスの合唱が「フロイデ」と答える。ここで佐渡さんは、この「フロイデ」にスピード感がほしい、といわれる。指揮棒の動きより一瞬早くFの音が出てこないといけない、「FろイDE」!!という感じ。「うれしい」とか、「やったア」という、いや、もっと激しい感情の爆発をここで見せたいのだ、と。9月のはじめから3カ月の間、週1回の練習を積み重ねてきた、その成果をこの一瞬に示さなければ、今までの努力は水の泡だ、という思いは合唱団全員の思いでもある
|
1楽章、2楽章、3楽章と演奏は進んで、いよいよ4楽章、われわれの出番となった。バリトン独唱の「フロイデ」が終わった瞬間、「FろイDE」!!!という自分たち男声陣の声が聞こえたとき、「あツ、やった」と思ったのである。後は一気呵成、まさに音の奔流である。 |
| 魔術師 指揮者佐渡 裕は正に魔術師。指揮棒は魔法の杖。オーケストラも4人の独唱者も、そして我々合唱団も、ひたすら指揮棒の動くままに、時には劇しく又時には祈りを籠めた静けさで演奏を繰り広げていったのである |
 |
| べートーヴェンは、耳が聞こえなくなるという、音楽家として致命的な疾患に苦しみながらも、幾多の名曲を残している。この交響曲第9番「合唱」の各楽章は彼のそれまでの生涯を振り返ったものとなっているそうだが、苦しみが大きければ大きいほど、それに打ち勝ったときの「歓喜」がどれほどのものになるか、充分に想像できる。その「歓喜」がこの最終楽章で爆発しているのだ。我々素人合唱団も燃えた。歌うほどにその感激は益々高まっていったのである |
| 「フロイデ」で始まった合唱は「フロイデ シェーネル ゲッテルフンケン」(歓喜、美しき神々の火花よ)という言葉で終わるのだが、最強音(ff)で「ゲーッテルフンケン」!と歌い終わったあと、佐渡さんが静かに指揮棒をおろした時、一瞬の間をおいて客席からの拍手と同時に、我々合唱団員全員も思わず一斉に拍手をしていた。果たして奇跡の瞬間が起こっていたかどうかは佐渡さんに聞いてみないと分からないが、少なくとも私自身のなかでは「やった!やった!」という気持ちから自然に拍手が出ていた。おそらく全員の気持ちもそうだったのではないか。 |
| 今年の参加者の中には7歳の少女から、89歳の高齢者までがいると聞いたが、あるいは19回全部に参加している人もいるほどに、この第9のコンサートは、歌うほどに魅力が増してやめられなくなるらしい。私自身も、来年も「絶対に参加するぞ」と鬼に笑われるのを覚悟で決心しているのである。 |
|
|