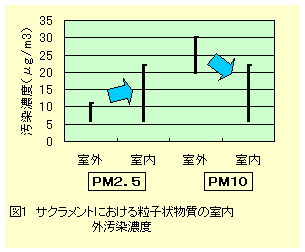
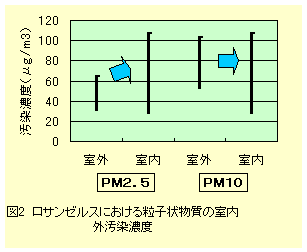
カリフォルニア州における自動車室内汚染濃度の測定結果
1999年12月17日
CSN #114
自動車からの排出ガスは、大気汚染の主な原因として、古くから改善すべき問題とされてきました。これまでにも様々な改善が行われてきましたが、交通量の増加が重なって、いまだに大気汚染の主な原因となっています。一般に自動車の排出ガスによる環境汚染問題は、室外大気中において評価されてきました。しかしながら、アメリカ、ドイツ、韓国などから自動車室内の空気質にも影響を与えていることが報告されています[1]。
これらの報告では、ベンゼン、エチルベンゼン、トルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物についての調査結果が報告されました。そして、これらの化学物質の空気汚染濃度は、自動車室外よりも室内の方が高いことが示されました。しかしながら、自動車の排出ガスや企業活動に伴う工場からの排出ガスなどによる日本の大気汚染は、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)などが大きな問題となっており、その中でも二酸化窒素と浮遊粒子状物質(SPM)における環境基準達成率が低い傾向が続いています[2]。
また環境庁は、1997年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、1997年度から地方公共団体(都道府県、大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリング調査を開始し、大気汚染防止法に基づいて指定物質に指定されている、ダイオキシン類、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについてモニタリング調査を行っています[2]。
浮遊粒子状物物質(SPM)は、大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm(百万分の1メートル、または千分の1ミリ)以下の物質で、微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着し、高濃度の場合は呼吸器に悪影響を及ぼします。日本ではオイルショック以降、ディーゼル車の普及が進んでおり、浮遊粒子状物質のうち、ディーゼル排気微粒子(DEP)は、発がん性や気管支ぜんそく、花粉症等の健康影響との関連が疑われています。特に粒子径が2.5μm以下の粒子状物質は、PM2.5と呼ばれています。PM2.5は超微粒子なので、肺の奥深くまで入り込み、肺の奥に付着しやすいので健康影響が大きいと考えられています[2]。
このように大気中では、ベンゼン、エチルベンゼン、トルエン、キシレン以外にも浮遊粒子状物質(SPM)などが問題視されており、これらの化学物質が自動車室内の空気汚染を引き起こす可能性が考えられます。
1999年6月10日にカリフォルニア州環境保護庁 大気資源委員会が、カリフォルニア州を走る自動車室内の空気汚染状況を測定した結果を発表しました[3]。
この研究は、米カリフォルニア州のサクラメントとロサンゼルスにおける自動車通勤圏内の地域において実際に走行し、様々な環境条件下における自動車室内の汚染物質濃度を評価するために行われました。
1997年9月と10月に、サクラメントへの通勤経路とロサンゼルスへの通勤経路を、それぞれ様々な環境条件下で走行し、自動車室内の汚染物質と室外大気の汚染物質が2時間収集して測定されました。測定結果の平均値を表1に示します。
表1 サクラメントとロサンゼルスにおける自動車室内外の空気汚染濃度の平均値([3]をもとに作成)
|
汚染化学物質 |
単位 |
サクラメント |
ロサンゼルス |
||
|
室内 |
室外 |
室内 |
室外 |
||
|
MTBE |
μg/m3 |
3- 6 |
2- 7 |
20- 90 |
10- 26 |
|
ベンゼン |
3- 15 |
1- 3 |
10- 22 |
3- 7 |
|
|
トルエン |
7- 46 |
4- 8 |
22- 54 |
10- 40 |
|
|
PM2.5 |
6- 22 |
6- 11 |
29- 107 |
32- 64 |
|
|
PM10(SPM) |
6- 22 |
20- 30 |
29- 107 |
54- 103 |
|
|
ホルムアルデヒド |
5- 14 |
2- 4 |
検出限界- 22 |
7- 19 |
|
|
一酸化炭素 |
ppm |
検出限界- 3 |
検出限界以下 |
3- 6 |
検出限界以下 |
表1から明らかなように、MTBE、ベンゼン、トルエン、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOCs)は、全体的に室外よりも室内の方が、空気汚染濃度が高くなっています。また図1、図2に示すようにPM2.5とPM10を詳細に見ますと、図2のロサンゼルスでは、PM10(粒子径が10μm以下)において室外と室内の空気汚染濃度に大きな変化がなく、図1のサクラメントでは、むしろ室内の方が減少している傾向が見られます。しかしながらPM2.5(粒子径が2.5μm以下)では、室外よりも室内の方が、空気汚染濃度が高くなっています。
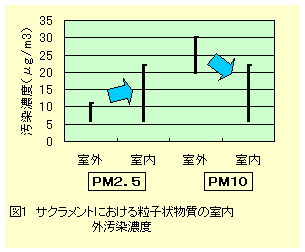 |
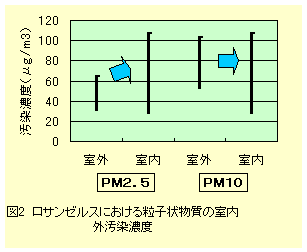 |
*[3]をもとに作成
自動車には換気装置が設置されており、室外空気を室内に取り込む時は、この換気装置を通じて室外空気が取り込まれます。つまり図1と図2の結果は、自動車の換気装置によって、直径2.5μ以下の超微粒子があまり除去されていないことを示しています。また、表1中のMTBE、ベンゼン、トルエン、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物も、室外より室内の空気汚染濃度の方が高くなっており、自動車の換気装置では十分に除去されていないことが示唆されています。
自動車室内は、窓を開けていなければほとんど密室空間ですので、取り込まれた汚染物質は、なかなか室外に排出されずに室内にとどまります。そのため、室内の空気汚染濃度が高くなります。次に表2では、様々な環境下での室内汚染濃度の状況について示します。
表2 環境条件と室内汚染濃度([3]をもとに作成)
|
条件 |
環境条件 |
室内汚染濃度の状況 |
|
一般 |
渋滞時と閑散時の高速道路 |
渋滞時>閑散時 |
|
地域差 |
都市郊外地域へ行くほど、汚染濃度が低かった |
|
|
自動車の種類(セダンが2種類、スポーツ車、カリフォルニア・スクールバス) |
ほとんど無関係 |
|
|
特殊 |
通学経路を走るカリフォルニア・スクールバス(サクラメント) |
住宅街を走るので、室内汚染濃度は低かった。 |
|
カープール・レーンと渋滞中の右側車線の比較(ロサンゼルス) |
カープール・レーン<渋滞中の右側車線(約1.6倍) | |
|
排気ガスが極端に多いディーゼル自動車や、ディーゼルエンジンで走る市バスの後ろを走行 |
微粒子濃度が(約1.3- 1.5倍) |
*カープール・レーンは日本にはないシステムで、渋滞解消とエネルギー節約のため、1台に2人(場所によっては3人)以上乗っている車を優先する制度です。
表2の結果から明らかなように、渋滞時など交通量が多い場合は室内汚染濃度が高く、閑散時や住宅街など交通量が少ない場合は、室内空気汚染濃度が低くなることが示されています。また特に、ディーゼル排気微粒子(DEP)を排出するディーゼル自動車の後を走行すると、微粒子濃度が高くなることが示されています。つまり、前方や周囲の室外空気の汚染状況と密接に関連していると言えます。
この報告のような研究は、気象条件や前を走行する自動車の排出ガス汚染度の違いなど、様々な外乱の影響を受けます。そのためさらに、追試による確認が必要です。また、この報告で実現されなかった二酸化窒素(NO2)や多環芳香族炭化水素(PAHs)の短期サンプリング手法を開発し、さらに広範囲に室内汚染物質の挙動について研究する必要があると思われます。
ただ最も本質的なことは、自動車室内の空気汚染は、周囲を走る自動車の排出ガスの影響を大きく受けているということです。さらに大きく言えば、自動車の排出ガスは大気汚染を引き起こし、住宅室内や自動車室内など、私たちの生活に関わる様々な空間を汚染しています。自動車からの排出ガス削減は、私たちの生活空間から有害化学物質をできるだけ排除するために、環境問題における最も重要な課題の1つです。
Author:東 賢一
<参考文献>
[1] 東 賢一, 「自動車室内の揮発性有機化合物(VOCs)濃度」CSN #099, Sep 29. 1999
http://www.kcn.ne.jp/~azuma/news/Sept1999/990929.html
[2] 平成11年版 環境白書
http://www.eic.or.jp/eanet/hakusyo/1999/mokuji.htm
[3] Charles Rodes, Linda Sheldon and others, California Environmental Protection Agency Air Resources Board, June 10, 1999.
http://www.arb.ca.gov/research/indoor/in-vehsm.htm
" MEASURING CONCENTRATIONS OF SELECTED AIR
POLLUTANTS INSIDE CALIFORNIA VEHICLES "