「男女雇用機会均等法」成立から40年、「機会の均等」から「結果の均等」へ -「男女を問わず」から「男女別」へと逆行する病める日本の社会をリードする関西学院大教授大内章子さん-
3月8日の読売新聞は、「[エール 均等法40年 国際女性デー2025]<5>「第一世代」その後 追跡調査 関西学院大教授 大内章子さん 59」と言う見出しで、次の様に報じていました。(茶色字は記事 黒字は安藤の意見)
------------------------------------------------------------------------------------
[エール 均等法40年 国際女性デー2025]<5>「第一世代」その後 追跡調査 関西学院大教授 大内章子さん 59
2025/03/08 05:00 読売
I143-2
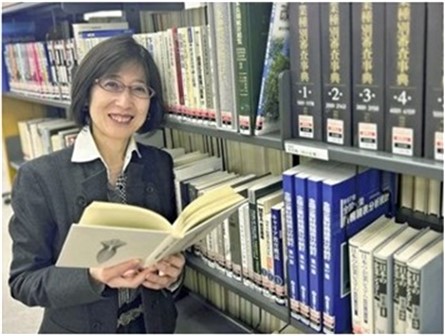
「企業は女性社員にチャンスを与え、スキルや自信を身に付けさせることが
肝要」と大内さん(大阪市の関西学院大大阪梅田キャンパスで)
(写真は省略)
入社間もない頃の大内さん=本人提供
朝8時30分頃に出社し、荷物を自分のロッカーに入れると、課内の同僚10人の机を布巾で拭く。「テレックス」を整理して配布。給湯室へ向かい、急須に茶葉と湯を入れて、課員それぞれの湯のみにお茶をそそぐ。9時15分、始業にあわせて、出社した課員にあいさつしながらお茶を出す――。
男女雇用機会均等法が成立した4年後の1989年。総合職として入社した大手総合商社での朝の務めだ。当時、一般職を含め、女性社員に当番制で割り振られていた。「湯のみには名前が書かれていなくて……。どの湯のみが誰のものか、それを覚えるのが最初の仕事の一つでしたね」。ほかにも、コピー取りや昼食時の電話番など、女性だけに課せられる任務は多かった。
記事は「男女雇用機会均等法」をこの女性問題(男女の問題)の原点として捉えています。ちなみに1989年は、少子化問題の原点である1.57ショックが発現した年でもあります。
〈総合職ゆえ、周囲の男性と同様の働きも求められた。長時間労働は当たり前だった〉
同じ総合職であれば、同様の働きを求められるのは当然の事と思いますが、何か異議があるのでしょうか。
雇用機会均等とは、男女に労働者として均等の雇用機会を与えると言うことであり、言うまでもなく男女同一の労働条件(長時間労働を含む)が前提となります。また、お茶くみが一般職の業務とされ、総合職の業務範囲でないのであれば、男女を問わず割り振られるべきではありません。
配属された経理部は、特に株主総会前、多忙を極めた。夕方5時30分の定時の終業時刻が過ぎ、しばらくすると社員食堂で「ざんめし」(「 残業飯ざんぎょうめし 」の略)を食べ、帰宅するのは深夜。3週間休みがないこともあった。入社後1年弱で7キロやせ、生理は止まった。体力が追いつかず、いつまでこの生活を続けられるのか不安を抱き、そのうち疑問がわいた。
「総合職の女性が増えたら、誰が家事や育児をするのだろう。均等法で入り口を整えるだけでは、女性が働き続けることはできないのではないか」
当たり前の事ですが、男女の雇用の機会が均等だからと言って、雇用の選考はくじ引きではないのですから、選考の結果が男女均等になるとは限りません。職種によっては当然男女の能力に差があるし、個人差もあります。
その中で家庭内で誰(夫婦のどちら)が家事・育児をするかなどは、およそ夫婦間の問題であって、夫婦のどちらかが退職するか、あるいは一般職に変更するか、それとも家政婦を雇うのか等は、自分たちで決められるべき問題であって、「雇用機会均等法」云々の問題ではありません。
「均等法で入り口を整えるだけでは・・・」と言いますが、そもそも雇用機会均等法は“入り口”の法律であり、出口(採用可否の結果)を約束するものではありません。雇用機会均等法を変更して「均等」から逸脱するのは“不均等(差別)”であり本末転倒です。
大内さんは写真の下の説明で、「企業は女性社員にチャンスを与え、スキルや自信を身につけさせる事が肝要」と言っていますが、これが男女を問わない若手社員一般に対しての発言ならともかく、女性に限って言うのであれば、露骨に「機会の均等」に反する、「結果の均等以上」を狙った発言(妄言)です。
この記事は総てに於いて男女の能力には差がない事を前提としているように見受けられますが、何か根拠があるのでしょうか。
最近「機会の均等」の話しが「結果の均等」にすり替えられるケースが多発しています。
2月23日の読売新聞は、「航空大学校入試に女性枠、女性パイロット比率10%に引き上げへ…「身長158cm以上」要件を撤廃」と言う見出しで、次の様に報じていました。
------------------------------------------------------------------------------------
航空大学校入試に女性枠、女性パイロット比率10%に引き上げへ…「身長158cm以上」要件を撤廃
2025/02/23 20:37 読売
国土交通省は、航空機の操縦士を養成する航空大学校の入学試験で女性枠を設定し、2027年度の募集から導入する方針だ。日本の航空会社では女性操縦士の比率が1・9%と、世界の主要航空会社(平均4・7%)より低い。国交省は35年までに10%に引き上げる考えだ。
(中略)
航空大学校は国内の操縦士の約4割を養成するが、24年度の入学者のうち女性は6人(5・6%)にとどまっている。
-----------------------------------------------------------
現在の女性の比率が1.9%で、世界平均の4.7%を下回っているから、10%に引き上げるというのは、全く理由になっていません。
10%と158センチが並記されていて、158センチの条件が、女性が10%に満たない原因のような誤解を誘発する恐れがあります。
この記事以外にも近年男女雇用機会均等を雇用結果均等にすり替える動きが顕著です。
例えば、一流企業の役員ポストに「女性枠」や、雇用ではありませんが、国立大阪大学で理工系大学生に「女性枠」などです。
女性枠の設定の目的が、現状の少ない女性の採用数を増加することが目的であれば、合格者のラインが別枠のないときに比べて低下する事は当然であり、反対に女性の増加のしわ寄せにより男性の採用数(男性枠)の縮少を伴うのであれば、その合格ラインは上昇します。その結果女性の雇用機会は拡大し、一方男性の雇用機会は縮少する事になり、両者の雇用機会には格差(合格ラインの男高女低)が生じ、「男女の雇用機会の均等」は破壊されたことになります。
これらの女性別枠に於いては、合格・採用者全体の10%~30%程度を女性枠としているケースが普通ですが、その数値の根拠については誰からも何の説明もありません。このような行為は「男女雇用機会均等」の大原則に反するものであることは明白です。それにも拘わらず、「欧米に比べて・・・女性が少ない」の一言で内政問題が左右されて実現してしまい、それに対しての批判が皆無の日本社会は「病める社会」と言わざるを得ません。
令和7年3月16日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ