女教師・紀子
第二十五章:官能の連鎖(前編)
週明けの一日・・・月曜日は、放課後を過ぎても慌しい。
「田辺先生、さようなら」
「はい、さようなら・・・車には気を付けて帰るようにね」
廊下ですれ違う上級生の子達に、差し障りのない挨拶を返しながら
私は足早に東校舎の二階へと急ぐ。
早朝、いつもより早く登校するとすぐに全体職員会議。
その後の学年別会議や各種の連絡事項が職員室内に飛び交っているうちに
朝のホームルームの時間がやってくる。
そして授業が始まると、休み時間や授業のない時間までもが雑務に費やされてしまう。
新任一年目の要領の悪い新人教師だからと言うわけではなくて
どの先生方も終業の短い職員会議の後、疲れを滲ませながら
慌しい一日の終わりを安堵の表情で迎えていた。
でも、それが出来るのは一部の先生で、クラブ活動の顧問を請け負っている先生は
ホッと一息つく間もなく、足早に職員室を後にする。
まだ部活動には関っていない私だったけれど、顧問の先生方について教室を後にしていたの。
そんな私が向かっている先は、小さな会議室が並ぶ校舎の一角だった。
毎週明けに開かれる生徒委員会の一つ保健委員会は
予定では数分前には終了している時間だったけれど、望みを捨てないで階段を駆け上がる。
階段を登り切った時、階段から一番近い部屋の扉が開いて
揃いの制服を着た生徒の一団が廊下へと吐き出されて来た。
「えっ? あ、田辺先生・・・失礼しますっ」
スカートを翻し、頬を紅潮させて荒い息遣いをしながら廊下で仁王立ちしている私と
鉢合わせた生徒の幾人かは、戸惑いの表情を浮かべて私の側をすり抜けていく。
でも、その流れの最後の方に、流れに逆らうように立ちすくむ一人の生徒がいる。
各クラスの保健委員会のメンバーのほとんどが会議室を後にした所で
ようやく今日初めて、私は彼と一対一で向き合う事が出来た。
「・・・紀子・・・先生」
ホームルームや授業中・・・ううん、昨日のデートの別れ際と同じように
視線を合わせないように顔を背けたままの一也くんに
私は胸が締め付けられる想いを感じながらも、満面の笑みを浮かべて迎えたの。
「先生・・・あのっ、昨日の事・・・どうしたら償えるんですか??
今日一日、何度も考えても・・・何も・・・ごめんなさいっ!」
促されて部屋に入るなり一也くんは
その場に土下座してしまいそうな勢いで謝罪の言葉を口にした。
後について力なく廊下を歩く彼の様子を見て、この事を予測していた私は
小刻み震えている一也くんの身体を、優しく抱き締めてあげる。
「過ち・・・そうね、公園での事は先生が求めた結果だから気に病まなくていいの。
昨日の一也くんに罪があるとしたら、先生に飲ませたクスリの事を黙っていた事。
それを恥じて懺悔してくれるのなら、償う必要はないわ」
「でもっ・・・でも、僕の歪んだ愛情を先生はあんなに気遣ってくれたのに
僕は・・・何も学ばないで・・・淫らな欲望で先生を・・・汚して・・・っ」
やっぱり、危惧していた通り
一也くんは自分の性癖・・・好きな女性の恥部、汚れた部分に
性衝動を抱く事を恥じて強く自戒していたの。
だけど、思春期の男の子の不安定な心の内を強く責めることなんて出来ない。
それに、夜の公園で、私は強い羞恥を覚えながらも
素直に自身を曝け出した彼から熱い想いを感じていた。
だから、あんな・・・あんな淫らなセックスを、誰が見てるとも知れない中で
熱く激しく・・・受け止められたんだと思う・・・。
・・・でも、人の心は直接伝わらない。
公園での別れ際、彼に許しの言葉を伝えていたけれど
自分を強く恥じていた彼の耳には、私の気持ちは届かなかったみたい。
帰宅した日曜の夜から今日までの時間、ずっと、懺悔の念に苛まれていてたんだわ。
その長くて辛い思いを肌で感じて、慌しい時間の中で
一つの手段を思い巡らせていた私は、決意を固くする。
「苦しんでたのね・・・ごめんなさい、こんな時間まで何も出来なくて。
短い言葉で伝えても一也くんは、先生の気持ちを理解してくれないかも知れない。
だから・・・二人きりになれる時間まで我慢したのよ。
先生の気持ちが一番伝わる場所と方法を、放課後まで待っていたの・・・」
「せん・・・せい??」
抱き締めていた手を離して微笑みながら目の前に立つ私を
涙の滴を残した瞳で一也くんは見つめる。
彼が私を真っ直ぐに見つめてくれているのを確かめると
私は身を屈めて、明るい水色のフレアスカートを両手で掴むと
ゆっくりと裾をたくし上げていったの・・・。
「ダメよ、一也くんっ! 目をそらさないでっ。
でなきゃ、意味がないの!!
先生の気持ち・・・一也くんを許す気持ちが伝わらないわ」
目の前で突然始まった刺激的な行為に戸惑ったのか恥らったのか
目をそらそうとする彼を私は強く叱責した。
「女性の汚れた部分・・・そう、汚れた下着に強い性欲を感じる一也くんを許したい
先生の気持ちを、言葉では伝わらないなら・・・こうして・・・伝えたいの。
強い覚悟で・・・鍵はかけていても、教師として強い恥じらいを感じるこの場所で
教え子に・・・愛しくて大切な教え子の目の前で
今日一日身に着けていた下着を脱いで手渡す勇気を・・・感じ取って欲しいから。
だから、一也くん・・・お願い、先生を見つめていて・・・」
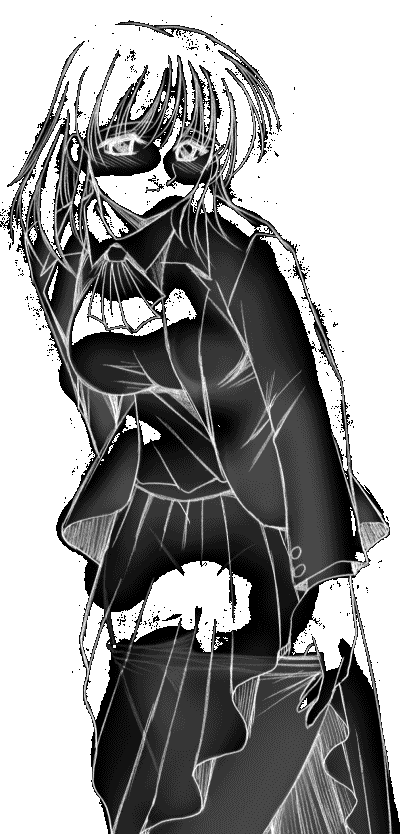 頬が焼けるように熱くなるのは隠せない・・・。
つい数時間前まで
大勢の教え子が真摯な瞳で見つめていた教壇の上で
ストリップまがいの行為に至ろうとしてる女教師の理性は
教え子を救う手段だと覚悟をしていても、悲鳴を上げてしまう!
人目を気にしないで済む生徒指導室なら
こんな激しい羞恥は感じないはずだった。
だけど、それじゃあ一也くんは
納得してくれないかもしれない。
今日一日、自戒の呪縛に捕らわれた彼の姿を
陰から見つめ続けた私は
生半可な態度じゃ、彼に誠意が伝わらないと感じていたの。
「そうよ・・・見ていて。
教室で・・・生徒達が学ぶ神聖な場所で下着を脱ぐ先生を・・・。
一日ずっと履いていた下着よ
何度もトイレにも行って用を足した、先生の汗と・・・
恥ずかしい匂いの染み付いた・・・汚れた下着・・・。
薬を飲まされたわけじゃない。脅されたわけじゃない。
自分で・・・自分から脱ぐの。
一也くんの事、怒っていないって伝えたいから・・・。
先生は今でも一也くんの事が大切なんだって
心から伝えたいからこうするの」
靴を脱いだ足首からストッキングと一緒に
ショーツが抜き取られる・・・。
明るいベージュのパンティーストッキングに覆われて
薄いピンク色のショーツが、掌の中でひっそりと丸まっている。
自宅に戻って着替えをする時には、いつも目にする光景だったけれど
ここは自宅ではなくて教室である事実が
私の中から強い羞恥心を湧き上がらせようとする。
だけど幸いにも、ショーツのクロッチ部分に
恥ずべき小水の染みが浮かんでいたとしても
ストッキングのベールがそれを私の目から覆い隠してくれていたの。
いざとなって彼に下着を差し出すのを躊躇ってしまう不手際は
ストッキングのお陰で解消されそう。
私は彼に気付かれないように心の中でホッとため息をつくと、顔を上げる。
「一也・・・くん??」
声をかけられた一也くんは
まるで何かの呪文が解けたかのように後ずさりして私を見つめた。
思っていた以上の効果があったみたい。
あんなに落ちこんでいた彼の頬が赤く染まっている。
私はそんな自分に素直な彼の目の前に、両手を差し出した。
「先生の気持ち、分かってくれたかしら??
さぁ、受け取って・・・そして、もう自分を責めるのは止めるのよ。
一也くんが元気になってくれて、また同じ物を望むのなら
先生、応えてあげるから・・・」
私の目と下着とを交互に見つめて、一也くんは小さくうなづくと
震える手で脱いだばかりの下着を受け取ってくれた。
まるで壊れやすい宝石を扱うかのように優しく両手で抱きかかえる。
「好きにしていいのよ・・・自宅で・・・ね」
私の目の前で、下着に顔を埋めてしまいそうなくらい熱い潤んだ眼差しで
手にした下着を見つめていた一也くんが慌てて自分のズボンのポケットに下着を押し込んだ。
「・・・・ごめんなさい」
「いいのよ、そんなに喜んでもらえて光栄よ・・・」
そこで、自然と会話が途切れてしまった。
私は安堵感で、彼は下着への強い関心で無口になる。
「帰りましょう・・・か??」
小さくうなづいた一也くんは、自分の机に向かうと
委員会の会議室から一緒に持ってきた自分の鞄を抱えて戻ってくる。
「あの・・・先生は?」
私も一緒に教室を出ると思っていたのか、一也くんは教室の前の方の扉の鍵を外そうとして
私がまだ教卓の前に立ったままでいるのに気付いて振りかえる。
「ええ・・・やり残してる事があるから、一也くんの後で出るわ」
きっと、手に入れた下着の事で頭が一杯なのだろう
気の回らない可愛い教え子は、私の説明に簡単に納得してしまう。
「あ、はい・・・それでは、お先に失礼します」
とても快活そうには見えなかったけれど
今日一日の落ち込んだ様子と違って内向的だけど礼儀正しい
いつもの一也くんに戻ってくれただけで私は十分に満足・・・なはずなのに。
「ええ、気を付けて・・・・」
一人教室に残された私は、自分でも理由の分からない寂しさを強く感じながら
彼の後姿を見送っていたの・・・。
それは、私に対する優しさなのかも知れなかった。
女性が下着を履き替える場面を恥らう事は、今日、目の当たりにしなくても
分かっていただろうから、彼なりに気遣って私を一人にしてくれたのかもしれない。
だけど、少しヒネた考え方をすると
学校を出るまで・・・帰宅してからも手にした下着に夢中で
好意を寄せる女教師がスカートの下に何も身に着けてないままでいる事自体を
忘れ去っているのかも知れない。
一也くんが元気になってくれるのは嬉しい・・・だけど
女性としてショックじゃないと言えば嘘になる。
その気になれば・・・そう、強引な手段に訴えなくても
ほんの少し頭を働かせて、落ちこんだ演技をすれば
こんな事をしてまで、自分を救いたいと願う女教師に
更なる・・・汚れた下着よりも、より淫らな要求が出来るかもしれないのに・・・。
誠くんのように、相手の気持ちを手玉に取るような事は望まない。
でも、男性として、下着を脱いだ生身の女性を目の前にして
「心ここにあらず」な態度を見せられて、私は苛立ちのような感情を抱いていたの。
私は替えのショーツとストッキングを入れたポーチを教卓の上に置いたまま
まだ強い日差しが差し込む教室の窓へと移動した。
運動場では、下校時間も過ぎようとしているのに
陸上部の子達が熱心に練習を続けてる。
張り詰めていた気持ちが一気に抜けた私は、その様子を漫然と二階の窓から見下す。
すると、グランド上でスタートダッシュの練習を繰り返す生徒の一人が
不意に校舎を見上げて立ち止まった。
頬が焼けるように熱くなるのは隠せない・・・。
つい数時間前まで
大勢の教え子が真摯な瞳で見つめていた教壇の上で
ストリップまがいの行為に至ろうとしてる女教師の理性は
教え子を救う手段だと覚悟をしていても、悲鳴を上げてしまう!
人目を気にしないで済む生徒指導室なら
こんな激しい羞恥は感じないはずだった。
だけど、それじゃあ一也くんは
納得してくれないかもしれない。
今日一日、自戒の呪縛に捕らわれた彼の姿を
陰から見つめ続けた私は
生半可な態度じゃ、彼に誠意が伝わらないと感じていたの。
「そうよ・・・見ていて。
教室で・・・生徒達が学ぶ神聖な場所で下着を脱ぐ先生を・・・。
一日ずっと履いていた下着よ
何度もトイレにも行って用を足した、先生の汗と・・・
恥ずかしい匂いの染み付いた・・・汚れた下着・・・。
薬を飲まされたわけじゃない。脅されたわけじゃない。
自分で・・・自分から脱ぐの。
一也くんの事、怒っていないって伝えたいから・・・。
先生は今でも一也くんの事が大切なんだって
心から伝えたいからこうするの」
靴を脱いだ足首からストッキングと一緒に
ショーツが抜き取られる・・・。
明るいベージュのパンティーストッキングに覆われて
薄いピンク色のショーツが、掌の中でひっそりと丸まっている。
自宅に戻って着替えをする時には、いつも目にする光景だったけれど
ここは自宅ではなくて教室である事実が
私の中から強い羞恥心を湧き上がらせようとする。
だけど幸いにも、ショーツのクロッチ部分に
恥ずべき小水の染みが浮かんでいたとしても
ストッキングのベールがそれを私の目から覆い隠してくれていたの。
いざとなって彼に下着を差し出すのを躊躇ってしまう不手際は
ストッキングのお陰で解消されそう。
私は彼に気付かれないように心の中でホッとため息をつくと、顔を上げる。
「一也・・・くん??」
声をかけられた一也くんは
まるで何かの呪文が解けたかのように後ずさりして私を見つめた。
思っていた以上の効果があったみたい。
あんなに落ちこんでいた彼の頬が赤く染まっている。
私はそんな自分に素直な彼の目の前に、両手を差し出した。
「先生の気持ち、分かってくれたかしら??
さぁ、受け取って・・・そして、もう自分を責めるのは止めるのよ。
一也くんが元気になってくれて、また同じ物を望むのなら
先生、応えてあげるから・・・」
私の目と下着とを交互に見つめて、一也くんは小さくうなづくと
震える手で脱いだばかりの下着を受け取ってくれた。
まるで壊れやすい宝石を扱うかのように優しく両手で抱きかかえる。
「好きにしていいのよ・・・自宅で・・・ね」
私の目の前で、下着に顔を埋めてしまいそうなくらい熱い潤んだ眼差しで
手にした下着を見つめていた一也くんが慌てて自分のズボンのポケットに下着を押し込んだ。
「・・・・ごめんなさい」
「いいのよ、そんなに喜んでもらえて光栄よ・・・」
そこで、自然と会話が途切れてしまった。
私は安堵感で、彼は下着への強い関心で無口になる。
「帰りましょう・・・か??」
小さくうなづいた一也くんは、自分の机に向かうと
委員会の会議室から一緒に持ってきた自分の鞄を抱えて戻ってくる。
「あの・・・先生は?」
私も一緒に教室を出ると思っていたのか、一也くんは教室の前の方の扉の鍵を外そうとして
私がまだ教卓の前に立ったままでいるのに気付いて振りかえる。
「ええ・・・やり残してる事があるから、一也くんの後で出るわ」
きっと、手に入れた下着の事で頭が一杯なのだろう
気の回らない可愛い教え子は、私の説明に簡単に納得してしまう。
「あ、はい・・・それでは、お先に失礼します」
とても快活そうには見えなかったけれど
今日一日の落ち込んだ様子と違って内向的だけど礼儀正しい
いつもの一也くんに戻ってくれただけで私は十分に満足・・・なはずなのに。
「ええ、気を付けて・・・・」
一人教室に残された私は、自分でも理由の分からない寂しさを強く感じながら
彼の後姿を見送っていたの・・・。
それは、私に対する優しさなのかも知れなかった。
女性が下着を履き替える場面を恥らう事は、今日、目の当たりにしなくても
分かっていただろうから、彼なりに気遣って私を一人にしてくれたのかもしれない。
だけど、少しヒネた考え方をすると
学校を出るまで・・・帰宅してからも手にした下着に夢中で
好意を寄せる女教師がスカートの下に何も身に着けてないままでいる事自体を
忘れ去っているのかも知れない。
一也くんが元気になってくれるのは嬉しい・・・だけど
女性としてショックじゃないと言えば嘘になる。
その気になれば・・・そう、強引な手段に訴えなくても
ほんの少し頭を働かせて、落ちこんだ演技をすれば
こんな事をしてまで、自分を救いたいと願う女教師に
更なる・・・汚れた下着よりも、より淫らな要求が出来るかもしれないのに・・・。
誠くんのように、相手の気持ちを手玉に取るような事は望まない。
でも、男性として、下着を脱いだ生身の女性を目の前にして
「心ここにあらず」な態度を見せられて、私は苛立ちのような感情を抱いていたの。
私は替えのショーツとストッキングを入れたポーチを教卓の上に置いたまま
まだ強い日差しが差し込む教室の窓へと移動した。
運動場では、下校時間も過ぎようとしているのに
陸上部の子達が熱心に練習を続けてる。
張り詰めていた気持ちが一気に抜けた私は、その様子を漫然と二階の窓から見下す。
すると、グランド上でスタートダッシュの練習を繰り返す生徒の一人が
不意に校舎を見上げて立ち止まった。
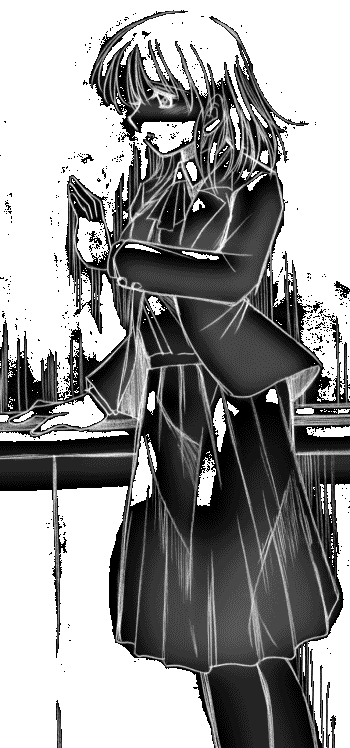 「・・・・えっ??」
戸惑いを思わず声に出してしまったけれど
細かな表情さえ見分けられない距離に隔てられて、私を遠くから見つめる彼は
ブルーな私の気持ちに気付かないで、無邪気に手を振ってくる。
「一組の宇佐美くん・・・?」
まだ一年生ながら陸上部で期待されている彼は
クラスの子ではなかったけれど
いつも私の授業で、快活に質問や回答をしてくれるので
印象が強く残っている。
さわやかな風貌と、クラス一番の身長で
きっと、この学校が共学だったら
女生徒が放っておかないくらいの男子だったの。
大切な練習を中断してまで手を振る彼に
気付かない振りをし続けるのが辛くなって、私も手を振り返す。
離れてて自分の気持ちが相手に伝わらないと思ったのか
私の応答に、彼は全身を使って喜びを表現してくれた。
「もう・・・ダメよ、部活動中でしょう。そんな事してたら・・・」
彼の反応に素直に喜びを感じた私は
相手には聞こえないにも関わらず声に出して応えてしまっていた。
そして案の定、心配は現実になってしまう。
先輩とおぼしき生徒の一人が後ろから近づくと、彼の頭をコツンと叩いた。
練習をサボっているのを咎められて、平謝りする彼。
すぐに視線をグランドに戻して、再び練習に集中する・・・。
「ほら、先生の言った通り・・・・」
つい口にした独り言が、教室の静寂に吸いこまれていくのを感じて
私は再び深いため息をつく。
そう、彼も・・・何も分かっていないのよ。
今の私が、下着も履かずにいる事を・・・。
女性として求められなかった寂しさを抱えている事を・・・。
グラウンドでは、陸上部の部員達が熱心に練習を繰り返してる。
少し離れたテニスコートでも、軟式テニス部の試合が行われてる。
きっと、室内プールでは水泳部・・・体育館ではバレーやバスケット。
文科系クラブの子達も、自分達の部室で部活動に励んでいるはずなのに
誰も気付いてはくれない・・・・。
当たり前だった。
今、私のスカートの中の真実を知っているのは一也くんだけ。
その一也くんも、きっともう下校しているはず。
だから、スカートの奥の秘密を知っているのは私だけなの。
女教師が、自分の教室で、剥き出しの下半身を
スカートの奥に隠しているなんて・・・誰も・・・。
「・・・・えっ??」
戸惑いを思わず声に出してしまったけれど
細かな表情さえ見分けられない距離に隔てられて、私を遠くから見つめる彼は
ブルーな私の気持ちに気付かないで、無邪気に手を振ってくる。
「一組の宇佐美くん・・・?」
まだ一年生ながら陸上部で期待されている彼は
クラスの子ではなかったけれど
いつも私の授業で、快活に質問や回答をしてくれるので
印象が強く残っている。
さわやかな風貌と、クラス一番の身長で
きっと、この学校が共学だったら
女生徒が放っておかないくらいの男子だったの。
大切な練習を中断してまで手を振る彼に
気付かない振りをし続けるのが辛くなって、私も手を振り返す。
離れてて自分の気持ちが相手に伝わらないと思ったのか
私の応答に、彼は全身を使って喜びを表現してくれた。
「もう・・・ダメよ、部活動中でしょう。そんな事してたら・・・」
彼の反応に素直に喜びを感じた私は
相手には聞こえないにも関わらず声に出して応えてしまっていた。
そして案の定、心配は現実になってしまう。
先輩とおぼしき生徒の一人が後ろから近づくと、彼の頭をコツンと叩いた。
練習をサボっているのを咎められて、平謝りする彼。
すぐに視線をグランドに戻して、再び練習に集中する・・・。
「ほら、先生の言った通り・・・・」
つい口にした独り言が、教室の静寂に吸いこまれていくのを感じて
私は再び深いため息をつく。
そう、彼も・・・何も分かっていないのよ。
今の私が、下着も履かずにいる事を・・・。
女性として求められなかった寂しさを抱えている事を・・・。
グラウンドでは、陸上部の部員達が熱心に練習を繰り返してる。
少し離れたテニスコートでも、軟式テニス部の試合が行われてる。
きっと、室内プールでは水泳部・・・体育館ではバレーやバスケット。
文科系クラブの子達も、自分達の部室で部活動に励んでいるはずなのに
誰も気付いてはくれない・・・・。
当たり前だった。
今、私のスカートの中の真実を知っているのは一也くんだけ。
その一也くんも、きっともう下校しているはず。
だから、スカートの奥の秘密を知っているのは私だけなの。
女教師が、自分の教室で、剥き出しの下半身を
スカートの奥に隠しているなんて・・・誰も・・・。
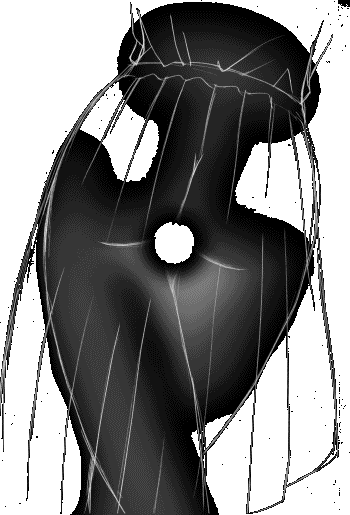 「そう、誰も知らないんだわ・・・」
心がザワザワと音を立て始める・・・。
「知らないから・・・誰も求めないんだわ。
でも、もし知ってしまったら・・・秘密を知ってしまったら」
胸が苦しくなる・・・身体が、理性が強く拒絶していよう。
「うら若い女教師が下着を身に着けていないと知ったら・・・。
スカートの奥で、女性器を無防備に曝していると知ってしまったら」
分かってる・・・分かっているわ。
簡単に言い訳の出来る行為じゃない事は十分分かってる。
脅迫されたわけじゃない、淫らに発情しているんじゃない
なのにっ、こんな・・・こんな事を望むなんて、どうかしてる!
「そうよ、どうかしてるのっ・・・先生は・・・」
グラウンドで他の部員達と黙々とランニングを続けてる宇佐美くんに
私は熱い視線を送りながら、つぶやいた。
「分からないのなら・・・先生の気持ち分かってくれないのならっ。
これなら、どう??・・・分かってくれるでしょう?
ねぇ・・・宇佐美くんっ!!」
それは、下着を脱ぐよりも遥かに簡単な動作だった。
だけど、覚悟も羞恥も遥かに下着より勝る行為だったの。
サイドの二つのホックとファスナーを外し
明るい水色の布地が力なく足元に落ちていった瞬間・・・。
私は、こみ上げる熱い固まりのような感情に声を詰まらせて
立ちくらんでしまう!
「ぁぁ・・・はぁぁぁ・・・っン、はふぅぅっ・・・・!!」
何もしていないのに、されてもいないのに
官能の色をたたえた熱いため息を吐き出しながら
私は軽い絶頂感に飲み込まれていたの。
窓のサッシにしがみ付かないと、その場に崩れ落ちそうになる・・・。
一瞬、止まったように感じた心臓から、再び鼓動が伝わってくる・・・。
全身が汗びっしょりになって、ブラウスの生地が肌に張りついて気持ち悪い・・・。
ひどい生理のように、子宮が膣からズリ落ちて来る感じがする・・・。
そして・・・ぁあっ、失禁したみたいに、アソコから発情の証が滴り落ちてるのっ。
「なんて、はしたないの・・・教室で、こんなに、教師が、アソコを濡らして
イってしまうなんてっ。オマ○コ曝して果ててしまうなんて・・・っ!」
窓ガラスに頬を強く押し付けながら、視線はグラウンドの彼に注がれる。
「軽蔑・・・するよね? 先生がこんな女だって知ったら君だって・・・」
自戒の言葉を口にしながらも、貪欲過ぎる私の中の情欲が
無意識に太股を擦り合わせ、刺激を受けた女性器が熱く昂ぶっていく!
「でも、これが先生なのっ・・・淫らな期待を膨らませて
それが叶わなければ、こんな格好で・・・わざと刺激を求めて
性欲を満たそうとする、破廉恥ではしたない・・・淫乱な教師なのっ」
小さな絶頂感と共に溢れ出したのとは別の新しい愛液が
性器から溢れ出てくるのを感じて、私は声に出して自分を責めた。
「だから・・・っ、思い切り軽蔑していいのっ。軽蔑した目で見つめて!
そして・・・先生を・・・もっと・・・感じさせてっ!
ぁぁあ・・・っ、宇佐美くんっ。先生っ・・・先生、もうたまらないわ!!」
そんなはずはない・・・ここから声なんて届くはずないのに
ランニングを終えた彼が、不意に顔を上げて
校舎を・・・教室の窓に持たれかかる私を見つめてくれたの!
周囲を覗いながら、そっと私に手で合図する彼・・・。
それだけで十分だった。
最後に残った理性のカケラが弾けて、私は股間に指を這わせるっ!
「はっ・・・うぅぅン!! いいっ!・・・気持ちいいっ!!」
一也くんに下着を差し出すと決めてからずっと・・・
私は、心の奥底で淫らな欲望を閉じ込めていたのかもしれない。
下着以上の行為を、彼から求められた時の対応を何度も頭の中で巡らせてるうちに
きっと・・・その萌芽は芽吹いてしまっていたんだわ。
「そう、誰も知らないんだわ・・・」
心がザワザワと音を立て始める・・・。
「知らないから・・・誰も求めないんだわ。
でも、もし知ってしまったら・・・秘密を知ってしまったら」
胸が苦しくなる・・・身体が、理性が強く拒絶していよう。
「うら若い女教師が下着を身に着けていないと知ったら・・・。
スカートの奥で、女性器を無防備に曝していると知ってしまったら」
分かってる・・・分かっているわ。
簡単に言い訳の出来る行為じゃない事は十分分かってる。
脅迫されたわけじゃない、淫らに発情しているんじゃない
なのにっ、こんな・・・こんな事を望むなんて、どうかしてる!
「そうよ、どうかしてるのっ・・・先生は・・・」
グラウンドで他の部員達と黙々とランニングを続けてる宇佐美くんに
私は熱い視線を送りながら、つぶやいた。
「分からないのなら・・・先生の気持ち分かってくれないのならっ。
これなら、どう??・・・分かってくれるでしょう?
ねぇ・・・宇佐美くんっ!!」
それは、下着を脱ぐよりも遥かに簡単な動作だった。
だけど、覚悟も羞恥も遥かに下着より勝る行為だったの。
サイドの二つのホックとファスナーを外し
明るい水色の布地が力なく足元に落ちていった瞬間・・・。
私は、こみ上げる熱い固まりのような感情に声を詰まらせて
立ちくらんでしまう!
「ぁぁ・・・はぁぁぁ・・・っン、はふぅぅっ・・・・!!」
何もしていないのに、されてもいないのに
官能の色をたたえた熱いため息を吐き出しながら
私は軽い絶頂感に飲み込まれていたの。
窓のサッシにしがみ付かないと、その場に崩れ落ちそうになる・・・。
一瞬、止まったように感じた心臓から、再び鼓動が伝わってくる・・・。
全身が汗びっしょりになって、ブラウスの生地が肌に張りついて気持ち悪い・・・。
ひどい生理のように、子宮が膣からズリ落ちて来る感じがする・・・。
そして・・・ぁあっ、失禁したみたいに、アソコから発情の証が滴り落ちてるのっ。
「なんて、はしたないの・・・教室で、こんなに、教師が、アソコを濡らして
イってしまうなんてっ。オマ○コ曝して果ててしまうなんて・・・っ!」
窓ガラスに頬を強く押し付けながら、視線はグラウンドの彼に注がれる。
「軽蔑・・・するよね? 先生がこんな女だって知ったら君だって・・・」
自戒の言葉を口にしながらも、貪欲過ぎる私の中の情欲が
無意識に太股を擦り合わせ、刺激を受けた女性器が熱く昂ぶっていく!
「でも、これが先生なのっ・・・淫らな期待を膨らませて
それが叶わなければ、こんな格好で・・・わざと刺激を求めて
性欲を満たそうとする、破廉恥ではしたない・・・淫乱な教師なのっ」
小さな絶頂感と共に溢れ出したのとは別の新しい愛液が
性器から溢れ出てくるのを感じて、私は声に出して自分を責めた。
「だから・・・っ、思い切り軽蔑していいのっ。軽蔑した目で見つめて!
そして・・・先生を・・・もっと・・・感じさせてっ!
ぁぁあ・・・っ、宇佐美くんっ。先生っ・・・先生、もうたまらないわ!!」
そんなはずはない・・・ここから声なんて届くはずないのに
ランニングを終えた彼が、不意に顔を上げて
校舎を・・・教室の窓に持たれかかる私を見つめてくれたの!
周囲を覗いながら、そっと私に手で合図する彼・・・。
それだけで十分だった。
最後に残った理性のカケラが弾けて、私は股間に指を這わせるっ!
「はっ・・・うぅぅン!! いいっ!・・・気持ちいいっ!!」
一也くんに下着を差し出すと決めてからずっと・・・
私は、心の奥底で淫らな欲望を閉じ込めていたのかもしれない。
下着以上の行為を、彼から求められた時の対応を何度も頭の中で巡らせてるうちに
きっと・・・その萌芽は芽吹いてしまっていたんだわ。
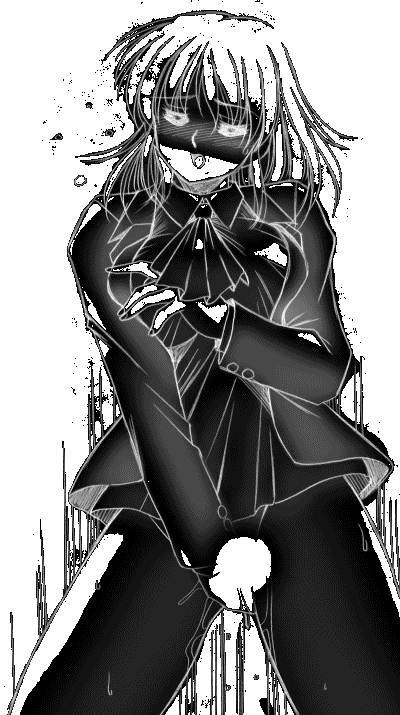 自虐の悦びに溺れる・・・マゾヒスティックな性癖・・・。
こんな自分だから、一也くんを責める資格なんかないから
彼の性癖も許してあげられたのかもしれない。
例え度重なる恥辱に抗えずに植え付けられたものだとしても
拭い去る事が出来ないのなら、一也くんと同じ。
女教師の汚れた下着の匂いを嗅ぎながら耽るオナニーと
生徒の視線を感じながら剥き出しの淫部を弄るオナニー・・・。
誰もが軽蔑の眼差しを向ける、淫靡でアブノーマルな性癖!
「いやぁ・・・ぁン、指が・・・っ、指が弄ってるのぉ。
先生のオマ○コ、イヤらしく弄ってるのよっ」
一也くんと私が同じなら・・・そうなの?
私自身も許してもらいたいの??
認めて欲しいから、こんな身の破滅を誘っても
おかしくない行為に耽って、一也くんが心で葛藤しながらも
私に利尿剤を飲ませたように、淫らな性癖に気付いて
愛してくれる誰かを・・・私、求めているの?!
「こんなに濡れてるのっ!
こんなにグチュグチュ濡らしてるっ・・・。
あぁっ、聞こえる?? 宇佐美くんっ!
先生のイヤらしい音・・・聞こえるんでしょう!?」
校舎を見上げながら、応答を待ち続けてる彼に
私はガラス越しにそう叫んでたの。
「聞いてっ・・・先生の側に来て、この音を聞いてっ!
そしてっ・・・先生のこと、軽蔑してっ!!
こんな先生をっ・・・はしたない先生をっ・・・蔑んで構わないわ!」
「そしてっ・・・そして、愛してちょうだい!
昂ぶったオチ○チンで先生を貫いてっ!!
たぎった精液をオマ○コに注いで先生を汚してっ!!}
「先生は・・・紀子は・・・ぁあっ、マゾっ・・・マゾだからっ!!」
激しい絶頂感が襲ってくると同時に
私は力なく膝から床に崩れ落ちていった・・・。
両膝を開いて正座するお尻に冷たい床の感触が心地良く感じて
無意識に腰を揺すってしまう。
「ぁぁっ・・・宇佐美くん・・・見てくれてた??
先生がイクの・・・ちゃんと見てた?」
あんなに絶頂を感じたのに、私の情欲は貪欲に新たな刺激を求め始める。
「冷たいの・・・お尻が・・・ぁあっ、また感じて来ちゃうぅ・・・。
先生、お尻でも・・・感じてしまう女なのよ・・・っ」
でも、その時だったの・・・その音に気付いたのは。
身体は窓の下にもたれ掛かって、視界の先は壁だったけれど
その音は・・・喘ぐ私の息遣いだけが響く教室に、微かに私の耳に届いたの。
「だ・・・誰、なの?? 一也くん?・・・それとも誠くん??
ねぇ、応えて・・・どうして教室の鍵、持っているの??」
振り向けば、鍵を開けようとしてる相手の正体が分かるかもしれない。
でも私は、鍵が開けられ扉が軋む音を聞いても振り返る事が出来なかったの。
足音が静かに近づいてくる・・・。
手を伸ばせば床に落ちたスカートを手繰り寄せて
剥き出しの下半身を覆うくらいの事は出来るのに
それさえ、真実を確信して身がすくんだ私には思い付かない。
教室の前の扉は一也くんが開けたままだった・・・。
職員室にある教室の鍵は、今私が持ってる・・・。
わざわざスペアの鍵で後ろの扉を開けられるのは・・・!?
靴音がすぐ背後で止まっても、振り向く勇気は私にはなかった。
「田辺先生・・・まだ満足なさっていないみたいですね?」
その冷たい・・・丁寧な口調の奥に、冷たい感情を秘めた声に
私は声を詰まらせ、身を縮ませるっ!
本能的に身体を丸め、その厄災が通り過ぎるのを待とうとした。
でも冷酷な現実は、私を更なる辱めを与えようとしていたの。
「えっ・・・?? く、国崎さん・・・何をっ??」
犯されてもおかしくない状況で、身体に指一本触れないで
去っていく足音に不安になった私が意を決して振り返ると
彼は教室を後にしようとしていた。
「お一人で、おもしろい事をなさっていましたから
私もその遊びに混ぜていただこうと思いましてね」
冷たい笑みを浮かべて、校務員の彼は教室を出ていってしまう。
「まっ、待って下さい国崎さんっ!!
そんなっ・・・私っ・・・無理ですっ!!」
涙声で訴える私を一人残して
彼の大柄なシルエットが教室のすりガラスの向こうに消えていった・・・。
そう・・・手には、替えの下着が入ったポーチと拾い上げたスカートを持ったまま・・・・。
自虐の悦びに溺れる・・・マゾヒスティックな性癖・・・。
こんな自分だから、一也くんを責める資格なんかないから
彼の性癖も許してあげられたのかもしれない。
例え度重なる恥辱に抗えずに植え付けられたものだとしても
拭い去る事が出来ないのなら、一也くんと同じ。
女教師の汚れた下着の匂いを嗅ぎながら耽るオナニーと
生徒の視線を感じながら剥き出しの淫部を弄るオナニー・・・。
誰もが軽蔑の眼差しを向ける、淫靡でアブノーマルな性癖!
「いやぁ・・・ぁン、指が・・・っ、指が弄ってるのぉ。
先生のオマ○コ、イヤらしく弄ってるのよっ」
一也くんと私が同じなら・・・そうなの?
私自身も許してもらいたいの??
認めて欲しいから、こんな身の破滅を誘っても
おかしくない行為に耽って、一也くんが心で葛藤しながらも
私に利尿剤を飲ませたように、淫らな性癖に気付いて
愛してくれる誰かを・・・私、求めているの?!
「こんなに濡れてるのっ!
こんなにグチュグチュ濡らしてるっ・・・。
あぁっ、聞こえる?? 宇佐美くんっ!
先生のイヤらしい音・・・聞こえるんでしょう!?」
校舎を見上げながら、応答を待ち続けてる彼に
私はガラス越しにそう叫んでたの。
「聞いてっ・・・先生の側に来て、この音を聞いてっ!
そしてっ・・・先生のこと、軽蔑してっ!!
こんな先生をっ・・・はしたない先生をっ・・・蔑んで構わないわ!」
「そしてっ・・・そして、愛してちょうだい!
昂ぶったオチ○チンで先生を貫いてっ!!
たぎった精液をオマ○コに注いで先生を汚してっ!!}
「先生は・・・紀子は・・・ぁあっ、マゾっ・・・マゾだからっ!!」
激しい絶頂感が襲ってくると同時に
私は力なく膝から床に崩れ落ちていった・・・。
両膝を開いて正座するお尻に冷たい床の感触が心地良く感じて
無意識に腰を揺すってしまう。
「ぁぁっ・・・宇佐美くん・・・見てくれてた??
先生がイクの・・・ちゃんと見てた?」
あんなに絶頂を感じたのに、私の情欲は貪欲に新たな刺激を求め始める。
「冷たいの・・・お尻が・・・ぁあっ、また感じて来ちゃうぅ・・・。
先生、お尻でも・・・感じてしまう女なのよ・・・っ」
でも、その時だったの・・・その音に気付いたのは。
身体は窓の下にもたれ掛かって、視界の先は壁だったけれど
その音は・・・喘ぐ私の息遣いだけが響く教室に、微かに私の耳に届いたの。
「だ・・・誰、なの?? 一也くん?・・・それとも誠くん??
ねぇ、応えて・・・どうして教室の鍵、持っているの??」
振り向けば、鍵を開けようとしてる相手の正体が分かるかもしれない。
でも私は、鍵が開けられ扉が軋む音を聞いても振り返る事が出来なかったの。
足音が静かに近づいてくる・・・。
手を伸ばせば床に落ちたスカートを手繰り寄せて
剥き出しの下半身を覆うくらいの事は出来るのに
それさえ、真実を確信して身がすくんだ私には思い付かない。
教室の前の扉は一也くんが開けたままだった・・・。
職員室にある教室の鍵は、今私が持ってる・・・。
わざわざスペアの鍵で後ろの扉を開けられるのは・・・!?
靴音がすぐ背後で止まっても、振り向く勇気は私にはなかった。
「田辺先生・・・まだ満足なさっていないみたいですね?」
その冷たい・・・丁寧な口調の奥に、冷たい感情を秘めた声に
私は声を詰まらせ、身を縮ませるっ!
本能的に身体を丸め、その厄災が通り過ぎるのを待とうとした。
でも冷酷な現実は、私を更なる辱めを与えようとしていたの。
「えっ・・・?? く、国崎さん・・・何をっ??」
犯されてもおかしくない状況で、身体に指一本触れないで
去っていく足音に不安になった私が意を決して振り返ると
彼は教室を後にしようとしていた。
「お一人で、おもしろい事をなさっていましたから
私もその遊びに混ぜていただこうと思いましてね」
冷たい笑みを浮かべて、校務員の彼は教室を出ていってしまう。
「まっ、待って下さい国崎さんっ!!
そんなっ・・・私っ・・・無理ですっ!!」
涙声で訴える私を一人残して
彼の大柄なシルエットが教室のすりガラスの向こうに消えていった・・・。
そう・・・手には、替えの下着が入ったポーチと拾い上げたスカートを持ったまま・・・・。
<第二十五章:官能の連鎖(前編)・終>
<次章「官能の連鎖(後編)」>
<第二十五章「あとがき」を読む>
<親父の趣味の部屋へ戻る>
<タイトルページへ戻る>
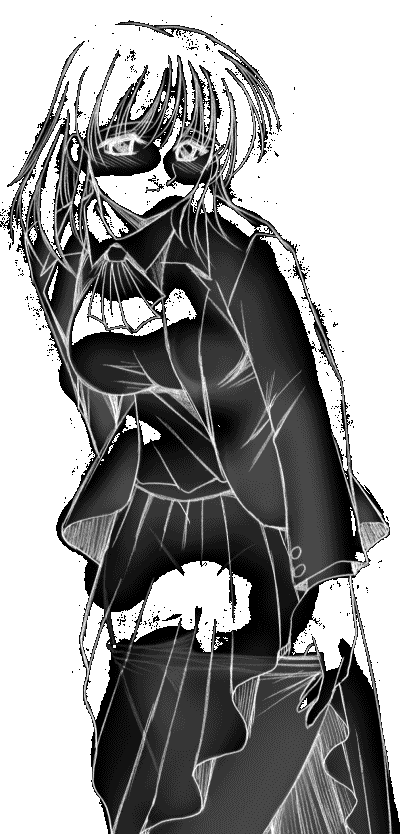 頬が焼けるように熱くなるのは隠せない・・・。
つい数時間前まで
大勢の教え子が真摯な瞳で見つめていた教壇の上で
ストリップまがいの行為に至ろうとしてる女教師の理性は
教え子を救う手段だと覚悟をしていても、悲鳴を上げてしまう!
人目を気にしないで済む生徒指導室なら
こんな激しい羞恥は感じないはずだった。
だけど、それじゃあ一也くんは
納得してくれないかもしれない。
今日一日、自戒の呪縛に捕らわれた彼の姿を
陰から見つめ続けた私は
生半可な態度じゃ、彼に誠意が伝わらないと感じていたの。
「そうよ・・・見ていて。
教室で・・・生徒達が学ぶ神聖な場所で下着を脱ぐ先生を・・・。
一日ずっと履いていた下着よ
何度もトイレにも行って用を足した、先生の汗と・・・
恥ずかしい匂いの染み付いた・・・汚れた下着・・・。
薬を飲まされたわけじゃない。脅されたわけじゃない。
自分で・・・自分から脱ぐの。
一也くんの事、怒っていないって伝えたいから・・・。
先生は今でも一也くんの事が大切なんだって
心から伝えたいからこうするの」
靴を脱いだ足首からストッキングと一緒に
ショーツが抜き取られる・・・。
明るいベージュのパンティーストッキングに覆われて
薄いピンク色のショーツが、掌の中でひっそりと丸まっている。
自宅に戻って着替えをする時には、いつも目にする光景だったけれど
ここは自宅ではなくて教室である事実が
私の中から強い羞恥心を湧き上がらせようとする。
だけど幸いにも、ショーツのクロッチ部分に
恥ずべき小水の染みが浮かんでいたとしても
ストッキングのベールがそれを私の目から覆い隠してくれていたの。
いざとなって彼に下着を差し出すのを躊躇ってしまう不手際は
ストッキングのお陰で解消されそう。
私は彼に気付かれないように心の中でホッとため息をつくと、顔を上げる。
「一也・・・くん??」
声をかけられた一也くんは
まるで何かの呪文が解けたかのように後ずさりして私を見つめた。
思っていた以上の効果があったみたい。
あんなに落ちこんでいた彼の頬が赤く染まっている。
私はそんな自分に素直な彼の目の前に、両手を差し出した。
「先生の気持ち、分かってくれたかしら??
さぁ、受け取って・・・そして、もう自分を責めるのは止めるのよ。
一也くんが元気になってくれて、また同じ物を望むのなら
先生、応えてあげるから・・・」
私の目と下着とを交互に見つめて、一也くんは小さくうなづくと
震える手で脱いだばかりの下着を受け取ってくれた。
まるで壊れやすい宝石を扱うかのように優しく両手で抱きかかえる。
「好きにしていいのよ・・・自宅で・・・ね」
私の目の前で、下着に顔を埋めてしまいそうなくらい熱い潤んだ眼差しで
手にした下着を見つめていた一也くんが慌てて自分のズボンのポケットに下着を押し込んだ。
「・・・・ごめんなさい」
「いいのよ、そんなに喜んでもらえて光栄よ・・・」
そこで、自然と会話が途切れてしまった。
私は安堵感で、彼は下着への強い関心で無口になる。
「帰りましょう・・・か??」
小さくうなづいた一也くんは、自分の机に向かうと
委員会の会議室から一緒に持ってきた自分の鞄を抱えて戻ってくる。
「あの・・・先生は?」
私も一緒に教室を出ると思っていたのか、一也くんは教室の前の方の扉の鍵を外そうとして
私がまだ教卓の前に立ったままでいるのに気付いて振りかえる。
「ええ・・・やり残してる事があるから、一也くんの後で出るわ」
きっと、手に入れた下着の事で頭が一杯なのだろう
気の回らない可愛い教え子は、私の説明に簡単に納得してしまう。
「あ、はい・・・それでは、お先に失礼します」
とても快活そうには見えなかったけれど
今日一日の落ち込んだ様子と違って内向的だけど礼儀正しい
いつもの一也くんに戻ってくれただけで私は十分に満足・・・なはずなのに。
「ええ、気を付けて・・・・」
一人教室に残された私は、自分でも理由の分からない寂しさを強く感じながら
彼の後姿を見送っていたの・・・。
それは、私に対する優しさなのかも知れなかった。
女性が下着を履き替える場面を恥らう事は、今日、目の当たりにしなくても
分かっていただろうから、彼なりに気遣って私を一人にしてくれたのかもしれない。
だけど、少しヒネた考え方をすると
学校を出るまで・・・帰宅してからも手にした下着に夢中で
好意を寄せる女教師がスカートの下に何も身に着けてないままでいる事自体を
忘れ去っているのかも知れない。
一也くんが元気になってくれるのは嬉しい・・・だけど
女性としてショックじゃないと言えば嘘になる。
その気になれば・・・そう、強引な手段に訴えなくても
ほんの少し頭を働かせて、落ちこんだ演技をすれば
こんな事をしてまで、自分を救いたいと願う女教師に
更なる・・・汚れた下着よりも、より淫らな要求が出来るかもしれないのに・・・。
誠くんのように、相手の気持ちを手玉に取るような事は望まない。
でも、男性として、下着を脱いだ生身の女性を目の前にして
「心ここにあらず」な態度を見せられて、私は苛立ちのような感情を抱いていたの。
私は替えのショーツとストッキングを入れたポーチを教卓の上に置いたまま
まだ強い日差しが差し込む教室の窓へと移動した。
運動場では、下校時間も過ぎようとしているのに
陸上部の子達が熱心に練習を続けてる。
張り詰めていた気持ちが一気に抜けた私は、その様子を漫然と二階の窓から見下す。
すると、グランド上でスタートダッシュの練習を繰り返す生徒の一人が
不意に校舎を見上げて立ち止まった。
頬が焼けるように熱くなるのは隠せない・・・。
つい数時間前まで
大勢の教え子が真摯な瞳で見つめていた教壇の上で
ストリップまがいの行為に至ろうとしてる女教師の理性は
教え子を救う手段だと覚悟をしていても、悲鳴を上げてしまう!
人目を気にしないで済む生徒指導室なら
こんな激しい羞恥は感じないはずだった。
だけど、それじゃあ一也くんは
納得してくれないかもしれない。
今日一日、自戒の呪縛に捕らわれた彼の姿を
陰から見つめ続けた私は
生半可な態度じゃ、彼に誠意が伝わらないと感じていたの。
「そうよ・・・見ていて。
教室で・・・生徒達が学ぶ神聖な場所で下着を脱ぐ先生を・・・。
一日ずっと履いていた下着よ
何度もトイレにも行って用を足した、先生の汗と・・・
恥ずかしい匂いの染み付いた・・・汚れた下着・・・。
薬を飲まされたわけじゃない。脅されたわけじゃない。
自分で・・・自分から脱ぐの。
一也くんの事、怒っていないって伝えたいから・・・。
先生は今でも一也くんの事が大切なんだって
心から伝えたいからこうするの」
靴を脱いだ足首からストッキングと一緒に
ショーツが抜き取られる・・・。
明るいベージュのパンティーストッキングに覆われて
薄いピンク色のショーツが、掌の中でひっそりと丸まっている。
自宅に戻って着替えをする時には、いつも目にする光景だったけれど
ここは自宅ではなくて教室である事実が
私の中から強い羞恥心を湧き上がらせようとする。
だけど幸いにも、ショーツのクロッチ部分に
恥ずべき小水の染みが浮かんでいたとしても
ストッキングのベールがそれを私の目から覆い隠してくれていたの。
いざとなって彼に下着を差し出すのを躊躇ってしまう不手際は
ストッキングのお陰で解消されそう。
私は彼に気付かれないように心の中でホッとため息をつくと、顔を上げる。
「一也・・・くん??」
声をかけられた一也くんは
まるで何かの呪文が解けたかのように後ずさりして私を見つめた。
思っていた以上の効果があったみたい。
あんなに落ちこんでいた彼の頬が赤く染まっている。
私はそんな自分に素直な彼の目の前に、両手を差し出した。
「先生の気持ち、分かってくれたかしら??
さぁ、受け取って・・・そして、もう自分を責めるのは止めるのよ。
一也くんが元気になってくれて、また同じ物を望むのなら
先生、応えてあげるから・・・」
私の目と下着とを交互に見つめて、一也くんは小さくうなづくと
震える手で脱いだばかりの下着を受け取ってくれた。
まるで壊れやすい宝石を扱うかのように優しく両手で抱きかかえる。
「好きにしていいのよ・・・自宅で・・・ね」
私の目の前で、下着に顔を埋めてしまいそうなくらい熱い潤んだ眼差しで
手にした下着を見つめていた一也くんが慌てて自分のズボンのポケットに下着を押し込んだ。
「・・・・ごめんなさい」
「いいのよ、そんなに喜んでもらえて光栄よ・・・」
そこで、自然と会話が途切れてしまった。
私は安堵感で、彼は下着への強い関心で無口になる。
「帰りましょう・・・か??」
小さくうなづいた一也くんは、自分の机に向かうと
委員会の会議室から一緒に持ってきた自分の鞄を抱えて戻ってくる。
「あの・・・先生は?」
私も一緒に教室を出ると思っていたのか、一也くんは教室の前の方の扉の鍵を外そうとして
私がまだ教卓の前に立ったままでいるのに気付いて振りかえる。
「ええ・・・やり残してる事があるから、一也くんの後で出るわ」
きっと、手に入れた下着の事で頭が一杯なのだろう
気の回らない可愛い教え子は、私の説明に簡単に納得してしまう。
「あ、はい・・・それでは、お先に失礼します」
とても快活そうには見えなかったけれど
今日一日の落ち込んだ様子と違って内向的だけど礼儀正しい
いつもの一也くんに戻ってくれただけで私は十分に満足・・・なはずなのに。
「ええ、気を付けて・・・・」
一人教室に残された私は、自分でも理由の分からない寂しさを強く感じながら
彼の後姿を見送っていたの・・・。
それは、私に対する優しさなのかも知れなかった。
女性が下着を履き替える場面を恥らう事は、今日、目の当たりにしなくても
分かっていただろうから、彼なりに気遣って私を一人にしてくれたのかもしれない。
だけど、少しヒネた考え方をすると
学校を出るまで・・・帰宅してからも手にした下着に夢中で
好意を寄せる女教師がスカートの下に何も身に着けてないままでいる事自体を
忘れ去っているのかも知れない。
一也くんが元気になってくれるのは嬉しい・・・だけど
女性としてショックじゃないと言えば嘘になる。
その気になれば・・・そう、強引な手段に訴えなくても
ほんの少し頭を働かせて、落ちこんだ演技をすれば
こんな事をしてまで、自分を救いたいと願う女教師に
更なる・・・汚れた下着よりも、より淫らな要求が出来るかもしれないのに・・・。
誠くんのように、相手の気持ちを手玉に取るような事は望まない。
でも、男性として、下着を脱いだ生身の女性を目の前にして
「心ここにあらず」な態度を見せられて、私は苛立ちのような感情を抱いていたの。
私は替えのショーツとストッキングを入れたポーチを教卓の上に置いたまま
まだ強い日差しが差し込む教室の窓へと移動した。
運動場では、下校時間も過ぎようとしているのに
陸上部の子達が熱心に練習を続けてる。
張り詰めていた気持ちが一気に抜けた私は、その様子を漫然と二階の窓から見下す。
すると、グランド上でスタートダッシュの練習を繰り返す生徒の一人が
不意に校舎を見上げて立ち止まった。
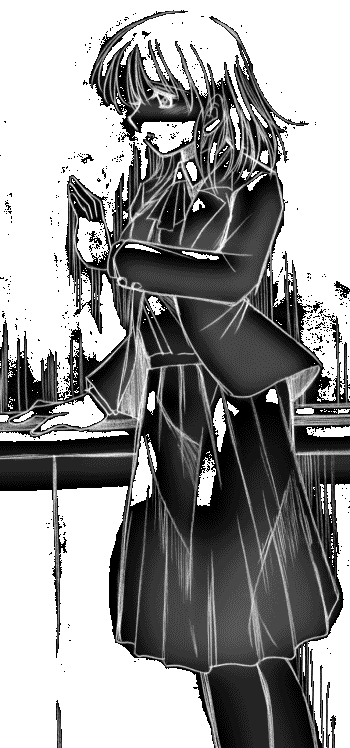 「・・・・えっ??」
戸惑いを思わず声に出してしまったけれど
細かな表情さえ見分けられない距離に隔てられて、私を遠くから見つめる彼は
ブルーな私の気持ちに気付かないで、無邪気に手を振ってくる。
「一組の宇佐美くん・・・?」
まだ一年生ながら陸上部で期待されている彼は
クラスの子ではなかったけれど
いつも私の授業で、快活に質問や回答をしてくれるので
印象が強く残っている。
さわやかな風貌と、クラス一番の身長で
きっと、この学校が共学だったら
女生徒が放っておかないくらいの男子だったの。
大切な練習を中断してまで手を振る彼に
気付かない振りをし続けるのが辛くなって、私も手を振り返す。
離れてて自分の気持ちが相手に伝わらないと思ったのか
私の応答に、彼は全身を使って喜びを表現してくれた。
「もう・・・ダメよ、部活動中でしょう。そんな事してたら・・・」
彼の反応に素直に喜びを感じた私は
相手には聞こえないにも関わらず声に出して応えてしまっていた。
そして案の定、心配は現実になってしまう。
先輩とおぼしき生徒の一人が後ろから近づくと、彼の頭をコツンと叩いた。
練習をサボっているのを咎められて、平謝りする彼。
すぐに視線をグランドに戻して、再び練習に集中する・・・。
「ほら、先生の言った通り・・・・」
つい口にした独り言が、教室の静寂に吸いこまれていくのを感じて
私は再び深いため息をつく。
そう、彼も・・・何も分かっていないのよ。
今の私が、下着も履かずにいる事を・・・。
女性として求められなかった寂しさを抱えている事を・・・。
グラウンドでは、陸上部の部員達が熱心に練習を繰り返してる。
少し離れたテニスコートでも、軟式テニス部の試合が行われてる。
きっと、室内プールでは水泳部・・・体育館ではバレーやバスケット。
文科系クラブの子達も、自分達の部室で部活動に励んでいるはずなのに
誰も気付いてはくれない・・・・。
当たり前だった。
今、私のスカートの中の真実を知っているのは一也くんだけ。
その一也くんも、きっともう下校しているはず。
だから、スカートの奥の秘密を知っているのは私だけなの。
女教師が、自分の教室で、剥き出しの下半身を
スカートの奥に隠しているなんて・・・誰も・・・。
「・・・・えっ??」
戸惑いを思わず声に出してしまったけれど
細かな表情さえ見分けられない距離に隔てられて、私を遠くから見つめる彼は
ブルーな私の気持ちに気付かないで、無邪気に手を振ってくる。
「一組の宇佐美くん・・・?」
まだ一年生ながら陸上部で期待されている彼は
クラスの子ではなかったけれど
いつも私の授業で、快活に質問や回答をしてくれるので
印象が強く残っている。
さわやかな風貌と、クラス一番の身長で
きっと、この学校が共学だったら
女生徒が放っておかないくらいの男子だったの。
大切な練習を中断してまで手を振る彼に
気付かない振りをし続けるのが辛くなって、私も手を振り返す。
離れてて自分の気持ちが相手に伝わらないと思ったのか
私の応答に、彼は全身を使って喜びを表現してくれた。
「もう・・・ダメよ、部活動中でしょう。そんな事してたら・・・」
彼の反応に素直に喜びを感じた私は
相手には聞こえないにも関わらず声に出して応えてしまっていた。
そして案の定、心配は現実になってしまう。
先輩とおぼしき生徒の一人が後ろから近づくと、彼の頭をコツンと叩いた。
練習をサボっているのを咎められて、平謝りする彼。
すぐに視線をグランドに戻して、再び練習に集中する・・・。
「ほら、先生の言った通り・・・・」
つい口にした独り言が、教室の静寂に吸いこまれていくのを感じて
私は再び深いため息をつく。
そう、彼も・・・何も分かっていないのよ。
今の私が、下着も履かずにいる事を・・・。
女性として求められなかった寂しさを抱えている事を・・・。
グラウンドでは、陸上部の部員達が熱心に練習を繰り返してる。
少し離れたテニスコートでも、軟式テニス部の試合が行われてる。
きっと、室内プールでは水泳部・・・体育館ではバレーやバスケット。
文科系クラブの子達も、自分達の部室で部活動に励んでいるはずなのに
誰も気付いてはくれない・・・・。
当たり前だった。
今、私のスカートの中の真実を知っているのは一也くんだけ。
その一也くんも、きっともう下校しているはず。
だから、スカートの奥の秘密を知っているのは私だけなの。
女教師が、自分の教室で、剥き出しの下半身を
スカートの奥に隠しているなんて・・・誰も・・・。
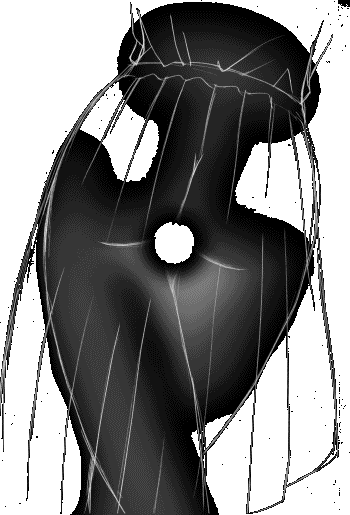 「そう、誰も知らないんだわ・・・」
心がザワザワと音を立て始める・・・。
「知らないから・・・誰も求めないんだわ。
でも、もし知ってしまったら・・・秘密を知ってしまったら」
胸が苦しくなる・・・身体が、理性が強く拒絶していよう。
「うら若い女教師が下着を身に着けていないと知ったら・・・。
スカートの奥で、女性器を無防備に曝していると知ってしまったら」
分かってる・・・分かっているわ。
簡単に言い訳の出来る行為じゃない事は十分分かってる。
脅迫されたわけじゃない、淫らに発情しているんじゃない
なのにっ、こんな・・・こんな事を望むなんて、どうかしてる!
「そうよ、どうかしてるのっ・・・先生は・・・」
グラウンドで他の部員達と黙々とランニングを続けてる宇佐美くんに
私は熱い視線を送りながら、つぶやいた。
「分からないのなら・・・先生の気持ち分かってくれないのならっ。
これなら、どう??・・・分かってくれるでしょう?
ねぇ・・・宇佐美くんっ!!」
それは、下着を脱ぐよりも遥かに簡単な動作だった。
だけど、覚悟も羞恥も遥かに下着より勝る行為だったの。
サイドの二つのホックとファスナーを外し
明るい水色の布地が力なく足元に落ちていった瞬間・・・。
私は、こみ上げる熱い固まりのような感情に声を詰まらせて
立ちくらんでしまう!
「ぁぁ・・・はぁぁぁ・・・っン、はふぅぅっ・・・・!!」
何もしていないのに、されてもいないのに
官能の色をたたえた熱いため息を吐き出しながら
私は軽い絶頂感に飲み込まれていたの。
窓のサッシにしがみ付かないと、その場に崩れ落ちそうになる・・・。
一瞬、止まったように感じた心臓から、再び鼓動が伝わってくる・・・。
全身が汗びっしょりになって、ブラウスの生地が肌に張りついて気持ち悪い・・・。
ひどい生理のように、子宮が膣からズリ落ちて来る感じがする・・・。
そして・・・ぁあっ、失禁したみたいに、アソコから発情の証が滴り落ちてるのっ。
「なんて、はしたないの・・・教室で、こんなに、教師が、アソコを濡らして
イってしまうなんてっ。オマ○コ曝して果ててしまうなんて・・・っ!」
窓ガラスに頬を強く押し付けながら、視線はグラウンドの彼に注がれる。
「軽蔑・・・するよね? 先生がこんな女だって知ったら君だって・・・」
自戒の言葉を口にしながらも、貪欲過ぎる私の中の情欲が
無意識に太股を擦り合わせ、刺激を受けた女性器が熱く昂ぶっていく!
「でも、これが先生なのっ・・・淫らな期待を膨らませて
それが叶わなければ、こんな格好で・・・わざと刺激を求めて
性欲を満たそうとする、破廉恥ではしたない・・・淫乱な教師なのっ」
小さな絶頂感と共に溢れ出したのとは別の新しい愛液が
性器から溢れ出てくるのを感じて、私は声に出して自分を責めた。
「だから・・・っ、思い切り軽蔑していいのっ。軽蔑した目で見つめて!
そして・・・先生を・・・もっと・・・感じさせてっ!
ぁぁあ・・・っ、宇佐美くんっ。先生っ・・・先生、もうたまらないわ!!」
そんなはずはない・・・ここから声なんて届くはずないのに
ランニングを終えた彼が、不意に顔を上げて
校舎を・・・教室の窓に持たれかかる私を見つめてくれたの!
周囲を覗いながら、そっと私に手で合図する彼・・・。
それだけで十分だった。
最後に残った理性のカケラが弾けて、私は股間に指を這わせるっ!
「はっ・・・うぅぅン!! いいっ!・・・気持ちいいっ!!」
一也くんに下着を差し出すと決めてからずっと・・・
私は、心の奥底で淫らな欲望を閉じ込めていたのかもしれない。
下着以上の行為を、彼から求められた時の対応を何度も頭の中で巡らせてるうちに
きっと・・・その萌芽は芽吹いてしまっていたんだわ。
「そう、誰も知らないんだわ・・・」
心がザワザワと音を立て始める・・・。
「知らないから・・・誰も求めないんだわ。
でも、もし知ってしまったら・・・秘密を知ってしまったら」
胸が苦しくなる・・・身体が、理性が強く拒絶していよう。
「うら若い女教師が下着を身に着けていないと知ったら・・・。
スカートの奥で、女性器を無防備に曝していると知ってしまったら」
分かってる・・・分かっているわ。
簡単に言い訳の出来る行為じゃない事は十分分かってる。
脅迫されたわけじゃない、淫らに発情しているんじゃない
なのにっ、こんな・・・こんな事を望むなんて、どうかしてる!
「そうよ、どうかしてるのっ・・・先生は・・・」
グラウンドで他の部員達と黙々とランニングを続けてる宇佐美くんに
私は熱い視線を送りながら、つぶやいた。
「分からないのなら・・・先生の気持ち分かってくれないのならっ。
これなら、どう??・・・分かってくれるでしょう?
ねぇ・・・宇佐美くんっ!!」
それは、下着を脱ぐよりも遥かに簡単な動作だった。
だけど、覚悟も羞恥も遥かに下着より勝る行為だったの。
サイドの二つのホックとファスナーを外し
明るい水色の布地が力なく足元に落ちていった瞬間・・・。
私は、こみ上げる熱い固まりのような感情に声を詰まらせて
立ちくらんでしまう!
「ぁぁ・・・はぁぁぁ・・・っン、はふぅぅっ・・・・!!」
何もしていないのに、されてもいないのに
官能の色をたたえた熱いため息を吐き出しながら
私は軽い絶頂感に飲み込まれていたの。
窓のサッシにしがみ付かないと、その場に崩れ落ちそうになる・・・。
一瞬、止まったように感じた心臓から、再び鼓動が伝わってくる・・・。
全身が汗びっしょりになって、ブラウスの生地が肌に張りついて気持ち悪い・・・。
ひどい生理のように、子宮が膣からズリ落ちて来る感じがする・・・。
そして・・・ぁあっ、失禁したみたいに、アソコから発情の証が滴り落ちてるのっ。
「なんて、はしたないの・・・教室で、こんなに、教師が、アソコを濡らして
イってしまうなんてっ。オマ○コ曝して果ててしまうなんて・・・っ!」
窓ガラスに頬を強く押し付けながら、視線はグラウンドの彼に注がれる。
「軽蔑・・・するよね? 先生がこんな女だって知ったら君だって・・・」
自戒の言葉を口にしながらも、貪欲過ぎる私の中の情欲が
無意識に太股を擦り合わせ、刺激を受けた女性器が熱く昂ぶっていく!
「でも、これが先生なのっ・・・淫らな期待を膨らませて
それが叶わなければ、こんな格好で・・・わざと刺激を求めて
性欲を満たそうとする、破廉恥ではしたない・・・淫乱な教師なのっ」
小さな絶頂感と共に溢れ出したのとは別の新しい愛液が
性器から溢れ出てくるのを感じて、私は声に出して自分を責めた。
「だから・・・っ、思い切り軽蔑していいのっ。軽蔑した目で見つめて!
そして・・・先生を・・・もっと・・・感じさせてっ!
ぁぁあ・・・っ、宇佐美くんっ。先生っ・・・先生、もうたまらないわ!!」
そんなはずはない・・・ここから声なんて届くはずないのに
ランニングを終えた彼が、不意に顔を上げて
校舎を・・・教室の窓に持たれかかる私を見つめてくれたの!
周囲を覗いながら、そっと私に手で合図する彼・・・。
それだけで十分だった。
最後に残った理性のカケラが弾けて、私は股間に指を這わせるっ!
「はっ・・・うぅぅン!! いいっ!・・・気持ちいいっ!!」
一也くんに下着を差し出すと決めてからずっと・・・
私は、心の奥底で淫らな欲望を閉じ込めていたのかもしれない。
下着以上の行為を、彼から求められた時の対応を何度も頭の中で巡らせてるうちに
きっと・・・その萌芽は芽吹いてしまっていたんだわ。
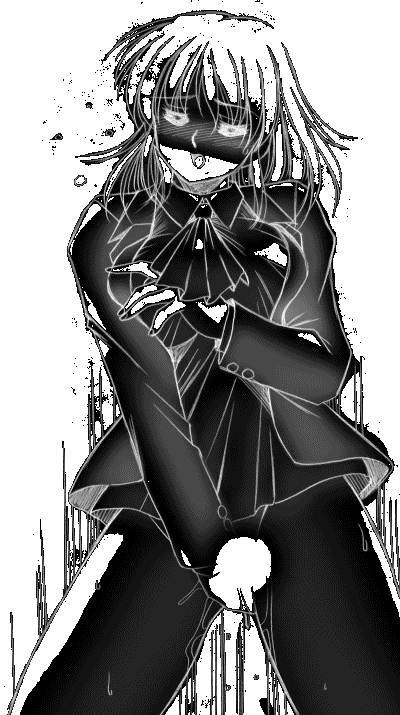 自虐の悦びに溺れる・・・マゾヒスティックな性癖・・・。
こんな自分だから、一也くんを責める資格なんかないから
彼の性癖も許してあげられたのかもしれない。
例え度重なる恥辱に抗えずに植え付けられたものだとしても
拭い去る事が出来ないのなら、一也くんと同じ。
女教師の汚れた下着の匂いを嗅ぎながら耽るオナニーと
生徒の視線を感じながら剥き出しの淫部を弄るオナニー・・・。
誰もが軽蔑の眼差しを向ける、淫靡でアブノーマルな性癖!
「いやぁ・・・ぁン、指が・・・っ、指が弄ってるのぉ。
先生のオマ○コ、イヤらしく弄ってるのよっ」
一也くんと私が同じなら・・・そうなの?
私自身も許してもらいたいの??
認めて欲しいから、こんな身の破滅を誘っても
おかしくない行為に耽って、一也くんが心で葛藤しながらも
私に利尿剤を飲ませたように、淫らな性癖に気付いて
愛してくれる誰かを・・・私、求めているの?!
「こんなに濡れてるのっ!
こんなにグチュグチュ濡らしてるっ・・・。
あぁっ、聞こえる?? 宇佐美くんっ!
先生のイヤらしい音・・・聞こえるんでしょう!?」
校舎を見上げながら、応答を待ち続けてる彼に
私はガラス越しにそう叫んでたの。
「聞いてっ・・・先生の側に来て、この音を聞いてっ!
そしてっ・・・先生のこと、軽蔑してっ!!
こんな先生をっ・・・はしたない先生をっ・・・蔑んで構わないわ!」
「そしてっ・・・そして、愛してちょうだい!
昂ぶったオチ○チンで先生を貫いてっ!!
たぎった精液をオマ○コに注いで先生を汚してっ!!}
「先生は・・・紀子は・・・ぁあっ、マゾっ・・・マゾだからっ!!」
激しい絶頂感が襲ってくると同時に
私は力なく膝から床に崩れ落ちていった・・・。
両膝を開いて正座するお尻に冷たい床の感触が心地良く感じて
無意識に腰を揺すってしまう。
「ぁぁっ・・・宇佐美くん・・・見てくれてた??
先生がイクの・・・ちゃんと見てた?」
あんなに絶頂を感じたのに、私の情欲は貪欲に新たな刺激を求め始める。
「冷たいの・・・お尻が・・・ぁあっ、また感じて来ちゃうぅ・・・。
先生、お尻でも・・・感じてしまう女なのよ・・・っ」
でも、その時だったの・・・その音に気付いたのは。
身体は窓の下にもたれ掛かって、視界の先は壁だったけれど
その音は・・・喘ぐ私の息遣いだけが響く教室に、微かに私の耳に届いたの。
「だ・・・誰、なの?? 一也くん?・・・それとも誠くん??
ねぇ、応えて・・・どうして教室の鍵、持っているの??」
振り向けば、鍵を開けようとしてる相手の正体が分かるかもしれない。
でも私は、鍵が開けられ扉が軋む音を聞いても振り返る事が出来なかったの。
足音が静かに近づいてくる・・・。
手を伸ばせば床に落ちたスカートを手繰り寄せて
剥き出しの下半身を覆うくらいの事は出来るのに
それさえ、真実を確信して身がすくんだ私には思い付かない。
教室の前の扉は一也くんが開けたままだった・・・。
職員室にある教室の鍵は、今私が持ってる・・・。
わざわざスペアの鍵で後ろの扉を開けられるのは・・・!?
靴音がすぐ背後で止まっても、振り向く勇気は私にはなかった。
「田辺先生・・・まだ満足なさっていないみたいですね?」
その冷たい・・・丁寧な口調の奥に、冷たい感情を秘めた声に
私は声を詰まらせ、身を縮ませるっ!
本能的に身体を丸め、その厄災が通り過ぎるのを待とうとした。
でも冷酷な現実は、私を更なる辱めを与えようとしていたの。
「えっ・・・?? く、国崎さん・・・何をっ??」
犯されてもおかしくない状況で、身体に指一本触れないで
去っていく足音に不安になった私が意を決して振り返ると
彼は教室を後にしようとしていた。
「お一人で、おもしろい事をなさっていましたから
私もその遊びに混ぜていただこうと思いましてね」
冷たい笑みを浮かべて、校務員の彼は教室を出ていってしまう。
「まっ、待って下さい国崎さんっ!!
そんなっ・・・私っ・・・無理ですっ!!」
涙声で訴える私を一人残して
彼の大柄なシルエットが教室のすりガラスの向こうに消えていった・・・。
そう・・・手には、替えの下着が入ったポーチと拾い上げたスカートを持ったまま・・・・。
自虐の悦びに溺れる・・・マゾヒスティックな性癖・・・。
こんな自分だから、一也くんを責める資格なんかないから
彼の性癖も許してあげられたのかもしれない。
例え度重なる恥辱に抗えずに植え付けられたものだとしても
拭い去る事が出来ないのなら、一也くんと同じ。
女教師の汚れた下着の匂いを嗅ぎながら耽るオナニーと
生徒の視線を感じながら剥き出しの淫部を弄るオナニー・・・。
誰もが軽蔑の眼差しを向ける、淫靡でアブノーマルな性癖!
「いやぁ・・・ぁン、指が・・・っ、指が弄ってるのぉ。
先生のオマ○コ、イヤらしく弄ってるのよっ」
一也くんと私が同じなら・・・そうなの?
私自身も許してもらいたいの??
認めて欲しいから、こんな身の破滅を誘っても
おかしくない行為に耽って、一也くんが心で葛藤しながらも
私に利尿剤を飲ませたように、淫らな性癖に気付いて
愛してくれる誰かを・・・私、求めているの?!
「こんなに濡れてるのっ!
こんなにグチュグチュ濡らしてるっ・・・。
あぁっ、聞こえる?? 宇佐美くんっ!
先生のイヤらしい音・・・聞こえるんでしょう!?」
校舎を見上げながら、応答を待ち続けてる彼に
私はガラス越しにそう叫んでたの。
「聞いてっ・・・先生の側に来て、この音を聞いてっ!
そしてっ・・・先生のこと、軽蔑してっ!!
こんな先生をっ・・・はしたない先生をっ・・・蔑んで構わないわ!」
「そしてっ・・・そして、愛してちょうだい!
昂ぶったオチ○チンで先生を貫いてっ!!
たぎった精液をオマ○コに注いで先生を汚してっ!!}
「先生は・・・紀子は・・・ぁあっ、マゾっ・・・マゾだからっ!!」
激しい絶頂感が襲ってくると同時に
私は力なく膝から床に崩れ落ちていった・・・。
両膝を開いて正座するお尻に冷たい床の感触が心地良く感じて
無意識に腰を揺すってしまう。
「ぁぁっ・・・宇佐美くん・・・見てくれてた??
先生がイクの・・・ちゃんと見てた?」
あんなに絶頂を感じたのに、私の情欲は貪欲に新たな刺激を求め始める。
「冷たいの・・・お尻が・・・ぁあっ、また感じて来ちゃうぅ・・・。
先生、お尻でも・・・感じてしまう女なのよ・・・っ」
でも、その時だったの・・・その音に気付いたのは。
身体は窓の下にもたれ掛かって、視界の先は壁だったけれど
その音は・・・喘ぐ私の息遣いだけが響く教室に、微かに私の耳に届いたの。
「だ・・・誰、なの?? 一也くん?・・・それとも誠くん??
ねぇ、応えて・・・どうして教室の鍵、持っているの??」
振り向けば、鍵を開けようとしてる相手の正体が分かるかもしれない。
でも私は、鍵が開けられ扉が軋む音を聞いても振り返る事が出来なかったの。
足音が静かに近づいてくる・・・。
手を伸ばせば床に落ちたスカートを手繰り寄せて
剥き出しの下半身を覆うくらいの事は出来るのに
それさえ、真実を確信して身がすくんだ私には思い付かない。
教室の前の扉は一也くんが開けたままだった・・・。
職員室にある教室の鍵は、今私が持ってる・・・。
わざわざスペアの鍵で後ろの扉を開けられるのは・・・!?
靴音がすぐ背後で止まっても、振り向く勇気は私にはなかった。
「田辺先生・・・まだ満足なさっていないみたいですね?」
その冷たい・・・丁寧な口調の奥に、冷たい感情を秘めた声に
私は声を詰まらせ、身を縮ませるっ!
本能的に身体を丸め、その厄災が通り過ぎるのを待とうとした。
でも冷酷な現実は、私を更なる辱めを与えようとしていたの。
「えっ・・・?? く、国崎さん・・・何をっ??」
犯されてもおかしくない状況で、身体に指一本触れないで
去っていく足音に不安になった私が意を決して振り返ると
彼は教室を後にしようとしていた。
「お一人で、おもしろい事をなさっていましたから
私もその遊びに混ぜていただこうと思いましてね」
冷たい笑みを浮かべて、校務員の彼は教室を出ていってしまう。
「まっ、待って下さい国崎さんっ!!
そんなっ・・・私っ・・・無理ですっ!!」
涙声で訴える私を一人残して
彼の大柄なシルエットが教室のすりガラスの向こうに消えていった・・・。
そう・・・手には、替えの下着が入ったポーチと拾い上げたスカートを持ったまま・・・・。