大気汚染と低出生体重児及び早産との関係
2000年2月21日
CSN #123
内分泌攪乱化学物質、たばこの煙[1]、大気や室内の空気汚染など、環境汚染化学物質がヒトの生殖系に影響を与えているのではないかと心配されています。1950年代以降の産業の発達とともに、精子数の減少[2]、乳癌の増加[3]などが示されていますが、その原因については、ほとんど明らかになっていません。子供の出生に対する影響も心配されており、日本では表1、2に示すように、出生児体重2,500g以下(未熟児)の比率が年々増加し、出生児体重の平均値が年々減少しています[4]。
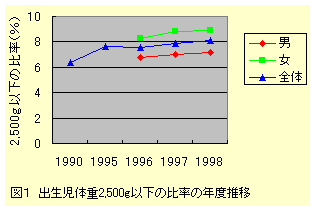 |
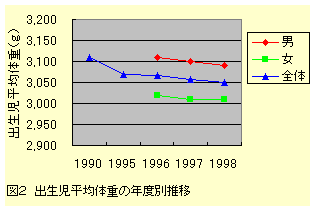 |
2000年2月号のアメリカ環境科学雑誌「環境衛生展望」において、英国ロンドン大学 疫学公衆衛生部 健康社会国際センターのMartin Bobakらが、大気汚染物質である二酸化硫黄(SO2)、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)と、子供の出生への影響との関連性について調査した結果を発表しました[5]。
Martin Bobakらは、英国の67の地区で、1990年-1991年に監視された大気汚染物質である、二酸化硫黄(SO2)、浮遊粒子状物質(SPM:直径が10μm以下の微粒子)、窒素酸化物(NOx)のそれぞれの大気中濃度と、その地区において1991年に出生が登録された、全ての出生児(108,173人)のデータを解析しました。母親が妊娠初期3ヶ月間に曝露した大気汚染物質濃度を、その地域の監視装置で測定された、日々の大気汚染物質濃度を単純平均化することによって求め、低出生体重児( 2,500 g以下、未熟児)、早産(37週以前に出生)、子宮内成長遅延(IUGR)のオッズ比を回帰分析から求めました。表1に妊娠初期3ヶ月間における各汚染物質への曝露濃度を示します[5]。
表1 妊娠初期3ヶ月間における各汚染物質への曝露濃度([5]をもとに作成)
|
化学物質 |
3ヶ月間の平均曝露量(μg/m3) |
||
|
低値25% |
中央値 |
高値75% |
|
|
SO2 |
18 |
32 |
56 |
|
SPM |
55 |
72 |
87 |
|
NOx |
23 |
38 |
59 |
*低値25%は、全体の濃度分布の低い方25%の濃度を平均化した数値。高値75%も同様に平均化した数値を示す。
そして、低出生体重児、早産、IUGRとの関連性を解析した結果、低出生体重児(有症率5.2%)と早産(有症率4.8%)が、二酸化硫黄(SO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)と関連性があることが示されました。しかしIUGRは、どの汚染物質においても関連性が示されませんでした。妊娠初期3ヶ月間の二酸化硫黄(SO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)への曝露と、低出生体重児と早産への影響について、表2に示します[5]。
表2 SO2及びSPMへの曝露と出生への影響([5]をもとに作成)
|
出生影響 |
SO2(曝露量: 50 μg/m3) |
SPM (曝露量: 50 μg/m3) |
||
|
オッズ比 |
95%信頼間隔(CI) |
オッズ比 |
95%信頼間隔(CI) |
|
|
低出生体重児 |
1.20 |
1.11-1.30 |
1.15 |
1.07-1.24 |
|
早産 |
1.27 |
1.16-1.39 |
1.18 |
1.05-1.31 |
*CI:95%信頼間隔
表2から明らかなように、50 μg/m3濃度レベルの二酸化硫黄(SO2)や浮遊粒子状物質(SPM)への曝露によって、低出生体重児や早産児が15%- 27%増加していることがわかります。
日本は、戦後の高度な工業化社会の発展とともに、産業活動や消費活動によって、様々な化学物質を大気中に排出しました。そのため大気汚染が深刻化し、公害問題へと発展しました。日本では、環境基本法第16条第1項による大気汚染にかかる環境上の条件につき、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として、二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO2)、光化学オキシダントに環境基準が定められています。また、それらの化学物質は、大気汚染防止法に基づき、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市により、全国 2,138の測定局(平成10年度末現在、一般環境大気測定局(以下、一般局):1,724局及び自動車排出ガス測定局(以下、自排局):414局)において、大気汚染濃度を常時監視しています。これらの中から、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)に関しては、表3の環境基準値が定められています。
表3 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素の日本における環境基準値
|
化学物質 |
環境基準値 |
|
二酸化硫黄(SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48. 5.16告示) |
|
浮遊粒子状物質(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) |
|
二酸化窒素(NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) |
また日本における、これら大気汚染監視物質の年平均値は最近10年間あまり変化しておらず、環境基準達成率は図3、4に示す通りであり、二酸化硫黄(SO2)を除いては環境基準値を達成しておりません。また、それぞれ汚染源や汚染濃度レベルは、表5のようになっています[6][7]。
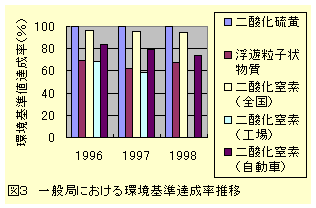 |
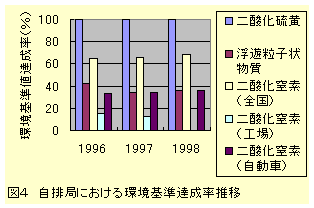 |
表4 大気汚染物質の汚染源と汚染濃度レベル([6][7]をもとに作成)
|
汚染物質 |
汚染源 |
汚染濃度レベル |
|
二酸化窒素 |
一酸化窒素(NO)・二酸化窒素(NO2)等の窒素酸化物(NOX)は、石油、石炭などの化石燃料の燃焼に伴って発生し、発生源としては、工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源がある。 |
年平均濃度では、首都圏特定地域や大阪・兵庫圏特定地域、一般局で0.025-0.027ppm、自排局で0.036-0.040-ppmとなっている。また、年平均濃度が0.03ppmを越える地域は、東京都・神奈川県の都市部、大阪府・兵庫県の都市部に集中している。 |
|
二酸化硫黄 |
硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じる。 |
SO2濃度の年平均値は、昭和40、50年代に比べ著しく減少している。 一般局:0.004ppm(1998年) |
|
浮遊粒子状物質(SPM) |
浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物(SOX)・窒素酸化物(NOX)等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子がある。一次粒子の発生源には、工場等から排出されるばいじんや、ディーゼル車の排出ガスに含まれるディーゼル排気微粒子(DEP)等の人為的発生源と、土壌の巻き上げ等の自然発生源がある。 |
浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、近年ほぼ横ばいが続いている。 一般局:約30μg/m3(1998年) |
次に、表4に示される日本の汚染濃度レベルと、表2に示される英国で出生に影響が示された、二酸化硫黄(SO2)、浮遊粒子状物質(SPM)の濃度とを比較した結果を表5に示します。
表5 日本の汚染レベルと英国で出生への影響が示された濃度との対比
|
汚染物質 |
環境基準値 |
汚染濃度レベル(1998年) |
英国で影響が示された濃度 |
|
二酸化硫黄 |
0.04ppm以下 |
一般局全国:0.004ppm |
0.0188ppm* |
|
浮遊粒子状物質(SPM) |
100μg /m3以下 |
一般局全国:約30μg /m3 関東、中部、近畿、瀬戸内、九州西部で環境基準値(100µg /m3)達成率が低い[7]。 |
50 μg/m3 |
*二酸化硫黄50 µg/m3を20度1気圧で体積濃度に換算
表5から明らかなように、二酸化硫黄については、英国で出生への影響が示された濃度よりも低いが、浮遊粒子状物質(SPM)については、自排局全国平均値において、英国で出生への影響が示された濃度に近い値となっています。また地域性を考慮すると、関東、中部、近畿、瀬戸内、九州西部において環境基準値を満足していない、つまり英国で出世への影響が示された濃度よりも2倍以上の濃度の地域が多いことがわかります。このことは、国内で交通網が発達している地域では浮遊粒子状物質(SPM)濃度が高く、英国で出生への影響が示された濃度を越えた地域が多く含まれることを示唆しています。これらのことから想定すると、日本において交通網が発達した地域では、浮遊粒子状物質(SPM)による出生への影響が生じている可能性が心配されます。
兵庫県の尼崎公害訴訟では、神戸地方裁判所が2000年1月31日に、国や阪神道路公団に対し、浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止め命じる判決を下しました[8]。その内容は、国道43号の沿道50mにおいて、一日平均値150μg /m3(環境基準値100μg /m3)を越える浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを命ずるもので、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも、ディーゼル排気微粒子(DBP)による気管支喘息などの呼吸器系疾患に関わる健康被害の可能性を指摘しました。
しかし、浮遊粒子状物質の健康影響問題は、気管支喘息などの呼吸器系疾患だけではありません。浮遊粒子状物質の中には、ベンゾ(a)ピレンなどの内分泌攪乱作用の疑いがある化学物質が含まれています。また、東京理科大学の武田教授らの研究グループは、ディーゼル排気ガスによって、雄マウスの精子産生能が低下することを示す研究結果を、1999年に発表しました[9]。そして今回、Martin Bobak らの研究によって、浮遊粒子状物質(SPM)が、低出生体重児(未熟児)や早産の増加といった、ヒトの出生に対して影響している可能性が示されました。
日本ではここ数年でさえも、低出生体重児(未熟児)や、早産が年々増加しています。大気汚染物質などの環境汚染因子との関連性について、今後のさらなる研究と、早急な抜本的対策が必要と思われます。
Author:東 賢一
<参考文献>
[1] 森山郁子, 周産期医学, Vol.29 , No. 4, p469- 473, April
1999
「嗜好品と周産期−タバコの影響」
住まいにおける化学物質CSN #119, 「妊婦の喫煙と出生児への健康影響」
http://www.kcn.ne.jp/~azuma/news/Janu2000/000124.htm
[2] Shanna H. Swan et al., Environmental
Health Perspectives, Volume 105, Number 11,
November 1997
http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/1997/105-11/swan.html
[3] 松崎早苗, 山崎みどり, 日本内分泌攪乱化学物質学会 第二回 研究発表会
要旨集, p237, December 1999
“乳癌死亡の長期増加傾向と環境因子の研究戦略”
[4] 厚生省大臣官房統計情報部
http://www.mhw.go.jp/toukei/toukeihp/index.html
[5] Martin Bobak, Environmental Health Perspectives, Volume
108, Number
2, p173-176, February 2000
http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/2000/108p173-176bobak/abstract.html
“Outdoor Air Pollution, Low Birth Weight,
and Prematurity”
[6] 平成11年度環境白書
http://www.eic.or.jp/eanet/hakusyo/1999/mokuji.htm
[7] 「平成10年度大気汚染状況について」環境庁大気保全局, October 18, 1999
http://www.eic.or.jp/kisha/199910/66125.html
[8] 朝日新聞(夕刊), January 31, 2000
[9] 武田 健、吉田成一、Endocrine
Disrupter News Letter, Vol.2 No.2, Sept 1999
"ディーゼル排気ガスの生殖機能への影響と内分泌攪乱作用"
住まいにおける化学物質, CSN #101, 「ディーゼル排気ガスによる内分泌攪乱作用と精子生産能力低下」
http://www.kcn.ne.jp/~azuma/news/Oct1999/991007.html