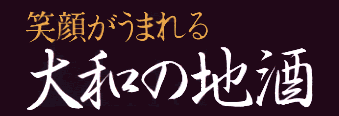
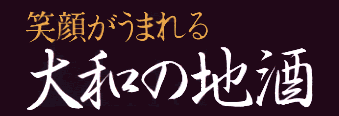
大和は国のまほろば古代より政治経済、文化の中心的役割を果たしてきた奈良県は
日本酒の分野でも、その歴史、技術両面で清酒産業の最も重要な働きとその地位を
保ってきました。
醸造の特殊用語の「菩提元」等、奈良県ゆかりの社寺の名前が今なお残り、古語辞
典による「大和酒」「奈良両白」など高級酒産地であったことが伺い知れます。
奈良県の社寺の中でも、酒との縁が最も深いのが桜井市にある三輪神社です。
ご神体は大和三山のひとつである三輪山で、古来三諸山、三室山などとも呼ばれ
「みもろ」すなわち「酒のもと」、酒の神様としての信仰からの呼び名であるとも
言われています。
毎年11月、杉の舞が奉納され、杉の葉を球状に束ねた「杉玉」
「酒ばやし」が作られ、これを奈良県下の酒造家に賜ります。この「杉玉」は、古
酒屋さんの軒に商標としてかける習慣があります。この他にもお酒にゆかりの地も
多く、奈良市の春日大社には酒蔵があり今もここで神社酒として造られています。
酒は神にお供えするもの等として社寺にて造られ貴族、上流階級にしか飲まれなか
ったものです。
また、明日香村には「酒船石」という巨石があり、これは長さ5.3メートル、
最大幅2.27メートルの花崗岩に丸いくぼみや溝を刻んだ石で、酒の
醸造に使われたのではないかという説もあります。
日本酒の種類と特徴
| 吟醸酒 |
|
米、米麹、醸造アルコールを原料に、精米歩合60%以下で仕上げた日本酒の芸術品。 10度位に冷やして飲めば、独特のフルーティな風味がひろがります。 |
| 純米吟醸酒 |
|
純米で吟醸造りという日本酒の逸品。 色沢がよく、すっきりとした飲み心地とともに、 独特のよい香りが口一杯にひろがります。個性的な日本酒の逸品です。 |
| 大吟醸酒 |
|
米、米麹、醸造アルコールを原料に、精米歩合50%以下、 つまり米の半分以上を削って贅沢に仕上げたお酒です。 |
| 純米酒 |
|
米、米麹を原料に、精米歩合60%以下。または特別な造り方の違いは、 ラベル等に表示されています。 |
| 特別純米酒 |
|
米、米麹を原料に、精米歩合60%以下。または特別な造り方の違いは、 ラベル等に表示されています。純米酒でもさらにうまい酒といえます。 |
| 本醸造酒 |
|
17世紀に「よりおいしいお酒を」という願いのもとに開発された醸造法。 米、米麹に少量の醸造アルコールのブレンドが、 日本酒本来のうまさを引きだします。精米歩合は70%以下。 |
| 純米大吟醸酒 |
|
米、米麹のみを原料に、精米歩合50%以下という吟醸造りで仕上げた 日本酒の逸品。固有の香味、色沢が特に良好で、 冷やして飲むことで魅力も倍増します。 |
| 特別本醸造酒 |
|
米、米麹、醸造アルコールを原料に、本醸造酒よりもさらに米を磨いて 精米歩合60%以下、または特別な製造方法で造られます。 味の個性によって、冷やで、そして燗で。 |