拾遺集(33) Aus meinem Papierkorb, Nr. 33
白兎 Der weiße Hase
『白兎 (シロウサギ)』はフリードリヒ・ゲオルク・ユンガー Friedrich Georg Jünger (1898-1977) の第二短篇集、「クジャクとそのほかの物語」(Die Pfauen und andere Erzählungen, 1952) に収められた作品である。同じ集の『とさか』(Hahnenkamm) と並んでこれは犯罪小説めいた短篇である。『とさか』の連続殺人は異常心理が不気味さを呼び起こすが、『白兎』は謎が提示され、ストーリーが進む中でさらに謎が重なり、そして死体の発見へと至る。こちらも不気味な雰囲気が漂う作品だが、サスペンスもあってミステリー(推理小説)とも言える。味わいの異なる作品だ。物語は「私」の曽祖父の身辺で起きた事件として語られる。時代は一八一四年のことと、ユンガーの小説には珍しく西暦年が明示されている。ヨーロッパを征服した皇帝ナポレオンの治世末期、ロシア遠征に失敗し、ヨーロッパ諸国の「解放戦争」が勃発、対仏同盟軍の攻勢が強まり、パリ陥落、フォンテーヌブロー条約締結、エルバ島へ追放となった年が一八一四年である。
私の曾祖父は、かなりの高齢まで生きたが、一種独特の猟師だった。春にも夏と秋にも猟をせず、冬だけ、それも厳冬の雪の積もった明るい月夜にだけ猟をするのだった。猟と言っても、狩着も身に着けず、口笛で犬に指図することもせず、雪に埋もれた野や森を歩き回ることもなかった。部屋の中で、毛皮の裏のついた部屋着を羽織って、高い背もたれのついたひじ掛け椅子を窓際に寄せて座り、そして静かな月の夜を眺める。横には猟銃が窓枠に立て掛けてあった。傍らの小テーブルには小さなアルコールコンロの上にポットが置いてあり、それとグラスが一つあって、ときおりポットで温めたグリューワインを注いでいた。 (S.244)「独特の猟師」だったとされるが、曾祖父は猟で生計を立てていたのではなく、あくまでも愉しみの範囲だった。また「鳥なしでは生きていけなかった」というほどの鳥好きで、ウソ Dompfaff を雛から育てて口笛で歌を仕込むことに打ち込んでいて、こちらの方がもっと大きな愉しみだったようだ。では本業はなにか、それについて作中で説明されることはない。家と畑を所有しているようだから、農家なのか、それとも別の収入源があるのか。家には妻と女中がいる。ただし、妻は事件の起きたときには病を得た身内の見舞いに出向いて家を空けていた。
冬の明るい月夜に、ゆったりと部屋の窓から狙う獲物は何か。それはウサギだ。ウサギ狩りは大昔から狩猟の一つのジャンルで、野山に大勢の勢子や犬を動員して大掛かりに行われることも多かった。だが曾祖父の場合、狙うのは自家のキャベツ畑に現れるウサギである。「厳しく凍えると食べごろとなるチリメンキャベツ(*)のある」畑である。その畑を見渡せる部屋の窓辺で待機している。
月の夜、積もった雪が硬く凍て付き、歩けばギシギシ音を立て、材木はポキンパキンと割れる、そういう月夜にウサギが村に入ってきて、若い果樹をかじり、キャベツをカリカリ食べる。ウサギは雪の上を影のように走る。ためらうように、おずおずと小さく跳び、耳を鋭く高く伸ばし、そして新たなジャンプに備える。ウサギ以上に危険に脅かされて生きているものがいるだろうか。野にいるどの動物がウサギ以上にやすやすと他者の胃の中を棺桶と墓にしてしまうだろうか。それでも甚だしい空腹に駆り立てられ、四方八方から作物の無い野原を出て村へと跳びはねてくる。音もなく近づいてきた。曾祖父のキャベツ畑は村のはずれにあって、ウサギを強烈に引き寄せた。 (S.245)ウサギは草食で、森や林に多くの食べ物があるが、冬になると餌が乏しくなる。そのため人里の畑にまで出現する。自分の部屋でグリューワインを飲みながら、それを狙うのが「独特の猟師」たる曽祖父であった。ある冬の一夜、いつものように明かりを消した部屋の窓から外を窺っていると、畑に真っ白なウサギが見えた。曽祖父が経験する最も奇怪な出来事はこうして始まった。
一番奇妙だった冬の夜はおそらく -- 一八一四年のこと -- あのシロウサギを見たときに過ごした夜だろう。そのときも狩のために部屋に座って外を見ていた。雪が降り積もり、その夜は氷のように冷たく、星はきらめき、月が明るく輝き、ウサギは四方八方から村へ接近してきた。雪の上を影がさっと走り、場所を変え、だんだんとキャベツ畑に忍び寄ってきた。曽祖父は鋭い視線で外を窺い、さらに鋭く目を凝らして見てはっと目をこすった。というのは何か妙なものが見えたからだ。冬には黒い耳の先を除いて白くなる雪ウサギがアルプスや北方にはいる;ニーダーザクセンの農地ではそういうウサギは見かけない。だがいまそこにいるのは白い雪の上でほとんど見えないやつだ、チリメンキャベツの黒っぽい芯の間で動く時だけ、見えるようになるが、これはシロウサギ以外であり得なかった。最初、曽祖父はそれが信じられず、注意深く近づいてくる動物をイタチかネコかラビットかと思ったが、キャベツ球の横で立ち上がってかじり始めると、これは間違いなくウサギだとわかった。あれはきっと赤い目のアルビノだ、目の色は月明かりでは判別できないが。シロウサギが二本脚で立って凍ったキャベツをかじっているのは奇妙な眺めだった。 (S.248)真っ白なウサギは普通はいない。ウサギには家ウサギ(飼いウサギ)と野ウサギがあって、日本語では両方ともウサギと呼ばれるが、ドイツ語では Kaninchen と Hase (女性形は Häsin 縮小形は Häschen / Häslein)とに呼び方が別れている。英語の rabbit と hare に相当する。


[付記1]曽祖父は真っ白な野ウサギなぞ普通ではないので、赤い目のアルビノ(***)だろうと想像した。この反応から伺えるのは、これまでもシロウサギについて稀には見たか聞いたことはあるのだろう。また、昔から夜に現れる白い動物には不気味な印象があって、漁師はぎょっとする。それで白いシカや白いノロジカには銃を発砲しない、白い動物を射止めると不幸をもたらす前兆だと、そういう縁起を担ぐ猟師はいつもいたと説明される。
ノウサギの分類名は日本語・学名で「ヤブノウサギ Lepus europaeus」という。ウィキペディアで「ヤブノウサギ」を見ると、毛の色についてこうある。
背中の毛皮は長い巻き毛で白黒の毛が混じった黄色がかった茶色である。肩や脚、首、のどは赤褐色である。腹側は白色で、尻尾と耳の先端も白色である。冬に完全な白色にはならない。しかし、頭部は白色になりやすく、尾部は灰色になることもある。
- - - - - - - - - -
冬毛の色については、ウィキペディア英語版、ドイツ語版のほうが少し詳しい。
[en] The European hare's fur does not turn completely white in the winter as is the case with some other members of the genus, although the sides of the head and base of the ears do develop white areas and the hip and rump region may gain some grey.
[de] Im Winterfell sind die Kopfseiten einschließlich der Ohrbasis weißer und die Hüften mehr grau.
ヨーロッパ・ウサギは他の種と違って冬に毛が完全に白くなることはない。側頭部と耳の付け根に白い部分が広がり、腰から尻にかけてグレーになることはあるが、ということ。
[付記2]
我々も「因幡の白兎」の話で《シロウサギ》には子供の時から馴染んでいる。この神話の出典(古事記)では「稻羽之素菟」とあり、「白兎」として伝わる表現は、ワニに皮をむかれて「素菟」になったところから由来するらしい。
「日本では飼いウサギは近世末から起こったもので,古くはすべて野生のものであった。このうち西日本のものは年間を通じ黄褐色の毛であるが,東日本のエチゴウサギは冬季白化する。このため西南日本では白いウサギを珍しがり神秘なものとして山の神の仮の姿と考えた痕跡も認められる」(『世界大百科事典』、「ウサギ」の項目、千葉徳爾)
明治時代に「因幡の白兎」がヨーロッパに紹介されたときのタイトルは『THE HARE OF INABA』(Mrs. T. H. James)で、兎は hare と訳されている。
しかし私の曽祖父は迷信深くなく、シロウサギとわかって、すぐさま仕留めて剥製にしようと決めた。このような珍しい獲物を見逃すことはできなかった。彼は静かに銃を撃つのに使う小窓を開け、そして同じくそっと銃身を差し入れた。だがそうして準備を終え獲物を窺おうとすると、チリメンキャベツのシロウサギは姿を消していた。どうしたのだ、ウサギはすぐまた姿を現すであろう。彼は銃を構えたまま、鋭く畑を見渡した。と、シロウサギは一跳びでキャベツを離れ、同時に二匹の黒い仲間も跳んだ。ウサギたちは広い野へ走って銀色の荒野へ消えていった。 (S.249)しくじったかと、と曽祖父は腹を立て、また驚きもした。ウサギたちに何が起きたのだ? 銃を引き入れ、小窓から外を見た。
雪が軋り、足音が近づいてきて、人影が一つ、納屋の方からそろそろと近づいてきて、姿が明瞭になり、彼が座っている窓にやってきた。こんな夜遅くにまだ人が歩いていることに驚いたが、静かに座ったまま、これはいったいどうなるのだ、と待ち構えた。やって来たのは一人の男だとわかった。長いブーツをはき、ジャンパーを着て、その斜めポケットに手を突っ込み、頭には、ここらでは誰もかぶらないような丸い帽子を被り、一まとめにくくった荷物を、ロープで肩から下げていた。窓のすぐそばまで来て中を覗き込んだ。ふたりの男は黙ってじっと見つめ合い、そしてやってきた男が言った:「相変わらずウサギ狩りかい、ヨーハン?」 (S.249f.)その「痩せて頬がこけた無精ひげの顔」が誰か最初は分からなかったが、見知らぬと思えたものが、覚えのあるものになり、親しい顔となった。曽祖父(ファーストネームがヨーハンだと分かる)は、大声を挙げるというのではなく、囁くように言った:「お前だったのか、コンラート?」窓から覗き込んでいるのは、二年以上前にロシアへ出征したコンラート・メーヴェスだった。中へ入るよう言ったが、「俺の農場はどうなってる?」と尋ねて、変わらないよとの答えを聞くと、「昔のままなのがあるのはいい。ここで会えてうれしいよ」 こう言うと雪の中を去って行った。そのとき教会の鐘が十二時を打った。離れてゆく者の背に向かって曽祖父は「明日の朝、またな、コンラート」と声をかけた。
翌朝、朝食の後、すぐにマントを羽織り、畑の道を通ってメーヴェスホーフ(****)へ向かった。それはすぐ近くで、三百歩を越えない距離だった。
空気は積雪時にしかない清浄さだった。雪混じりの空気は真珠のように粒立ち泡立っていた。間もなく農場は雪の舞う中に浮かび上がった。農場の前では下男が薪を割る音を立てていた。曽祖父は下男に会釈した。傍を通り過ぎるとき、ちょっと言葉をかけ、同時に割り木に目をやった。節のない良質のオーク材で、その薪になった大きな塊が周りに積んであった。もともとこの材木は薪に適していたのだ。二年以上会っていないコンラートとゆっくり話ができると思って、曽祖父は上機嫌で農場の建物に入った。どこもかしこもきちんと整頓されているのに感心しながら、調理場へ行くと、農婦が一人でかまどに向かって働いていた。「コンラートはまだベットの中かい?」と声をかけると、彼女は振り向いて彼を凝視した。「何のこと?」と彼女は小声で言った。「あんたのご亭主がまだベットの中かと訊いている」と言い足す。亭主がどうしてここにいるわけがありますか、という反応なので、昨夜の窓辺での出来事を事細かに語った。彼女は驚き信じられない表情で曽祖父を見て、首を振り、そして大声で「カール、こちらへおいで」と下男を呼んだ。下男は農場からゆっくりと入ってきた、まだ両手に斧を抱えたままだ。下男も考え深そうに真剣に、黙って話を聞いた、三人は、鍋はかまどの上で沸騰し、かまどで薪が弾ける調理場で立ち尽くしていた。
木を割って、また割って、他に何も無いかのようだと曽祖父は思い、下男の勤勉を褒めるように、もう一度頷いて農場に入って行った。 (S.252)
みなは突っ立ったまま、じっと顔を見合わせていた。曽祖父は考えに集中しようとした、そうしながら農婦の胸を見ていた、高く硬く盛り上がった胸が、青い麻の衣服の下で激しく上下していた。我々の熟考は往々にして筋を辿って進む方にはゆかず、目の前の鳥を追うキツネのようにやみくもに進んで筋を縺れさせる。我々は目にしていることを考える、曽祖父も同じだった、やはりそこにぼんやりと立って考えていた:コルセットを着けていないな。その必要も無いのか、と続けて考えた。[中略]曽祖父は途方に暮れる。農場を後にして、昨夜のことを思い返しつつ薪の積まれたところに差しかかったときには、あの男が窓辺に来たのは事実だ、と独り言をもらした。わずかな会話の一語一語を記憶にたどりながら、先へ進んだ。雪は相変わらず降り続き、夜間の痕跡はみな雪の下に埋まり覆われていた。小川の方に道をそれて川沿いを歩き、氷の上に上がった。氷上で跳び跳ねたが、ミシリとも軋まず、ひび割れを起こすこともなかった、水車の堰まで行くと、水車小屋から主が出てくるのが見え、言葉を交わした。前に立った雪まみれの男の狡猾そうな顔を注意深く観察しながら、天気や氷や雪、材木や粉にひく穀物について喋るのをじっと聞いた。だが自分が直面している問題に関しては何も話さなかった。そのあと、オーク材を伐り出す森へ向かって、材木が伐られた場所に目を注いだ。伐採した場所と切り屑は雪の下になっていたが、木の幹と枝は積み重なっていた。
おかしな話だ、と私の曽祖父は思った。頭のなかで車輪が回り始め、自分の正気を疑った。シロウサギが迫ってくる瞬間がよみがえった。目の前でシロウサギが後ろ脚で立つのを見えた。自分は夢遊病だったのか、シロウサギと亡霊がさまよう夢を見たのか? (S.253f.)
帰宅すると、コンラートの所属していた連隊から公文書が届いていた。
竜騎兵下士官コンラート・メーヴェス、第一騎兵中隊、旧ヴェストファーレン王国第二騎兵中隊、同人はロシア進撃において、スモレンスクの戦闘(一八一二年八月十二日)の後、行方不明、以降姿を見た者無かりしが、同連隊の蹄鉄工ヴィルムセンの陳述によればトゥーラの野戦病院にて一八一三年三月二十日に死亡した。メーヴェスは貴地を故郷とするゆえ、親族に丁重なる伝達を願う。連隊に故人の遺留物は無し。 (S.256)曽祖父はなおさら深い驚きに捕らえられた。驚きは余りに深刻で、しばらくはあらゆる思考が麻痺し停止した・・・この箇所で読者も同様に当惑する。十カ月以上も前に野戦病院で死亡? では、雪明りの窓辺での出会いは、あれは何だったのだ。あれはコンラートではなかったのか。あれはコンラートの亡霊だった?
推理小説を紹介する時の一般の慣わしに従って、我々もストーリーを辿るのはここまでにしよう。
物語の事件が起きた年について「一八一四年のこと」と明記されている。連隊から届いた文書でコンラートの死亡日時が「一八一三年三月二十日」とあり、それを「十カ月以上も前」のこととしているので、一八一四年の一月か二月の出来事となる。行方不明となった「スモレンスクの戦闘(一八一二年八月十二日)」はナポレオンのロシア遠征における最初の大規模な戦闘。
時代背景をうかがわせる描写がもう一カ所ある。曽祖父が、直面した出来事について考え尽して「この結論にゆくしかない」と思い定め、事件解決のために告訴を決意、馬ぞりで一時間以上走って地方憲兵のもとに出向いた。曽祖父はこの憲兵とは旧知の間柄で、殺人の告訴をまともに取り合おうとしない憲兵に向かって、かつての出来事を持ち出す。「老ヴァルルモーデンがアルトレンブルクの協定に署名し、この土地がフランス領に編入された時、お前さんはどうした、憲兵さんよ? あの時、おろおろして俺のところにやって来たのではなかったか?」と言う。そんな古い話、誰も覚えているものかと憲兵が言うと、もう一つ持ち出す。「ジェロームがカッセルに本拠を置いて、ジョリヴェ、シメオン、ブーグノの旦那たちがここでフランス行政区を開いた時、あんたはまた来たじゃないか?」 こう迫って、告訴を受理させる。
前者は、フランス軍がハノーファー軍を圧倒し、1803年7月、ヴァルルモーデン元帥との間でアルトレンブルクの協定 Vertrag von Artlenburg を結んで、ハノーファー軍を解体に導いたことを指し、後者は1807年のティルジットの和約により、ナポレオンがカッセルを首都とする「ヴェストファーレン王国」Königreich Westphalen (Royaume de Westphalie) を作り、弟のジェローム Jérôme を国王に据えたことを指している。
物語の主人公、語り手「私」の曽祖父のファーストネームはヨーハン、ファミリーネームは不明。年齢は四十歳前後か、せいぜい五十歳までだろう。家族は妻のことには触れられているが、子供のことは不明。語り手の曽祖父だから子孫を残しているはず。何で生計を立てているのか説明はない。大きくはなさそうな家と畑を所有し、女中が一人いる。その他の使用人の有無は不明。そりを所有し、そりを引く馬も飼っている。人々との接し方からこの土地では顔が利きそうな雰囲気がある。場所はニーダーザクセンのどこからしい。
その人物像は、ナポレオン時代末期の一人の市井の人として、性格といい、ものの考え方といい、なかなか魅力的に仕立てられている。ウソを飼って、口笛を吹いて歌を教え込むことに凝っている。《クールプファルツの猟師》(*****) を完璧に歌わせた。そして冬の夜のウサギ狩り。狩は狩猟本能に駆られたわけではなく、目的は食べるため、「ベーコンを挟んだウサギの焼き肉が好き」とある。その欲望が夜の狩猟に向かわせた。「ウサギの肉にはたっぷりのキャベツをそえて食べるのが好きだったし、その際、キャベツがウサギを呼び寄せる世界は良く出来ている」と、臆面もなく怪しげな所感を述べる。
だが、「もっと好きだったのは、夜の数時間、いつもの椅子に座ってグリューワインを飲み、物思いにふけることだった」というように、月夜の猟の目的はワインのグラスを傾け、一人空想にふけることだった。「ときには回想を追い、ときには世界がいまとまったく違った造りになりえないかと考えこみ、ときには星の位置を確かめたりする。また覆いをかぶせた鳥かごのなかで穏やかに休んでいる鳥のことを思い、自分も鳥になりたいと願った。この体に羽根が生え、家からパタパタと飛び出し、森へ飛んで行って別の鳥たちと会って一緒に飛び回る」 こういう奔放な空想は、「ウサギ狩りのおまけであった」とされる。
縁起を担いで白い獲物を忌避する猟師が多い中、「曽祖父は迷信深くなく、シロウサギだとわかったら、すぐさま仕留めて剥製にしよう」と決めた。そんな人間にシロウサギとともに奇怪な事件が忍び寄ってくる。夜が明けてメーヴェスホーフへ行ってみると、夜中に会ったコンラートが家に帰っていないという不思議な状況に直面する。呆然と立ち尽くしつつ、「農婦の胸を見ていた、高く硬く盛り上がった胸が、青い麻の衣服の下で激しく上下していた。」 コンラートの行方は?という大きな、深刻な謎に襲われながら、胸の隆起やコルセットを着けていないなど不謹慎なことに気を取られる。だが、このあたりの描写から農婦が妊娠していることを読み取る評者(v*)もあるようだ。 彼は見かけに囚われることなく理詰めで考え、その冷静な推理と行動の決断が死体の発見、事件の解決に道筋をつけたのである。
凄惨な死体発見現場を躊躇なく村人に見せる。「どんなにむごい光景であれ、物事を直視することが子供にも未婚の乙女にもいい薬になるという厳格派に、彼は依然として属して」いた。また、犯人が村人のリンチに遭わないよう、死体のある場所に近寄せず、遠く離れさせる。「あれこれの配慮は、彼が秩序と分別の男」であることを示していた。
物語を読み終わって、奇妙な事件は解決したが、すっきりとは解消されないで残った疑問が一つある。コンラート死亡の間違った公文書のことだ。曽祖父は大いに困惑したが、同時に、文書にある「蹄鉄工ヴィルムセンの陳述」に疑念を抱いた。読者も、これは錯誤か故意の誤報か当惑させられる。ストーリーが進行して、死体が発見され犯人が逮捕されても、この件はあいまいで、宙ぶらりの気分が残る。サスペンスを強める仕掛けとしては効果を発揮したが。
さて物語の主人公は「私」の曽祖父とあるが、作者ユンガーの先祖にモデルとなるような人物がいたのだろうか。兄エルンスト・ユンガーの伝記 Helmuth Kiesel: Ernst Jünger. Die Biographie (2009) によると兄弟の曽祖父 Georg Christian Jünger は1810年、ハイルブロンのネッカー川を挟んだ対岸の村に生まれ、靴職人の修行を積み、オスナブリュック(ニーダーザクセンの一都市)で親方となったとあり、直接の関連はなさそう。ただこの町は1807年ナポレオンが建国した「ヴェストファーレン王国」に含まれるので、物語の舞台と地理的には重なっていると思われる。
曽祖父の魅力ある人物像の造形には成功した作品であろう。そして、物語の背景をなす、真冬の季節の描き方が美しい。降雪、積雪、朝と昼と夜それぞれの雪景色の描写。見事だ。物語の結末部分を引用しておこう。
いまお話しした出来事からしばしの時が経っていたが、ある夜、窓辺に座っていると、シロウサギが再び現れた。それが畑から近づいて来るところはまったく見なかった;突如そこにいたのだ、曽祖父がシロウサギのことなどいささかも考えていない時に、チリメンキャベツの側に座っていた。ユキウサギでないことははっきりわかった、というのは耳の先も白かったからだ。尻尾から耳まで、足元の雪のように少しの斑点もなく白くて、そのため見え辛かった。ウサギはそこに座り、前足を揃えて上げ、再び二本脚で立ち上がってキャベツをかじった。ごく近くにまで来ていたので、静まり返った冬の夜にカリカリかじる音が窓越しに聞こえたくらいだった。そしてあたかも猟師に目配せしているように見えた。だが曽祖父はウサギを撃つ気はまったく失っていて、銃は窓の側に立てかけたままであった。「さあ、さあ」と彼は言った、「食べろ。お前を見ただけで俺は満足だ。」 (S.265f.)
『白兎』を訳し始めて、そういえばこれには前川道介先生の翻訳があったと思い出した。それは先生がまだ三十代初めの、1957(昭和32)年のことである。推理小説雑誌「宝石」の1957(昭和32)年、新年特大号に掲載されている。(p.264-281)
この作品は先生のドイツの短篇翻訳アンソロジー『独逸怪奇小説集成』(2001 国書刊行会)には採られていないので、(これの収録作品28編の原著者名とタイトルは「CiNii 独逸怪奇小説集成」に掲載)アクセスが難しい翻訳だが、先日、「日本の古本屋」で当該雑誌を見つけ、幸いにも入手できた。

表紙 糸園和三郎の鳥の絵
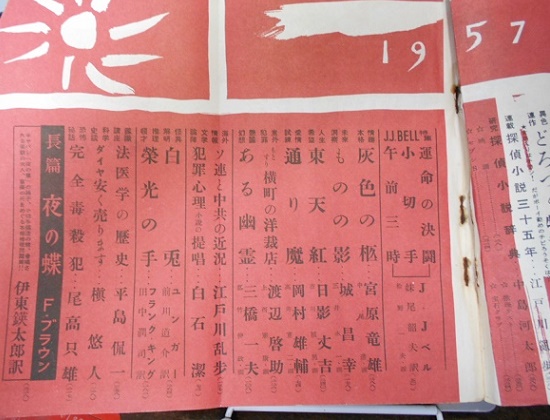
目次(部分)
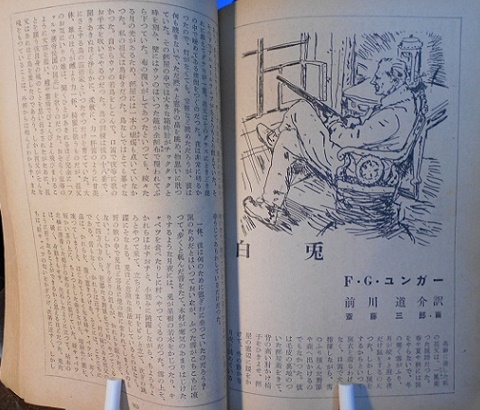
p.264, 265
一通り自前の訳を作り終えてから、前川訳に当たった。対照して読んでみて、拙訳の多くの箇所で拙訳ぶりを思い知らされた。それどころか誤訳の発見も数箇所に上った。先生のこなれた日本語に感心しきり、訳語の自由な(辞書に縛られない)選択、強調の副詞などの省略、言い換え、追加に唸らされた。訳者か編集者かいずれの指示か不明だが、原文に無い段落も加えられていて、もちろん圧倒的に読みやすい。先生は、その他ユンガーの短篇をドイツ語テキスト中級読み物としても編まれていた。ユンガーについて、またドイツ語の翻訳について、もっと真剣に教えを乞うておくべきだったと、今更ながらに悔やんでいる。
[使用テキスト: Friedrich Georg Jünger: Werke. Erzählungen 1 (Klett-Cotta, Zweite Auflage, 2004) S.244-266]
* Grünkohl 別名を Krauskohl ともいう、とあるので (de.wikipedia) 「チリメンキャベツ」と訳しておいた。
** 和名「アナウサギ」(ウィキペディア)
Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) ist die einzige Art in der Gattung Oryctolagus innerhalb der Familie der Hasen (Leporidae). Es ist die Stammform aller im deutschen Sprachraum bekannten Hauskaninchen. Kreuzungen zwischen Feldhasen und Wildkaninchen gibt es aufgrund ihrer unterschiedlichen Chromosomenzahl nicht. (de.wikipedia)
桜井富士朗「アナウサギの日本飼育史(日本絵画でたどる)」が参考になる。
*** Albino アルビノ(先天性色素欠乏症)
先天的なメラニンの欠乏により体毛や皮膚は白く、瞳孔は毛細血管の透過により赤色を呈する。劣性遺伝や突然変異によって発現する。広く動物全般に見られ、シロウサギやシロヘビが有名である。(ウィキペディア)
**** Meweshof は「メーヴェスの農場」だろうが、 Mewes' Hof と書かないのは、近辺では固有名詞となっていたのか。...hof という小地名は珍しくない。ネットで検索すると、Buchholz (Mönchengladbach) という村があり、そこにも「メーヴェスホーフ」という農場があるようだ。(http://www.mg-buchholz.de/meweshof.htm)
***** "Der Jäger aus Kurpfalz" は良く知られた民謡の一つ。いくつかのヴァージョンを youtube で聞くことができる。
v* スイスで刊行されたユンガー短篇集 ≫Dalmatinische Nächte und andere Erzählungen≪, o.J. [1973] の Erhard Schwabe による後書きに、"Die von fein spielenden Humoren umwitterte Schilderung von den nächtlichen Zimmerjagden des Urgroßvaters springt jäh um in die Geschichte vom Mord an dem Heimkehrer aus dem napoleonische Rußlandzug, der durch tausend Höllen geschritten sein mag und nun hier in der Heimat vom Knecht auf Anstiften der von dem anderen schwangeren Frau erschlagen und im Dunghaufen verscharrt wird." とある。
夜の明かり Nachtlichter
『夜の明かり』はフリードリヒ・ゲオルク・ユンガー Friedrich Georg Jünger (1898-1977) の短篇集「クジャクとそのほかの物語」(Die Pfauen und andere Erzählungen, 1952) に収められている。他とはかなり趣を異にする作品で、登場人物の言動と物語の雰囲気が異様かつ奇矯、読み進めるのに骨の折れるところがある。ストーリーはさして複雑なものではない。主人公の名はプレス、年齢は三十歳前後か。時代は第一次世界大戦後の1920年代か30年代らしく、「彼のベルリン時代の最後の年」に、古アパートの四階に住んでいた。プレスが夜更けに部屋を出るところから物語は始まる。
雨模様の陰鬱な十一月、プレスは人と会う約束を思い出して、待ち合わせ場所のビヤホールへ行く。目指す相手、医師グルトの姿が見えず、立ち去ろうとした時、広いフロアの一隅に、最近交際するようになった若手女優シルヴィアが、人気俳優といちゃつき戯れあっているのを見る。この俳優とは人生の敗北者とでもいった役柄を得意とするヴァイムートである。プレスを見かけたシルヴィアが寄ってくるが、冷たくきっぱりとはねつける。その報告を聞いたヴァイムートが談判にくるが、対話は異様なやり取りに進展する。人気俳優の突然の自殺という事件を挟んで、出来事の時系列に沿ってストーリーはリニアに進行し、べつに複雑ではない。では何が難しいか、何が読者を戸惑わせるのか。それは事件の謎もあるが、何よりも登場人物の語る異様な話柄だ。
このあと「事件」が起きる。この俳優の突然の自殺である。ストーリーのヤマとなる謎の出来事である。店内は騒然、外へ飛び出す客、遅れて医師グルトが来る・・・
プレスがビヤホールを出ると、衝撃で放心状態となったシルヴィアがすがってくるが、冷酷にあしらう。通りの反対側にコートもなく路上をさまよう少女の姿がある。声をかけると、旅の途次に立ち寄ったこのベルリンで母親が急病で倒れ病院に収容されるが、娘は身寄りもお金もないとのこと。プレスは事情を聞いて、ゲルトルートという名のこの少女を自宅に招じ入れ、食事を与え、眠るためのソファーを提供する。翌朝、着衣のまま熟睡している少女にメモ書きを置いて出かける。ヴァイムートの葬儀の段取りを確かめ、病院で少女の母親の容態を尋ね、ついでに少女のためのコートを買ってこようと考えるところで物語は終わる。
まずは冒頭のプレスが住む古アパートの描写。部屋は建物奥の中庭に面しているが、「中庭といってもモルタル張りの壁に囲まれた四角い明り取りの縦穴」でしかなかった。壁にはひび割れが走り、あちこちで漆喰がはがれ、赤いレンガが見える箇所もある。そのはがれ傷の線をたどると何かの形に見える。ある模様はウサギに見える。モルタルの剥がれが作る模様、これは誰にも見えるものではない、「象形文字と同じく、注意深く解読しなければならないものだからだ。割れ目が作りうるものがここでは作られていた。動物がひび割れているのではない、壁はひび割れることを示すのであり、それをまた人間に無言で知らせるのだった。」(S.43)
たまたま生まれた形、人の意思に依らない造形についてはもう一度、素材を変えて大掛かりに描写される。主人公プレスと俳優ヴァイムートとの異様なやり取りが長々と続き、肝臓の病気のこと、飲み薬(俳優は「人工の明かり」"künstliches Licht" と呼ぶ)のこと、そして「時間の圧縮」「純粋な意識」が話頭に上がった奇妙な対話の最後、赤道近くの小さな島で貝殻の作る模様をヴァイムートは饒舌に語る。
アンダマン諸島のなかに小さな島があります、白砂の島で海の巻貝の見事な壁に覆われています。真珠母貝の帯、虹色のヴェール、色鮮やかな石灰です。何かの海流が海底のサンゴの森からこうした貝類を砂の上に運ぶのです。そこでは白い虎が教皇の冠の横にあり、オレンジ色の提督がバビロンの塔の横に立ち、そしてムーア人の帯、ハートの角、巨人の耳、ナツメグの王冠、大理石のナツメヤシを見立てることができる。あなたも愛好家がお気に入りに付けた素敵な名前に気付かれるかもしれない。これら石灰の多くは純金と釣り合う値打ちのある物だった。円錐のカタツムリ、石灰の三角袋、それはもうないが、アレトゥーサが青い部屋で見る夢はまだある。 (S.56f.)アレトゥーサの青い部屋とはこのニンフが姿を変えた泉のことか。あなたはその島を見たのか、行ったことがあるのか、とプレスは尋ねた。すると、それを実際に見たわけでなく、想像世界の光景であることが判明する。こう言う、
もっと悪いことに、夢で見たのだ。私はカタツムリのコレクションを持っていた。それで私は何の夢を見たのだろう。納骨堂だ。太陽が白砂の上で燃えている。青い鳥の群れ、いやな臭気。というのは堂内部の部屋、その紡錘体、渦巻き、螺旋階段に、柔らかいバラ色の肉が付着していた、そこには陽の光を浴びて他ならぬ腐敗がある。塔、円錐、石灰の円柱は腐敗に満たされていた。 (S.57)「もっと悪いことに」と、実際に見るより夢で見る方が悪いと意味深長な言葉を発し、ヴァイムートはこのあと「人間とは何か、なぜ生きているのか云々」という詩(プレスに言わせれば空虚な詩句)を吟唱し喝采を受け、壁を飾っていた仮面の一つを取って顔にあてがって周囲を見まわし、さらに大きな喝采を浴びる中で、銃を取り出し自殺に至る。
この物語のもう一つの特徴は、主人公プレスの内面の動きが地の文に紛れていて、語り手「私」の思考と交錯していることだろう。語り手が登場人物が語る理屈を解りやすく説明する機能を果たさず、逆に論旨を複雑にし、読み進めるのを困難にしている。プレスが「私」でないのはなぜ。どうして語り手を分けたのか。これは小説として成功しているか。プレスと語り手が物語中で最初に会話を交わすのは冒頭近く、剥がれたモルタルが作る模様の描写の後である。
私は壁について彼と交わした会話を思い出す。「これは」と彼は私に言った、「素晴らしいものだ、我々に何も隠さない、我々はあらゆる秘密の核心に踏み込む、秘密はまさに我々の内にあるからだ。とにかく物事の本当の在り方から、人間の真の性質から目を逸らせようとする努力は全く無益だ。目を逸らさなければどうなる? すべてが表面化する。このような壁は自然界のどこにも存在しない。これは造られ、ここに置かれ、これを製造し配置したことが持つ意味をすぐさま示す。壁は自らを発見し、暴露することで、なんと静かに製造と配置を暴露することか」プレスの見解も「私」の解釈も、読者を戸惑わせるものだろう。
「どこへ話を持ってゆく気だ?」と私は尋ねた。「私が間違っていないとすれば、存在するものは説明できない、まさしく説明不可のところに明晰と真実がある、と言いたいのだな」 (S.44f.)
この短篇には作者のベルリン時代の体験が色濃く反映しているように思われる。F・G・ユンガーは第二次大戦後、自伝的なエッセーを2冊出している。『緑の枝。記憶の書』(1951) と『年月の鏡--記憶集』(1958) である。前者は誕生からライプチヒ大学で法学を修め、司法修習を始めたものの、法律家の道を断念するまで、後者はその後、ベルリンを拠点にフリーの著作家としての生活を自伝的に書いたもの。1928年から1935年までの『記憶集』である。
ユンガーのベルリン時代は、第一次大戦後ドイツ帝国が崩壊し、ワイマール憲法による「ドイツ共和国」が成立した以降の時代に重なる。あの天文学的なインフレ(司法修習生時代、勤務地マイセンのワイン酒場で食事をして3兆マルク支払ったことがあった。「緑の枝 -13-」参照)もようやく終息し、経済的には安定期に入って近代的都市生活が広まり、ヨーロッパきっての産業都市に発展したベルリンは、文化芸術また芸能分野においても時代の最先端を走る。都市型大衆文化が一気に広まったのである。文学、音楽、アールデコの美術・装飾・ファッション、カフェハウス、バラエティー、キャバレー、ヴァリエテ、レヴュー、演劇、映画で次々と実験的な試みが行われた(「ベルリンの空気 Berliner Luft」参照)。だが帝都から共和国首都へと変わった「世界都市ベルリン」の、そんな「黄金の二十年代」が黄昏を迎えようとしていた。
政治・社会的には階層間の対立が激しくなり、騒擾・紛争が続き、1929年にアメリカ合衆国で始まったの世界大恐慌の影響をもろに受け、失業率がすさまじい勢いで上がってゆく、社会の隅々で高まった不安を背景にナチスが台頭する、そんな時代のベルリンでユンガーは過ごしたのであった。『年月の鏡』によると、大都市ベルリンに移ってきて、初めは兄のエルンストの住居に居候し、やがて各所を転々と移り住む。新しい知人との交友が始まった。新しいタイプの変人奇人と呼ぶしかない人間も少なくなかった。時代の大きな転換期に、ライプチヒなどとは比較にならない都会らしい都会で、数多くの新しい経験を味わった。街を歩き回るのが日課であった。
『夜の明かり』では俳優ヴァイムートの突然の、異様な形での自殺がストーリーのヤマとなるが、ユンガーはベルリンで実際に自殺を目撃している。ベルリンの地下鉄駅での出来事である。
私はあるとき階段を駆け下りる男を見た。私の横をすり抜け、あたかもすべてがスピードにかかっているかのような、少しでも緩めると危険だ、という様子だった。下に降りてゆくと、電車の運行が止まっていた;駆け下りていった男が線路に身を投げて轢死していた。そこは分刻みにいろいろな列車が走っていた。何のために急いだのか、なぜ人々を無遠慮に押しのけたのか? 自分の決意が揺らぐのではと恐れたのか? それとも決行をぐずつく一刻一刻が耐えられなかったのか? 私にはわからなかった。(Spiegel der Jahre. S.18f.)『年月の鏡』にはさまざまなエピソードが散りばめられていて、ヴァイムートの自殺事件の舞台と同様の、怪しい雰囲気の酒場へ出かけたときの体験についても語られている。
凍てつく冬のある夜、ある酒場に入ると仮面パーティが開かれていた。ブラックがいて、ヴェラも一緒だった。それは無頼のならず者が寄り集まっているパーティだと見えた。酩酊は人間から多くのことを引き出す。それにまた斬り裂くような、グラスが飛び散るような鋭い音響があり、ここで聞こえるのはそのような音ばかりだった。このパーティは緊張と隠された敵意に満ちていて、笑うよりも泣き出しそうな連中が多いようだった。私はいきなり酔っぱらった俳優と衝突した。誰か知らない俳優だったが、私を敵の一人だと取り違えたようだった。仲間が引き戻したが、彼は片隅で座って陰にこもりぶつぶつ騒いでいた、その近くで一人の女性が顔をテーブルに臥せて痙攣を起こしたように泣きじゃくっていた。ヒステリックな叫びが、空虚で無意味な叫びが、喧騒の中を貫いた。ヴェラはその場の振動にグラスハープのように共振していたが、突如立ち上がり着衣を脱ぎ捨て、身を切る寒さの冬の夜の道路へ走り出た。(Spiegel der Jahre. S.91f.)まこと、ユンガーは「私にはこの街がしばしば魔法の霊液を調合する試験管のように思われた」(Spiegel der Jahre. S.91) と言うほど異様なもろもろの出来事にベルリンで出会うのである。
[註]
Brack と Vera(いずれも仮名か)。ブラックはベルリン時代に知り合った一人。第一次大戦をオーストリアの兵士、士官として従軍した。首に銃弾を受け、イタリア軍の捕虜となった。喉頭の傷により、声が出にくく、話すのに苦労が要った。理解できない激しい戯曲を書く。「声を持たない人間のアナーキー」、とある。 (Spiegel der Jahre. S.85)。
ヴェラはドイツ人夫妻の養子となったコサックの娘。ブラックと結婚するが、破滅的なふるまいを繰り返す。この場は誰かがヴェラの後を追い引き戻したが、その後まもなく、夜の街をさまよい「人工の光の中でどのような思いがよぎったのか」、自宅で生命を断ち、裸で横たわっていた。 (Spiegel der Jahre. S.93)
『夜の明かり』では、登場人物たちの突拍子もない議論が続く。形と時間、自動機械、痛みの実験室、時間の節約から存在の意味に及ぶ議論の筋道をたどるのは容易でないが、ずっと見え隠れしているのが「時間」のテーマである。プレスは酒場での長いやり取りの末、金を無心する俳優に、これ以上飲まないのがもっといいのだが、と言いながらも酒を一杯おごる。ヴァイムートはダブルで注文したウィスキーを一気に飲み干したので、プレスは忠言する。
「この圧縮した飲み物をそんな一気に飲み干すべきではありませんでした」と、プレスはもう一度述べた。物語の各所で時間にまつわる話柄が繰り広げられる。プレスはそれまでベルリンでつつましく生きていたが、事件が起きた「彼のベルリン時代の最後の年」か、その少し前に発明家の叔父の遺産が、特許使用料が転がってきた。その発明と言うのが、三つの自動機械であった。
「それは私のフレーズだ」とヴァイムートは叫んだ、「あなたは私のフレーズを口にした」
「どの語が?」
「圧縮、だ。人は圧縮しなければならない」
「何を?」
「時間、空間、運動、我々自身。人は圧縮しなければならない」
≫Sie sollten dieses komprimierte Zeug nicht so hastig hinunterschütten≪, bemerkte er noch einmal.
≫Das ist mein Stichwort≪, rief Weimuth. ≫Sie haben mein Stichwort ausgesprochen.≪
≫Welches?≪
≫Komplimiert. Man muß komprimieren.≪
≫Was?≪
≫Die Zeit, den Raum , die Bewegung, uns selbst. Man muß komprimieren.≪
(S.52)
発明とは他人が必要として、まだ所持しないものを調達する技だ。その必要なものは、進んで受け取られるために、なるほどと思わせるところがなくてはならない;これを使うと節約できるものがあるという印象を与えねばならない、すなわち時間である、というのは全ての節約は時間の節約に結びつく。何のために時間が節約されたのか、これのためだと言えるものは何もない。節約された時間はすべて自由な瞬間を生み出すことはない、それはできないのだ、何故と言うに時間の節約は時間の窮乏から生じるもので、それゆえ自由な時間の不足は増す一方だからだ。(S.45)この箇所から読み取れるのは、近代の技術が集約するところは《時間の節約》だ、という観点だが、俳優ヴァイムートと主人公のプレスとのやり取りでも「時間の圧縮」「純粋な意識」が主たるテーマとなる。ヴァイムートは先ほどのやり取りに続けて言う、「だから我々は圧縮しなければならない、酔っぱらうか・・・」
「あるいは?」この「純粋な意識」の定義は作者ユンガーの思考と通じるものかも知れない。それが自由を生み出さないとすると、生命を短縮する人間が出てくるのも考えうる成り行きか。病気であろうがなかろうがいずれ人はみな死ぬのである。
「純粋な意識」
「それは何を意味しているのですか?」
「我々の歴史です、あなたや私の個別の歴史を含んだもの。歴史が終わると時間が終わる。わかりますか?」 彼は空のグラスを指ではじいたので倒れた。「光だ」
≫Oder?≪
≫Pures Bewußtsein.≪
≫Was verstehen Sie darunter?≪
≫Unsere Geschichte, Ihre und meine Spezialgeschichte mit einbegriffen. Und Schluß mit ihr, Schluß mit der Zeit. Verstehen Sie das?≪ Er schnippte mit dem Finger gegen sein leeres Glas, daß es umfiel. ≫Licht.≪ (S.53)
俳優ヴァイムートはなぜ自殺したのか。彼はその世界ですでに名を成していたが、肝臓癌か肝硬変という重い病を患っていた。医師の診断では治癒の見込みはなく、手立てとしてはモルヒネで最後の苦しみを和らげるだけだったようだ。彼の自殺はいずれ来る死を早めようとしたのか。「ヴァイムートは自ら孤独を求めたので、穏やかな死に耐えられなかった。俳優としての精神と言うべきものが、彼をさらっていった。この結末のパトスは極端で、自己の破滅の演技にまで進展した」(S.64) 彼の役者として最後の演技が死の決行だった。
タイトルの「夜の明かり」Nachtlicht, -er (pl.) は現在では寝室用の照明を意味するのが普通だが、ここではさしあたり都市の街灯、店舗のショーウインドーを指している。《精神の闇を照らす光》まで含意しているだろうか。俳優ヴァイムートは「純粋な意識=光」と定義し、肝臓病の飲み薬を「人工の明かり」と呼ぶ。ユンガーがベルリンで交友のあったブラックの妻ヴェラは夜の「人工の光の中」をさまよって、そのあと生を閉じた。プレスがビアホールを出たあと、ホール前の道路には果物店のウインドーがあり、それがまたアーク灯の光を受けている近くの病院に通じている。
プレスが街頭をさまよう純朴な少女ゲルトルートを「夜の明かり」から《救出》したところで、作者は物語を終わらせた。
[使用テキスト: Friedrich Georg Jünger: Werke. Erzählungen 2 (Klett-Cotta, Zweite Auflage, 2004) S.43-72]
十字路 Kreuzwege
『十字路』はフリードリヒ・ゲオルク・ユンガー Friedrich Georg Jünger (1898-1977) の第三短篇集、「十字路」(Kreuzwege, 1961) の表題作。かなりの長さがある作品で、いくつかの劇中劇ならぬ《話中話》が語られ、そこに登場人物の特異な思考が絡み合って進行する複雑な物語である。物語は、珍しい花の描写から始まる。
白いテーブルクロスの上のカルセオラリアには赤と黄色の斑点があった。花弁下部の膨らみが靴のように見えることからこの名がきている。南アメリカ原産。打ち眺めるに、植物学者が与えた系統内の位置は、この花を観察する者の内に呼び起こすイメージについては何も語っていない。それはまた同じ系統に配置された親族、モウズイカやヴェロニカの記憶も呼び覚ますことがない。花は非常に色鮮やかで、東洋の履物だ。柔らかく膨らんでいるようで、あたかも花の中に空気を張ってあるように見える。とても柔らかく傷つきやすい素材で作られていた。三つの花の名、テキストのドイツ語では Kalzeolarie, Königskerze, Veronika である。カルセオラリア、モウズイカ、ヴェロニカと訳したが、和名あるいは一般の呼称と合っているかどうか。作者は三つを「同じ系統に配置された親族」として扱っているが、現在の分類では変更された可能性もある。調べてみるとカルセオラリア「キンチャクソウ(巾着草)」はシソ目、キンチャクソウ科、「モウズイカ(毛蕊花 )」はゴマノハグサ科の属、ヴェロニカ「ルリトラノオ(瑠璃虎の尾)」はオオバコ科 / クワガタソウ属(ベロニカ属)となっている。
ヴェロニカはクワガタソウである。いまテーブルに一緒に座っている少女もヴェロニカという名であった。彼は少女に一瞥をくれ、会話に耳を傾けた。妻がビリング医師について語る調子から、ガルは妻の標的が医師ではなく少女であることに気付いた。回り道を選んでいるな、と彼は思った。エリーゼがまっすぐの道を進めばいいのだが。彼の思考はまた会話から離れた。 (S.153)

[de.wikipedia を見るとそれぞれには多数の種があり、
転載した画像が作中の花と重なるかどうかは不明]
そしてそこに座る少女の名がヴェロニカで、テーブルのカルセオラリアを囲んで座るあと二人は、ガルとエリーゼという名の夫婦である。ヴェロニカの年齢は正確にはわからないが、結婚適齢期にある娘らしい。エリーゼとは昔から親密な付き合いのようで、どうやらこの家に入り浸りの様子。そして女性二人の話題はビリング医師のこと。この人物は、少し先でわかるが、夫妻のもとによく訪ねてくる客の一人のようだ。
語り手のガルは、女性二人のやり取りを聞くともなしに聞いている。というか、食事中なのに自分の思弁世界に入り込んでいて、ときおり二人の声が外から聞こえてくる、という状況らしい。いまは会話 Gespräch と像 Figuren について思いを巡らせている。会話はフィギュアを作り出し、会話が強い力と妙なる響を持つなら、そのフィギュアもより力強く響きの良いものとなる。フィギュアの位置と形が変わると、駒の動きは見えるがその隠れた意図が見通せないチェスの対局に似てくる。どうやらエリーゼはビリング医師について厳しい見方をし、それを直接言わないで、医師のイメージを攻撃することで自分の意図を表現している、とガルには思える。
そこからガルの思考は音楽の倍音に進む。フランスのソーヴェールなる聾唖の学者が倍音を見つけ出したこと、続いてジャン=フィリップ・ラモーの理論にも考えが及び、振動体が発する音は基本の音に倍音が加わっている、その倍音の方に音の響きの色彩が宿っている。色彩のない音は、物理的に純粋な音は死んで生命がないので、つまりは倍音の方に生命がある。「エリーゼの語りに倍音があって、その中に生命があることは間違いない」と考えるのである。
食事を終え、ガルが自室に戻ってしばらくすると、女たちの話題になっていたビリング医師が部屋に訪ねてきた。医師はヴェロニカと結婚したいと考えていて、ガル夫妻に仲介を依頼に来たのだった。ガルは先ほどの食卓の会話を思い浮かべつつ、「ヴェロニカは成年(*)に達しているし、両親はいない」ので、結婚のことをどうするかは「彼女の自由だ、彼女は自立していて、自ら決めなければならない」と言って、仲介は引き受けられないので、直接プロポーズするのがいいと勧めた。ビリングはその勧めに応じて、女たちのところへ向かった。
やがて日が暮れかけたころ、階段を昇ってくるエリーゼの足音で、ガルにはプロポーズの結果が察知できた。妻の足音から喜びが隠せない心持ちが聞き取れたのである。話がまとまらなかったことを喜ぶエリーゼは、医師のことを「無味乾燥で索漠としたところがある」と評する。あの人と一緒になるくらいなら、「ウズラかフクロウと一緒に住む方がいいと思わない?」と言う。
またしばらくして、二人の女は仮装してガルの部屋に上がって来た。肩に鳥の翼をつけ、鳥の仮面、長い風切り羽のついた帽子をつけるといった、奇抜な衣装だった。「謝肉祭はまだ先だ。時節前にはしゃぎ過ぎだ」と咎めるものの、ガルは仮装すると二人は見分けがつかないことに気付いた。同じ背丈、そして体形も同じだった。いつも二人は彼にはまったく異なった人間として見えていた。二人を区別できないことが彼を混乱させたのである。このエピソードは、徐々に見えてくる小説のテーマを端的に指し示している。似ていること、区別できないこと、アイデンティティ、人と人との間の同一性、異質性の問題である。
このあと、夫妻のもう一人の常客、ヴェヒターが訪ねてくる。夕食に招かれていたようだ。客が持参した花がまたカルセオラリアであった。二つのカルセオラリアがテーブルを飾ることになった。ヴェロニカは客人の驚いた顔を見て、笑って言う。「花二つは一つよりいいのよ」と。これを聞いたガルが「本当かい?」と気遣わしげにヴェロニカの顔を見たとあるが、彼は何を気遣ったのだろう。ここでも類似・同一の問題が浮かび上がる。エリーゼが「こちらは暗紅色の花弁よ」と違いを指摘する。そして、この花を育てた庭師ヘプナーの話題となる。この町で昔から園芸に携わっていた人物のようだ。
「彼のことを覚えている」とガルは言った。「小男で、プラムの老木のように体が屈曲している。しわだらけのプラムのような顔で、しわが内へと窪んでいる」この問いを受けてヴェヒターは、キエフから当地を訪れたときの出来事について話をする。それは四月の初めで、花が必要となり、戦時下で野菜を優先するため花の栽培が禁じられていた状況で、ヘプナーのところならあるかも知れないという噂を耳にして出かけた。その日は駅近くに爆弾が落ちたのだったが、駅のそばを通って庭師のところへ通じる道を上って行った。爆弾の一つが園芸農園の真ん中に落ちて、花壇に大きな漏斗状の弾孔ができていた。ガラスの温室は骨格だけが残っていた。そこにはレタスやトマトがあり、さらにカルセオラリアがあった。ヘプナーは「追い立てられたウサギのように」農園を走っていて、声をかけても振り向きもしなかった。その日以降、庭師は抑うつ状態になった。
「そんな風に人間を描写しません、それは地霊です」とエリーゼは言った。
「だが当たっている」 ヴェヒターは頷いた。「庭師は地霊の世界からやって来る」
「私は会ったことがありません」、ヴェロニカは言った。「彼はどうなったのですか? まだ生きてらっしゃるのですか?」
「いや、もう亡くなりました。彼の最期について少しお話しさせてください。当時私はキエフから、初めて当地にやって来ました、短い滞在でしたが」
「キエフにいらっしゃったのですか?」とガルは、ヴェヒターのほうを注意深く見ながら、声をかけた。 (S.162)
ヴェヒターが物語の舞台である当地に「初めてやって来た」「四月の初め」「駅近くに爆弾が落ちた」という時期、歴史上の時系列で下敷きにあるのは、恐らくドイツが敗戦にむかっていた1943年だろう。第二次世界大戦の独ソ戦(東部戦線)において、スターリングラード攻防と並ぶ激しい戦闘で大きな犠牲者を出したのが、当時ソビエト連邦下のウクライナを戦場とした1941年「キエフの戦い」と1943年「ドニエプル川の戦い」である。二年余り独軍がウクライナの大半を占領・支配していたが、1943年十一月六日にソ連軍が奪回した。
「当時私はキエフから、初めて当地にやって来ました」と言うヴェヒターの言葉に、ガルは注意をひかれたようだ。当地、すなわち物語の舞台となっている町についてはロケーションが明らかでない。ドイツのどこか北方の小都市だろう、というくらいの印象である。ドイツのどこをとってもキエフとの距離は相当ある。ベルリン・キエフ間はグーグルマップで見てざっと1200キロから1300キロくらいか。ヘプナーの園芸農園を破壊した爆撃とは、キエフとはかなり離れているが独ソ戦の一部であったのか、西部の連合国側との戦線だったのか。
ヴェヒターは語る、「私はまた町を離れ、そして戻って来た時、道を上がって行って、庭師の妻と話した、いま話すのは彼女から聞いたことだ」とのこと。 爆撃で破壊された園芸農園のヘプナーは、爆弾が落ちたしばらくのち、夜、寝床を出てゆくのに気付いて後を追ってみると、箪笥の引き出しを一つ一つ開けて紙袋から種をまいているのだった。
「気味の悪いこと」とヴェロニカは言った。そしてある夜、庭師ヘプナーは妻が気づかないうちに出て行き、翌朝、園芸農園で亡くなっているのが発見された。巻いた鉄線を持ち裸足で外へ出て、水槽の一つに入り、鉄線を高圧線に投げていた。感電死を選んだのだ。
「気味悪い?」とガルは、この時初めて会話に加わった様子。「気味が悪い、確かに。しかし見事で、立派で、強くもある。優れた庭師、生まれながらの庭師はそうでなければならない」
エリーゼはそれに賛同した。「気味悪いのですが、優しくもあります。多くのことが重なっていますね、男性の憂愁、月明かり、行為の虚しさ。とても静寂です、すべてが。でも気味の悪さはどこにあるのでしょうか? 月明かりでも孤独の中でもなく、思い違いと取り違えにあるのでしょう」 (S.163f.)
ガルは事前に種を撒いたその死に方を見事と評し、亡くなる日の朝、部屋中に飼っていた全部の鳥を放した男とか、死の直前、育てていた美しいゼラニウムを何もかもすっかり花瓶から投げ捨てた女性とか、死にゆく者が心残りの無いようにする話はいくらでもある、と言う。気味の悪い話を続けると、怪談から離れられなくなるからとエリーゼが言って、ガルの提案でゲームをすることになる。始めたのは魚釣りゲーム。鉄鋲をつけた紙のサカナを箱に入れ、磁石のついた釣り竿で釣り上げる他愛もないゲームであった。そのあと「キエフではどうでしたか?」とエリーゼはヴェヒターに尋ねた。「私たちにお話しください」
ここで場面が切り替わり、新しい場面ではすでにヴェヒターは去ったあと、ガルはリンゴの皮をむいている。茎のところか萼のところか(**)、どちらから始めるかの考察に耽っている。「重要とみえる多くの問題も、これ以上に重要ではない」と。そしていきなり、「教師が多すぎる」と、ため息とともに語ってエリーゼとヴェロニカの会話に割り込む。エリーゼは「私は教師がなかなか増えない、と聞いています」と異議を唱えるが、ガルは「教師ぶった態度が、他人に教えようとするやからが増えている」と言う。その結果「愛嬌の無さがはびこるのだ」と。話しの趣意についていけないヴェロニカに対して、ガルは「私が剥いているこれがどんなリンゴかはご存じでしょう」ヴェロニカは「カルヴィレ(***)です」と答える。ガルは言う、リンゴはその名前を知っていると、おいしさが増すだろうか、リンゴの甘さ、「それは教えることによるのか? 違う。無知から来るのか。違う。それは教えることで増加しないのと同様、無知によって減少することもない」
ここでエリーゼは、「Wさん。ヴェヒターさんのことでしょう。いまのお話は、あの方のことをあてこすってらしたのですね」と言う。テキストの原文は ≫Ein W. An Wächter vermutlich. Auf ihn war das gemünzt, was du gesagt hast.≪ である。"Ein W." が 唐突な表現で、この訳が適切かどうか。いったいガルとエリーゼ夫妻は、この客人をどう思っているか、エリーゼは寄宿学校の評価でヴェヒターと対立している。しかし夫の議論に、「でもあの方は教師のように振舞っていますか?」≫Aber ist er lehrhaft?≪ と疑問を呈してもいる。この "lehrhaft" は「教育的」より「教師風を吹かしている」のニュアンスだろうか。ガルの方はヴェヒターがキエフにいたと聞いた時、驚いたような表情を見せた。早春のカルセオラリアの時期に、爆弾がヘプナーの園芸農園に落ちる直前にキエフにいた、との話に矛盾を感じたのだ。キエフの町の様子もあいまいにしか話せない。いろいろな状況から判断して、「ヴェヒターはキエフから来ることは不可能だった、ということははっきりしている」と考える。
偶然はしばしば奇妙な働きをする。単独の、あるいは見かけは連鎖しているような、というのは偶然には連鎖などあり得ないからだ。多くの偶然の間に関連はない;偶然は自らを通じて出来事の偶然性を止揚する。我々が偶然と名づけたがるものは、それは関連が無い何かだ。煉瓦は通り過ぎる者の頭に偶然落ちる;それは偶然当たる、だが病院に運ばれるのは偶然ではない。なにか不整合があると、とガルは口走った、その不整合に光が当たるのは偶然でない。ひょっとしたらそれは解くべき謎だったかもしれない。一枚の写真がそれを解くことができた。 (S.171)「一枚の写真がそれを解くことができた」"Ein Bild konnte es lösen." この Bild という語はさしあたり水彩画や油絵、あるいは写真、映像 [picture]だが、光景 [sight] とか表象・イメージ [image] の意味にも用いられる。物語後半で (S.187) Photograpie の語で表現される同じ対象と考えられるので、ここではその同義語として解しておく。Bild という語を用いたことで、表象・イメージの含意が込められているように感じられる。
冬がまた戻ってきて、居座った。ガルは森を散歩して町へ戻って来た時、園芸農園の側を通りかかり、病んだ男が引き出しに種子を撒いたことをまた思った。一人の老嬢が営む紙製品店で筆記用紙を買って散歩を続ける。病院の横を通る道をとった。病院の建物を眺めつつ、ビリングがそれについていかにも不快な面持ちで話したことを思い出した。そのとき、当のビリングが病院から姿を現した。医師と会うのはヴェロニカへ求婚に来たあの日以来である。長時間の手術を終えたばかりで疲れきった様子、医師の方から居酒屋に誘う。ワインを傾け、結婚の目的のことなどを語ったあと、病院勤務について、「この地で職に就いたことが私の間違いだった」と言う。
「医師たちは私の意見を認めない。あなたは医師同士の妬みをご存じか。私に苦痛を与えない彼らの行いなどない。腹の立たない日は一日とてない。今日は猛烈に腹が立った」この町ではいいことが何もなかった、病院でも個人的にも、だから別の町の病院に移ろうと考えているとのこと。ビリングは戦いを諦めた、しかし彼の怒りは再燃するだろう。場所を変えても解放されないだろう。彼の困難は若い娘の鎖骨にあるのではなかった。彼はそれを自ら産み出したのだ。ニシンが卵を産むように、困難を作り出した、つまり同じ必然性でもって産みだした。エリーゼは正しい、とガルは思った。改めてビリングとヴェヒターのことを考える。二人とも、自分のいる場所に適応できないのだ。
彼は考えて、話さねばならないことをまとめた。「少女が自転車から落ちて鎖骨を折った。病院へ運び込まれたが、私のところではなかった、私は居合わせなかったので、アシスタントの医師の許へ送られた。鎖骨骨折には特別な伸縮性のある包帯がある。包帯をする前にレントゲンを撮っておかねばならないものだ。その医師はそれを手抜きして骨折を手で探って、包帯をした」
「治療ミスなのか?」
ビリングは不機嫌な疑念に満ちた顔を挙げた。「手抜きだ。何が起きる? 骨がぱっくり開き、くっつかない、醜いかっこうになる。若く可愛いい少女、ユリのような胸、白鳥の首の成熟した少女なのだ。ことはそのまま放っておけないことは自明だ。彼女は整形外科医のもとへ行き、手術を受け、縫合してきちんとなる。彼女は、私の不倶戴天の敵のところへ行く、彼の一人の患者も私の病院で手術しない。わかりますか、これはみな私にとって辛いことだ」 (S.176)
ビリングがやっていたことは個人の集団に対する戦いではなかった。彼を苦しめたのは彼がずれていたことだ。一致できないことがここにもあった――ガルはヴェヒターのことを思った――しかしその現れ方は異なっていた。集団の中では――例えばレンガの集まりでは――個々のレンガは四角くなければならない、大きさ、色彩、配合が点検されねばならない。使い古された病院、守られない約束、失敗した手術、意地の悪い医師たち、最後に娘が与えたカゴ――これら分子は、外から来たものだが、共通の分母を持つのだ。
寒さが増してきた、湖は凍るだろう。スケート靴を見に行く時だ。 (S.179)
明るい満月の夜、ガルとヴェロニカがスケートで森林監督の家まで湖の氷上を滑って行く。ここから物語の後半に差し掛かる。銀色の満月の夜、湖は無風の酷寒と澄んだ空の下にあって凍っていた。鏡のような表面に雪は一粒も無く、一筋の線条も凹凸も見えなかった。氷はガラスのように透明で、細かな明るい気泡があった。凍てつく寒気は清浄で、焔とはまた別様の清浄さだった。ガルもスケートの腕前には相当の自信があったが、ヴェロニカの軽快で優美な滑りを見て舌を巻く。
ここで描写される湖の風景はユンガーが少年時代住んでいた近くのシュタインフーダー・メール(「緑の枝 -3」 参照)を思わせるところがある。氷上を行く二人の前でホオジロガモ Schellente、ウタハクチョウ Singschwan が飛び交う。
[下の写真は de.wikipedia から]

「この辺りの水深はどれくらいでしょう?」とヴェロニカは尋ねた。湖の中の島の側を通り、凍り付いた柳の古木を見ながら、氷に走る亀裂を避け、遠回りして目指す方向へ向かう。背の高いアシの茂み、そしてハンノキがそびえ立つ岸が近づいてきた、ここが目指す上陸場所である。アシの茂みを通り、堅く凍り付いた湿原を丘に沿って森の方に向かった、森の家に灯りがついているのを見た。犬が吠え、森林監督とその妻が出てきた。
「そんなに深くはない。三メートル位かな。五メートル以上でないことは確かだ」
「もっとずっと深ければ、と思っていたわ」
彼は答えなかった。いまは月は氷の上で明るく輝いていた。そして鮮やかな明るい反射光がはるか遠くまで走っていた。だが視界は限られていた;薄いもやが夜の明かりの中、銀色の輝きとなって、すべてを包み、同時に視程を遠ざけた。夜だ、と彼は思った、ガラスのような湖の氷上真ん中にいるのは我々だけだ。なぜ、彼女は湖がもっと深ければと願うのだろう? この願いの中には何があるのか? そこには沈降がある。彼女は私と深淵を共にしている。深淵は充分に深くないのか? (S.181)
森林監督の妻ゲルトルートはヴェロニカの姉である。子供は娘ばかり三人で一人は八歳、二人は六歳の双子。「私は女性陣に包囲されている。これは男にとって容易な運命ではない」とは父親の弁。子供たちのあどけない寝顔を見て、夜の食事を終えた後、森林監督とガルは犬を連れて森を歩きにゆく。まだ月が明るかった。この散歩の途中で、写真の話が出る。
雪が降り始めた。風がさらさらと雪を斜めに吹き下ろしていた、最初はまばらに、それから密に。裸の斜面にあるトウヒの保存木が立ち並ぶ一画にやって来た。そして古いトウヒの残るところへ曲がって行った。しばしの沈黙が続いた。森林監督の家に戻って、ガルは問題の写真を渡される。それは将校たちの集合写真であった。もとの小さな写真を引き伸ばし、厚紙に貼ってあった。明瞭さは望むべくもない集合写真だが、ルーペを使えば顔の識別は可能だった。
「写真があるよ」と森林監督は言った。「エンザーが送ってくれたんだ」
「よくわかる写真かい?」
「とてもよくわかる。拡大してあり、画面に名前が書き加えられている」
「それは行き届いたことだ」
「ヴェロニカはどうだい? 求婚されて断ったと聞いたが。いい縁組だった」
「そうかもしれない。しかし結婚は釣り合いだろうか? いい縁組からいつもいい結婚になるとは限らない」
「うむ。女性のことが全部わかっているものは誰もいない」
「それもいいことかも知れない」
「誰にとってかな? 彼女は思いのままに振舞う。彼女は火と戯れる」
ガルは驚いた。「どんな火と?」彼は尋ねた。(S.187f.)
「将校たちだ。これを写すために彼らは執務室から呼び出されて、撮影にふさわしく明るい中庭に出た。急いで行われたろうが、無秩序が入り込むほどの急ぎ方ではなかった。みな、同じ形になって、みな立っていて、そのような条件の下でグループが自ずとできる」知った顔が一人もいないことを確認する、それは何のためか。自宅に戻ったガルは森林小屋から持ち帰った写真を改めて熟視するが、そのとき、別に手紙を受け取っていたことが明らかにされる。どうやら写真の一人物の履歴を記した文書らしい。いつ、誰から届いたのか、経緯は語られない。写真は森林監督が「偶然」に入手できたというが、提供者の名前がエンザー Enser と言うだけで、それが一体誰なのか、どういう筋道で届いたのかわからない。
「階級に従って、でしょうね」とゲルトルートは言った。
「そう、一番位の高い士官は前列の中央にいて、他の者みながとる距離は地位で測られている」
「その写真をお調べになっているのは、そんなことじゃないでしょう」とヴェロニカは疑わし気に言った。「みんなオルガンのパイプか何かのように立っていたらどうだと言うの」
「まったくその通り」とガルは写真を見ながら、つぶやいた。人物には番号が打たれ、台紙の厚紙にきれいな丸みを帯びた字体でそれぞれの職階と名前が記されていた。
「写真の人達をご存じなの?」とヴェロニカは尋ねた。
「一人も」
「なら、理解できないわ、その写真の何が惹きつけるのか」
「この写真で面白いのは、まさに私がその中の誰も知らないってことさ」
「分かりたい者には分かる、ですか。説明がおできになりますか?」
(S.187f.)
彼は読んでいた手紙から目を離して、森林小屋から持ってきた写真の上に置いた。この写真のヴェヒターは、いま履歴を読んだばかりのヴェヒターと同一人物であることには、いかなる疑いも無かった。写真の彼は中背で、髭がなく、細身で歩兵部隊大尉の制服を着て、ある参謀部で軍務につくため招集されていた。写真の左端に立っていて、まっすぐ前を見ていた。向けられているレンズを覗き込んで。彼の思考は写真と手紙に戻った。ヴェヒターはヴェヒターではなかった。二人が同一でないなら、二番目が一番目に成り代わるため、書類の遺産以外何も受けていないなら――偽りは何のためだったのか? 彼はいったい誰だったのだ?
ひょっとしたらこれは彼が写った最後の写真かも知れない。多くの時間はもはや彼には残されておらず、彼は戦死者の仲間に列することは確実だった。それについては報告がなされていて、疑いの余地はなかった。墓が何処かは不明だ、無名で記録なく、見つけられないだろう。 (S.192)
「お客さんが来るのを忘れたの?」と妻から声をかけられ、ガルは物思いから覚めた。階下に降りると、ビリングが訪ねて来ていて、旅行から戻ったヴェヒターもいた。ビリングはどうやら別の町の病院に移ることになるようだった。ヴェヒターもまた当地を離れて別の町の寄宿学校の校長として赴任することになりそうだ。エリーゼは寄宿学校という制度に反対で、人工的な教育に反対する意見をのべてヴェヒターと論争する。
「あなたはお忘れかも知れません」とヴェヒターはエリーゼに言った、「寄宿学校は必要で利用されるからあるのです。子供は誰もが家族のもとで大きくなるのではありません、そしてすべての両親が子供の教育に向いているわけでもありません」その論拠は反論を許さぬように見えたがエリーゼは、寄宿学校に価値があるとすれば、女の子と男の子とが一緒に教育されることだけだとした。ガルが割って入り、男女の共学こそ人工的だと憂慮する人が多い、男の子と女の子は学校の外では別々なのだから、と言う。エリーゼはなお「子供たちは礼儀正しくなるわね、一緒に教育されたら」と主張するが、ガルは「礼儀というのもどこか人工的なところがある」と言い、またヴェヒターに向かって、あなたのお仕事は当地では注目されていたし、他所に移られると皆さびしく思うでしょう、と言うがどうやら移ることになりそうな口ぶり。
「その想像は、つまり崩壊した結婚、崩壊した家族の子供たちがそこへ送り込まれるというのに近いですね」
「たとえそうであっても」とヴェヒターは言った、「それは寄宿学校の否定を意味するのではなく、肯定かつ必要性を語るものです。寄宿学校に短所があるとすれば長所もある。劣悪な家庭環境から子供がやってくれば、その子供は自分が抱えている争いに直面しないで済む。自然の風景の中で、老人たちと共に穏やかに成長する。私が行った学校を評価できるものがある、それは生徒たちが生涯失うことのない帰属感です」(S.195)
「じゃあ、私たちともお別れなのね」とエリーゼは言った。彼女は物思いに沈んだ、その様子を見ていたガルは自分に言った、彼女は私が図形思考と呼んだものに耽っているな。魅惑する非論理の映像が彼女の脳内で浮かんでいるのだ。「どの深さまで君は潜っているの?」「生とは抽象的なものだ」という言い回しにヴェヒターがショックを受けたのはなぜか。ガルは、生とは単なる概念で、それ以上のことは何も語らない、「概念なんて神様と唱えるようなもので、神でも様でもなく、単に邪魔になりそうなものを締め出した一般的な取り決めだ」≫Er [= der Begriff] ist wie der liebe Gott, der weder lieb ist noch ein Gott, sondern nur die allgemeine Vereinbarung, die das ausschließt, was stören könnte.≪ と断じる。激しい発言だ。
「生とは何でしょうか?」
「生とは抽象的なものだ」
ヴェヒターはその言い回しにショックを受けて、彼の方を疑わし気に見た。そしてエリーゼの視線にも、彼女が異議を申し立てているのが見て取れた。
「生とは単なる概念で、それ以上のことは何も語らない。概念なんて神様と唱えるようなもので、神でも様でもなく、単に邪魔になりそうなものを締め出した一般的な取り決めだ。神様はそこにはいない、皆は神様がいないことで生きている。だが 明示的ニ言フコト(****)は許されない」
「それはあなたの神学の一つでしょうか」とヴェヒターは笑いながら尋ねた。
「私は神学者ではない。なぜ神学者、医師、法律家がいるのか、考えてくれ。彼らがいなくともやっていける、彼らを必要としない、それが誰にとっても望ましいことだ。だが誰もが彼らを必要とする、なぜなら罪、病、不正が責め立てるからだ。問題に通じている専門家に高額の支払いをしなければならない。我々の苦痛は痛みを与えるだけでなく、おまけに金銭も支払わなければならない」 (S.196)
寄宿学校と教育についての議論を聞いていたビリングが会話に加わって、指物師シュターデルの話を持ち出す。一卵性の双生児を産んだ妻が産後すぐに亡くなった。双子の世話に子守少女が雇われ、子供たちは洗礼を受け、名前を与えられた。二人に色違いの、それぞれの名前を刺繍したおむつと下着と服をあてがった。ベッドにも名前が描かれたたが、少女が双子を取り違えてしまった。すると、同じ両親から生まれた一組の双子だから取り違えても酷いことではない、とエリーゼは言う。子供たちがそんなに見分け難いなら、間違いは続くだろうし、二人はいつも取り違えられるだろう、というのがエリーゼの考え。
子守少女から、子供を取り違えた、もう双子の区別がつかなくなったと告白されたことが、不幸な成り行きの引き金となった。それを聞いて父親の指物師は考え込んでしまった。そして精神を病んで、施設に運び込まれた。エリーゼは「少し前、私たちは庭師ヘプナーの身に起きたことを聞きました。そして今度はこれです。私には今度の話がヘプナーより暗く思われます。あなたはどう思われます?」 とヴェヒターに尋ねた。「それにお答えするのは難しい。この出来事で彼には何が衝撃だったのか、知らねばならないでしょう。双子の子供は怪我もせず病むこともなく残された。秩序に対する感覚が衝撃を受けたのだろうか?」
ガルは、一卵性の双子で「片方がヨーロッパ、片方がアメリカに住んでいて、同じ日に交通事故で亡くなった話」を聞かされたことがあると言い、さらにシャム双生児にまで話を広げる。類似と取り違えが議論になる。
類似についてヴェヒターはこう言う、「はるか相違したものとは、すべて実は類似から発している。類似は誤らせる、誤りは取り違えに通じ、取り違えはまたもやさまざまな結果を引き起こす。それはたいていが滑稽な混乱につながると言われていた。だがそれは恐らく結果が無害で危険がない時のみだろう」
ガルはこう言う、「類似とは何だろうか? それは似たものの記憶だ。しかし取り違えは私がもはや類似に気付かない、似たものを思い出さないところで生じる。同一と知覚されるところではすべて類似は終わる」と。こうしたやり取りの中で、ガルがヴェヒターの入れ替わりを察しているということが、ヴェヒターに伝わるのであろう。
「それでどういう結論になる?」とビリングは尋ねた。二人が去ったあとガルは、彼らとはもう再会しないかもしれないと漏らしてエリーゼを驚かせる。「どうしてそうなるの?」という疑問には答えず、春になれば旅行に行こうと持ち掛ける。「どこへ行きたい?」との問いに、「あなたの行きたい所へ」という答え、夫妻のほのぼのとした(?)やり取りで物語は終わる。ここに登場した人々は今後どうなるのだろう。様々な《話中話》としての挿話と議論と謎めいた考察の脈絡があいまいなままだ。名前だけ出てきて説明のない人物があるし、途中経過が抜けているのではと疑わせる出来事の描写があり、これはひょっとして長篇小説を、あちこち削って中篇に縮めたのではないか、とすら思えてくる。
「ここから私が導く結論は、指物師は一人の哲学者だった、類似、一致、同一性について考え込み、そんな難しい問題を考える人間には生まれついていなかったので、病になった」
「あなたは相変わらず冗談ばかり」とエリーゼは言った。
「いや、ここから真面目が始まる。概念などは同一であり得る、しかし二人の人間は決して同一ではありえない。一人の特定の人物について、もし疑問が生じたなら、それはこの人であり別人でないと確定され得る;その人物だと同定される。その証拠は、もし立証しなければならないとすれば、必ずしも容易に得られない。我々はアイデンティティに関しては容易に信じるし、またそうでなければならないだろう。目前にいるのはこの人であり別人ではないと我々は最初から認める。証明書を求めることはない。そして証明書が求められるところであっても、同一性について疑われることはまずない。証明書は本物かあるいは偽物かどちらかである。多くの証明があれば同一性は確定されるだろうか? 本物の証明書でも、それを持参しているのとは別の人物のものかもしれない。間違った、あるいは偽造された証明は同一性に触れる必要は無い」 彼は話し止め、ヴェヒターの方を向き、見つめて付け足した:「はっきりしていますか? 分かるように話したでしょうか?」
「完全だ」とヴェヒターは答えた。彼は思案し前方を見つめた。「だがそこからどういう結論が出るのですか?」
「何も、我々を不安にさせるようなものは何も。だが指物師の心で生じた不確かと混乱は一層深い。それはアイデンティティなるものが測鉛の達しない深さの秘密だからだ。他の人たちは、我々自身は、自分が誰か知っているだろうか? 子供の写真を見る男がいて、その子供は見ている男と同一だろうか? 再認知は類似性に基づく、類似が終わるところ、再認知は止む」
「納得できる」とヴェヒターは言った。話に休止が生じた、彼は時計を見て語らいを終わらせた。「遅くなった」彼は呟いた。「出かけるときだ、私はまだすることがある」
「まあ突然に?」とエリーゼは驚いて尋ねた。しかしビリングも立ちあがって別れを告げた。 (S.201f.)
この作品のドイツ語原題は "Kreuzwege" で、複数の『十字路』である。作中に登場する人物はそれぞれの機縁で岐路に立つ。十字路は様々な出会いと別れの場となる。ガル夫妻の住む家も十字路となり、ここを訪れる人々も、交差してそれぞれの進路に別れて進んでゆく。だが、なぜヴェヒターは別のヴェヒターに成り代わったのか、そもそも語り手のガルとは何者なのか、などなど多くの謎が解決されずに宙ぶらりんで物語は終わる。何よりも気がかりなのは、エリーゼとも姉のゲルトルートとも微妙な関係で、ガルと氷上にあって湖の水深が深いことを願ったり、森林監督が「彼女は思いのままに振舞う、彼女は火と戯れる」と評するヴェロニカのこと。 "Kreuzweg" は十字架への受難の道行でもある。
[使用テキスト: Friedrich Georg Jünger: Werke. Erzählungen 2 (Klett-Cotta, Zweite Auflage, 2004) S.153-204]
* 成年 mündig / Volljährigkeit
地域によって異なるが、ドイツでは1876年から21歳、1950年からDDR(東ドイツ)では18歳、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)では1975年以前は21歳、それ以降は18歳となった。
** am breiten oder spitzen Ende, beim Stiel oder Kelch (S.166)
リンゴ、ナシなどは花托が肥大した部分を食用にする。いわゆる芯の部分が外果皮-内果皮にあたる。
*** Kalville リンゴの種類、甘くて十九世紀には珍重されたようだ。
**** expressis verbis 明示的ニ言フコト

